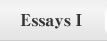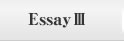第2章 自我論的視点
第2節 意識
1.意識の誕生
前節で見たように、原初の意識は自分についての了解である。胎内で目も見えず耳も聞こえず、その他の感覚も未発達な胎児が最初におぼろげに感じるのは自分である。ここでいう自分は反省以前の<じぶん>、すなわち非言語的な自己性である。原初の意識は自己性の了解として誕生する。羊水に包まれてまどろむ胎児に自己性の了解として意識の領域が開け、意識において自分が自分に現れる。自分が自分に現れるとは、自分を意識して自分として了解することである。胎児が自分というものに気づいて自分を了解することによって意識が芽生える。こうして開けた意識の領域で自分が自分に現れ、自分が自分を意識する。といっても胎児が自分を了解することと、自分が自分に現れることと、自分が自分を意識することは順を追って起こるのではない。意識が誕生する局面でそれらはまったく一つのことである。自分の意識が生まれるためには自分を了解していなければならず、自分を了解するためには自分が自分に現れていなければならず、自分が自分に現れるためには意識の領域が開けていなければならない。意識とは自分が自分に現れることであり、自分とは自分が自分として了解されることである。胎児のなかで意識と自分の了解は一体のものとして目覚めて意識の領域が開けるのである。
胎児のなかで最初に意識が自分に向けられて自己性の了解として誕生すると、胎児の意識のまなざしはゆっくりと胎内の環境に向けられる。周囲の環境を探知する意識作用として感覚が生まれる。感覚は周囲を探知して直接環境から刺激を受けるという観点からは意識の一次形態である。ここで用語について言及すると、「感覚」は、周囲を探知する能力の側面を強調して「感性」と呼びかえてもよく、あるいは周囲から刺激を受ける側面を強調して「感受」と呼びかえてもよい。胎児は嗅覚や触覚や味覚を使って自分の周囲を探知する。感覚によって音や振動など外部からの刺激が探知される。胎児は快い刺激にたいしては満足の表情を見せ、不快な刺激にたいしては拳をにぎって防御の姿勢をとったり、渋面をつくって不快感を示したり、ときには羊膜の壁を足で蹴って抗議する。自己性の了解が次第に鮮明になるにつれて、外部からの刺激は自分ではないものとして意識されるようになる。
胎内では周囲の環境は漠然と自分ではないものとして了解されている。胎児の原初の意識が自分の意識であるのにたいして、感覚は環境の意識である。環境の意識である感覚の中心にはつねに自分の意識がある。この自分の意識に、感覚の意識作用によって自分ではないものの意識が出現する。このとき自分の意識に自分ではないものが出現することによって、自分の意識に自分ではないものの意識が重なる。感覚が発達するにつれて自分ではないものの意識は次第に明瞭になり、それと並行して自分の意識も鮮明になる。最終的に意識は、自分の意識であると同時に自分ではないものの意識として成立する。これは自分の意識であると同時に環境の意識であるという人間の意識の原型である。
発生論的に見れば、意識は周囲の自然を探知する働きとして生じた。この自然の探知において、所与として与えられた自然の事物を直接的に受容するのが感覚である。感覚は、周囲の自然を探知して自然の事物に関する情報を収集する意識の働きとして発達した。視覚は周囲の環境を見るように、聴覚は周囲の音を聞くように、触覚は周囲の自然に触れるように、味覚は自然の事物を味で弁別するように、嗅覚は周囲の事物を嗅ぎわけるように、そして痛覚は身体を害するものを察知するように形成された。感覚が収集した情報を処理して把握するのが知性である。本論では知性を、感覚が集めた情報を処理して知覚を形成する意識の働きとして定義する。「知性」という用語は、感覚情報を処理する能力の側面を強調して「知的能力」と呼んでも、伝統的語法にならって「悟性」と呼んでもいい。肝要なのは、自然のなかで生存することを目的として、周囲の環境に関する情報を収集するために感覚が生まれ、感覚が集めた情報を処理する能力が発達したことである。このプロセスをより効率的に行うために神経回路が発達し、神経回路の束として脳が形成された。その結果、自然の事物が与えられ、それを感覚意識が受け取って知性が処理するために脳が活動するようになった。ここに<所与-意識現象-脳活動>という方向のプロセスが成立する。
ここで留意すべきは、本論で考察の対象とするのはあくまでも意識の働きであり、意識の脳科学的な仕組みではないということである。本論は感覚を意識の働きと捉えるのにたいして、感覚を脳の感覚中枢の作用として捉えるのが脳科学である。本論で感覚による情報の収集や知性による情報の処理と呼んでいる意識の働きは、脳科学では脳の神経回路の作用として説明される。脳科学に限らず科学一般はある現象を説明するために、その現象の背後にある構造とその機能を解明することをめざす。それは意識現象についても同様で、脳科学は意識現象を神経回路の物理化学的なプロセスとして説明しようとする。脳科学は脳の客観的な構造や機能と主観的な意識体験を区別せず、意識現象は物理化学的なプロセスによって説明しつくせると主張する。これにたいして「心の哲学」は基本的に、意識現象には主観的側面があるため物理化学的なプロセスで説明しつくすことは難しいという立場にたつ。だが、脳科学的な知見から意識現象を説明しようとする点では「心の哲学」も脳科学と同じ方向にむいている。<所与-意識現象-脳活動>の方向では、所与として与えられた自然の事物が感覚意識を介して脳神経の活動を引き起こす。そのため脳科学はどの感覚刺激がどの脳領域の特定のニューロンを発火させるか原理的に説明できる。だが、逆に脳の活動からどのように意識現象が生じるかという「心の哲学」が設定する問題は「ハードプロブレム」1)である。おそらくこの難問に答えが与えられることはなく、できることといえばせいぜい問題設定を精緻化することだけだろう。なぜなら、そもそも自然において<脳活動-意識現象-所与>という逆方向のプロセスは成立しないからである。
2.意識の特性
前節で見たように、意識は自己性の了解として自己参照的に統一されている。自己参照的であることは意識そのものの発生に淵源する意識の本質である。この意識の本質から意識のいくつかの重要な特性が導き出される。
意識の第一の特性は、意識は意識そのものを意識することである。意識が意識そのものを意識することを反照と呼ぶ。反照は意識の基本的構造である。反省は意識を対象化して観察する意図的な意識作用であるが、およそ反省が可能であるのは意識の反照構造にもとづいている。反省によって意識を対象化できるのは、意識そのものが反照によって自分自身を意識するからである。意識が反照によってみずからを意識する構造になっていなければ、意図的に意識を反省することは不可能である。意識が反照を基本的構造としているのは、意識が自己性の了解として自己参照的に統一されていることに起因する。原初の意識は非言語的な自分、すなわち<じぶん>の了解として誕生する。<じぶん>とは自分という言葉の意味の根源である。意識がみずからを指し示すことにおいて<じぶん>が了解される。この意識の反照構造を保ったまま非言語的な<じぶん>が言語化されて「自分」となり、さらに「自分」が人称化されて「私」となる。それに対応して<じぶん>の了解は「自分の意識」、そして「私の意識」となる。
意識は反照によって自分自身を意識するのであるから、意識は本質的に自己意識である。光は周囲を照らすと同時に光自身を照らす。自己意識でない意識がありえないのは、みずからを照らさない光がありえないのと同じである。「自分の意識」は、「自分が意識する」ことと「自分を意識する」ことを包含した潜在的な自己意識である。また、「私の意識」は「私が意識する」ことと「私を意識する」ことを包含した顕在的な自己意識である。
意識は反照構造にもとづきそれ自体で自己意識であるが、自己意識の強度、つまり自我が意識される度合いはつねに一定ではない。意識はあるものの意識であると同時に自分の意識であるが、意識があるものに向かっているとき、とりわけ意識がその注意を引きつける外部の対象に集中しているとき自我は背景に退いている。しかしその場合も自我が意識の水面下で意識されていることには変わりはなく、意識の対象への集中度が弛緩するにつれて再び自我が顕在化する。意識が外部の対象に向かっているときに自己意識は背景に退いているのとは逆に、意識が自分自身にまなざしを向けると自我が顕在化して顕在的自己意識となる。意識作用を統御する自我は意識のいかなる状態でも不変であるが、自我の顕在化の程度はそのつどの状況でさまざま異なる。
意識の第二の特性は、意識はつねにあるものの意識であることである。意識があるものの意識であるのは、意識は本来的に環境の意識であることに由来する。意識があるものの意識でないとしたら、したがってなにものの意識でもないとしたら、それは意識ではありえない。あるものの意識ではない意識、それゆえいかなる内容ももたない意識というものは存在しない。意識は、そのつどの環境において働く欲求、感覚、感情、意志、知覚、思考などの意識作用である。これらの意識作用は複合してつねにあるものを意識している。しかしおよそ意識があるものを意識できるのは、意識そのものが自己参照的に統一された意識、すなわち「自分の意識」として成立しているからである。
意識があるものの意識であるとは、意識はつねにあるものに向かっていることを意味する。意識がこのように志向的な性格をもっているのは、根本的には人間がこの世界で所与に引き渡されているからである。人間はこの世界に生まれて世界の構成要素に囲まれており、世界の構成要素は人間に所与として与えられている。意識があるものに向かうとは、意識が意識に与えられた所与とつながりをもつことである。具体的にいえば、意識はあるものを見たり、聞いたり、好いたり、嫌ったり、判断したり、評価したり、意欲したり、排斥したり、その他ありとあらゆる精神的行為によってあるものとつながっている。
意識は自分の意識であると同時に環境の意識であるから、そのつど環境に規定された内容を含んでいる。たとえば私はいま自分の仕事場で目の前のパソコンの画面に視覚と思考を集中させているが、同時にパソコンの背景にある書棚もぼんやりと見えており、その横にある窓も視界にはいっている。頭を少し下げるとキーボードと椅子が見え、さらにゆっくりと頭の向きを転じるにつれて入口のドアの像が意識の視界にはいってくる。部屋の温度はエアコンによって快適に調整されている。触覚に注意を向ければ私の背中は椅子の背もたれに接触しており、臀部はしっかりと体重を受けとめ、足は靴下とスリッパをとおして床面を感じている。意識の焦点を身体内に転じれば、胃もたれ感や肩のこりが意識される。聴覚に注意を集中すると、エアコンから空気の吹き出し音が聞こえる。壁にかかっている時計に耳を傾けると、これまではまったく聞こえなかったが驚くほど大きい音で1秒1秒刻んでいるのがわかる。窓の外からは車が接近して遠ざかる音が聞こえ、ときどき人の声もする。こうした身の回りの出来事はつねに意識されている。すなわち、それらは実際に見られ、聞かれ、触れられている。だが、それらすべてに常時均等に意識の焦点が振り向けられているわけではない。もし背中と椅子の背もたれの当り具合が気になっていたら、仕事に集中できないので、仕事に没頭しているあいだは背中も椅子の背もたれもすっかり忘れ去られている。しかしそれは完全に意識されていないのではなく、意識の焦点の背景に退いているだけである。意識の焦点の微妙な変化によって時計の秒針の音やエアコンの振動音が耳にはいり、背もたれの感触も意識される。こうしたすべての要素に注意が均等に振り向けられてはいないが、思考や感覚や感情その他の意識作用がたえず働いている。
意識の第三の特性は、意識はその本質において関係であることである。関係とは、意識がその志向性によってあるものとさまざまな仕方でつながることをいう。関係は本質的に意識の事柄である。関係が意識の事柄であるとは、関係は関係の意識であることを意味する。あるものと関係するとは、あるものと自己参照的に関係することである。自己参照的に関係するとは、みずからが関係していることを意識することである。それゆえ意識のないところに関係は成立しない。関係することは意識作用であり、あらゆる意識作用は意識作用の動作主として意識する主語を前提とする。意識作用で意識する主語をなすのは自我である。意識作用として関係が成り立つためには、自我による統御を必要とする。関係は自我が主語として関係することを統御することによってはじめて成立する。
視覚を例にとると、対象を見るとは、見ることをとおして対象とつながること、すなわち対象と視覚的に関係することである。人間の目とカメラと比較すると、目は物体の反射光を角膜、瞳孔、水晶体をとおして網膜上に結像させる。この構造はカメラがレンズと絞りをとおして対象をフィルム上に結像させるのと基本的に同じである。光学的な結像の仕組みとしてはカメラと人間の目に違いはない。しかし人間の目とカメラでは決定的に異なる点がある。それは人間の目は対象を見るのにたいし、カメラは対象を見ないことである。カメラで起こっているのは、対象から反射した光が光学系を通って感光材料に結像するという物理的プロセスである。カメラは対象を反映するだけで、対象を見ることはけっしてない。対象を見るのは、あくまでもカメラのファインダーをのぞく人間である。なぜなら見ることは意識作用であり、視覚の意識作用は自我によって「私が見る」という意識構文で統御されなければならないからである。
意識はあるものと関係することにおいて関係していること自体を意識する。それは意識が意識そのものを意識することにもとづいている。見ることを意識しない視覚が成り立たないように、関係していることを意識しない関係はありえない。カメラが対象の反射光を受容しても対象を見ないのは、カメラは単に対象の光を受容するだけで当の対象と関係しないからである。関係が成立するためには関係の主語がなければならず、関係の主語となりえるのは意識作用の主語としての自我である。自我は対象との関係において対象と関係していることを意識している。自我は対象と関係していることを意識してはじめて意識に現れ、意識に現れる限りで関係の主語であることができる。あるものと関係するとは関係を意識することであり、関係を意識するとは関係の主語である自我を意識することである。
3.意識の自発性と所与性
生命の本質はみずから生きようとする自発性である。自発性とは、他から規定されることなくみずから作用することをいう。意識は生命の発現であり、それ自体で自発的である。意識作用は本質的に意識の自発的な働きである。自発的な意識作用において自我は意識を「私が意識する」という一人称の意識構文で統御する。「私が意識する」ことにおいて私に先行する主語はなく、意識は必ず「私が意識する」ことによって開始する。
自我は「私が意識する」という自発性において意識に顕現する。あらゆる意識に自我が顕現して意識作用を統御する。自我が意識作用を統御しなければ、意識作用が「私が意識する」という統語的構造で働くことはなく、その場合は意識作用そのものが成り立たない。もし「私が意識する」のでなければ、意識は私とは別の者が意識することになろうが、それはもはや「私の意識」ではない。「私の意識」を私以外の者が意識することはありえないのと同様に、「私の意識」ではない意識、つまり私とは別の者の意識を私が意識することもありえない。意識はつねに「私の意識」であり、「私の意識」は「私が意識する」ことにおいて私自身に意識される。
具体的な意識の内容はそのときどきの状況に規定されて変わるが、意識の内容がどれほど変わろうともつねに変わらないのは「私の意識」である。意識はその内容をめまぐるしく変えながらもつねに「私の意識」として連続している。具体的な意識作用はそのつど思考や感情や気分などであるが、それぞれ私の思考、私の感情、私の気分としてしか存在しえない。意識がそのときどきに思考や感情や気分としてその姿を変えようと、またそれらの思考や感情や気分自体がどのように変化しようと、「私の意識」としてつねに同一である。「私の意識」は、「私が意識する」ことと「私を意識する」ことを包含する顕在的自己意識である。「私の意識」は、私自身がそれを意識することによって顕在的自己意識として成立する。
「私が意識する」ことにおいて私に先行する主語はないが、私によって意識されるものは私に先行する。意識はつねにあるものの意識であり、意識作用が成り立つためには、意識されるものがなければならない。「私が意識する」ことにおいて私によって意識されるものがなければ意識作用そのものが成り立たない。「意識はあるものの意識であると同時に自分の意識である」という意識の本質的な構造を言語化すれば、「私があるものを意識する」と「私が私を意識する」という構文になる。「私があるものを意識する」の構文において「私」は主格であり、「あるもの」は目的格である。意識は主格によって成り立つと同時に、目的格を必要とする。
「意識はあるものの意識である」とは、意識がそのつどの意識作用の結果を受容することである。意識作用の結果を受容しない意識はありえない。意識するとは、私が意識すると同時に私の意識の内容を受容することである。私が意識する側面では自我が自発性において意識に顕現し、意識の内容を受容する側面では私によって意識されるものが所与性において意識に立ち現れる。この場合、私の意識は、私に先行するものの意識として成り立つ。この点で見れば、意識はつねに所与として意識に先行するものの意識である。「私が意識する」ことにおいて私が主語として意識に顕現するのも、そのつど所与として私に先行するものの意識を受容することにおいてである。所与として意識に先行するものの意識を受容することにおいて、自我がその意識作用の主語として意識に顕現するのである。
意識作用が成立するためには、自我が意識作用を実行すると同時に、実行された意識作用の結果が自我に与えられなければならない。意識作用の結果とは、「私が意識する」ことの内容である。意識作用が「私が考える」ことであればそのつどの思考内容であり、「私が見る」ことであればそのつどの視覚像であり、「私が感じる」ことであればそのつど感受した内容である。意識作用はその結果が与えられてはじめて成立する。たとえば「私が考える」という意識作用が成り立つためには、同時に考えられた内容が自我に与えられるのでなければならない。思考には明晰な思考から漠然とした思考まで幅があるが、自我はいかなる思考内容ももつことなく思考することはできない。意識作用の結果が与えられるとは、意識作用の結果が自我に所与として与えられ、自我がそれを受容することである。自我が考えるとき、考える内容が自我に与えられて受容される。自我に受容された結果は私の思考内容として捉えられる。知覚の場合も、「私が見る」という意識作用は見られる像がなければ成立しない。見ることによって自我に視覚像が与えられ、それが私の視覚像として捉えられる。自我は意識作用を統御することによって意識作用を実行すると同時に、意識作用の結果を所与として受容する。
4.能動性と受動性
以上見たように、自我は「私が意識する」という自発性において意識作用を統御するとともに、所与性において意識作用の結果を受容する。この自我の自発性と所与性における意識の成り立ちから、意識の能動性と受動性が明らかになる。意識は、自我によって自発的に統御された意識作用という側面で見れば能動的である。この側面で意識は自発的な意識作用として作用する能動的意識である。しかし同時に意識は、意識作用の結果が所与として受容される側面で見れば受動的である。意識作用の結果が所与として受容されるとは、そのつどの具体的な意識内容が自我に与えられることである。この側面では意識は受動的意識である。能動的な意識作用はそれ自体では成り立たず、意識作用の結果が所与として受容されなければ成立しない。なぜなら意識はつねにあるものの意識であり、あるものの意識でない意識はありえないからである。あるものの意識とは総じて環境の意識であり、環境の意識は意識作用によって意識された結果である。この意識作用の結果が能動的意識に受容されてはじめて意識作用そのものが成り立つ。能動的意識と受動的意識は、意識作用において一体化されており、能動的意識はそれが成り立つために受動的意識を必要とし、受動的意識はそれが成り立つために能動的意識を前提とする。
視覚を例にとるならば、目の前に降り積もっている雪を見る視覚は、雪の白さをまざまざと捉えている。視覚の意識作用は、「私が見る」という構文で自我に統御されている。見るという視覚の意識作用は能動的意識である。しかし、雪そのものは視覚によって生み出されたわけではなく、視覚の意識作用に先行する。目の前に積もった白い雪は視覚によっては変えることのできない事実である。白い雪は意識にたいして与えられたもの、すなわち意識の所与である。視覚の意識作用において「私が見る」という意識は能動的意識であるが、現に見ている視覚像は意識に与えられた受動的意識である。この場合、視覚は雪を見ることと雪が見えることが同時に成立しており、能動的意識と受動的意識が一体となっている。これは雪を目の前に見るのではなく、頭のなかで思い浮かべる場合でも同じである。頭のなかで雪景色を思い描くにせよ、子供のとき作った雪だるまの記憶がふとよみがえるにせよ、想像の目に雪が与えられていることに違いはない。知覚であれ想起であれ、それぞれ見るものあるいは思い浮かべるものの像が意識に与えられた所与であるという点で変わりはない。「私が見る」という能動的意識は、見られたものを受容する受動的意識において成り立つのである。意識において能動性と受動性が一体不可分であることは特に対象と直接的に関係する感覚の意識作用で顕著である。視覚において雪を見ることは雪の像が与えられることであるように、対象を見るという能動的側面と、見られた対象が与えられるという受動的側面が一体となっている。
聴覚の例でいえば、コンサート会場でピアニストが舞台に登場して、ピアノの前に座り鍵盤に両手を添えて深く息をしたあとおもむろにその手を持ち上げたとき、観客は意識を集中して耳を傾ける。次の瞬間、軽やかなピアノの音が聞こえてくる。この場合は演奏に耳を傾けるという行為によって、音を聞くという意識作用が実行される。音を聞くことは能動的な意識作用である。しかしそれによって聞こえる音そのものは所与である。音を聞くこと自体は能動的意識であるが、それは音が聞こえるという受動的意識を伴う。この場合、聴覚は音を聞くことと音が聞こえること、つまり能動的意識と受動的意識が一体となって成立している。これはコンサート会場を出て、いま聞いたばかりの演奏を思い出す場合でも同じである。コンサート会場という物理的空間にいる状態で聞くのではなく、まったく頭のなかで自発的に音を生み出すのであるから、この行為は純粋に能動的である。しかしこの自発的行為によって生み出される音の記憶は所与であり、そこにあるのは音、正確には音の余韻が聞こえるという受動的意識である。この受動性は自分で実際に音を出してみれば、もっとはっきりする。机の表面を指で叩くと乾いた木の音がする。机を叩いて音を出すことは能動的な行為であり、その音を聞くことは能動的意識である。しかし木の音そのものは意識が生み出したものではなく、聴覚に与えられたものである。それゆえ音の意識は受動的である。音を聞くのは能動的意識であるが、音が聞こえるのは受動的意識である。音を聞くのは、あくまでも音が聞こえるという受動的状態においてである。音を聞くという能動的意識は、音が聞こえるという受動的意識において成立するのである。
能動的意識と受動的意識が不可分であることは、視覚や聴覚に比べて味覚や嗅覚や触覚の場合にいっそう顕著である。なぜなら視覚や聴覚が空間を介するのにたいし、味覚や嗅覚や触覚の場合はより直接的だからである。空間を介するとは、知覚されたものを空間に定位することである。たとえばなんらかの光景を目にして、あるものは遠くにあり、別のあるものはそれより近く、さらに別のあるものはすぐ間近にあることが知覚される。音の場合も遠くの音と近くの音を区別する際には空間が介在している。雪景色の例でいえば、雪は間近にあってその白さが知覚されているが、雪と感覚のあいだには空間が介在しているのでその冷たさを感じることはできない。雪のなかに手を入れて実際に雪と触れてみて、はじめて雪が冷たいことを実感できる。このとき意識は物体の冷たさを感じる冷覚として作用する。その作用はつねに「冷たい」という意識の状態として現れる。「冷たい」という意識の状態がなければ「雪に触れる」という触覚を意識することはできない。触覚の作用がなければ冷たさを感じることはありえないが、実際に触覚の作用を意識するのは「冷たい」という感覚そのものにおいてである。感覚という意識の能動的な作用は、その作用の結果である「冷たい」という意識の状態で発揮される。同様のことは、嗅覚の場合は匂いを嗅ぐことと匂いが与えられることに、味覚の場合は食べ物を味わうことと食べ物の味が与えられることに該当する。
感覚は一次形態の意識として、それ自体が意識作用である。意識の特性は意識そのものを意識することであるから、感覚は感覚していることを意識する。たとえば触覚は単に接触することではなく、接触することを意識することである。「単に接触する」とは、たとえば金属同士が物理的に触れることを意味する。この場合、触れること自体は意識されていない。どちらの金属が触れて、どちらの金属が触れられるということはない。二つの金属片が物理的に接触しているだけである。これにたいして触覚は、対象に触れると同時に触れることを意識している。触れるのは自分であり、触れられるのは自分以外のものである。触れることを意識するとは、自分が触れることを意識することである。この場合、触覚の意識作用の基底には非言語的な自我である自分があって、主格として意識作用を統御している。触覚の意識作用も自我が主格として統御することによって成立する。
意識は能動的意識としてはそのときどきの具体的な意識作用であるが、受動的意識としてはその作用によって意識に生じる結果である。ここでいうまでもないが、能動的意識と受動的意識が別々に存在し、その二つが合体して意識作用が成り立つというのではない。具体的な意識は、つねになんらかの像や音や味や臭いや触感が与えられるという所与性において生じている。与えられるという局面で見れば意識は受動的である。これにたいして与えられたものを見たり、聞いたり、感じたりするという局面で見れば意識は能動的である。意識の受動的な局面も能動的な局面も、意識の対象が与えられているという所与性を前提としている。意識がつねにあるものの意識であるのは、意識が根本的に所与性において成立しているからである。意識は意識にあるものが与えられることによって、はじめてあるものの意識でありえる。もし意識になにも与えられないとしたら、意識そのものが成り立たない。意識にあるものが与えられるという限りで意識は受動的である。しかしながらそれは意識が全面的に受動的であることを意味するものではない。意識にあるものが与えられるためには、意識にあるものが与えられるという事態そのものが可能でなければならない。意識にあるものが与えられることは、意識がその与えられたものを受け取ることが前提である。意識が与えられたものを受け取ることができなければ、意識になにかが与えられるということは起こりえない。意識が意識に与えられたものを受け取ることが可能であるためには、そこに意識の能動性が働いていなければならない。意識が与えられたものを受け取るとは、意識がその与えられたものを意識することである。意識が意識に与えられたものを意識するのでなければ、意識にあるものが与えられるという事態は成立しない。つまり意識があるものを意識することなくして、なにものも意識に与えられることはできない。意識はあるものを意識するという能動性によって、意識にあるものが与えられることを可能にし、その結果として意識はつねにあるものの意識として現れるのである。意識することと、意識にあるものが与えられることとは、根本的に相補関係にある。意識の能動性は意識にあるものが与えられることを可能にするが、この意識の能動性が発揮されるのは意識にあるものが与えられることを前提とする。つまり意識の能動性は、あるものが与えられるという受動税において発揮されるのである。
5.認識
意識は、人間が周囲の自然を探知するために発生した。意識はその出自からして人間と自然との関係である。人間と自然との関係において、意識は自然の事物を意識する側面では能動的であり、自然の事物が意識に与えられる側面では受動的である。意識がつねにあるものの意識として具体的な内容を伴うのは、意識がそのつど与えられた自然の事物を受容することによる。能動的側面では、自我は意識作用を統御して「私が意識する」という主格の構えで自然に働きかける。受動的側面では、意識する内容が所与として与えられる。「私が意識する」ことにおいて私に先行する主語はなく、自我によって統御される意識作用は自発的である。
人間はつねに意識を介して自然と相対している。自然と相対して生きるために、周囲の状況を認識し、その認識にもとづいて適切な行動を取らなければならない。ここで認識を定義すると、認識とは関心の対象となるものを把握する意識作用である。人間にとって究極の関心は生存することであり、最大の関心の対象は生存環境である。生存環境を認識する一次的な意識形態は感覚である。感覚は環境の意識として生存環境の情報を集める。たとえば目の前にある自然の事物について色や匂いや手触りや味などの情報を収集する。感覚が集める情報は直接事物に接して得られる生データである。感覚が直接事物に接して受容する生データを感覚情報と呼ぶ。感覚情報は、感覚が接する事物の色や匂いや音などといった感覚刺激の内容である。
感覚が集めた情報を処理して知覚を形成するのは知性である。事物の感覚情報が知性によって処理されることにより、事物がなんであるか特定されて知覚が成立する。ここで知覚を感覚との関係で定義すると、知覚とは感覚情報にもとづいて事物をある特定のものとして認識することである。感覚情報が事物に関する生データであるのにたいし、特定された事物の情報を知覚情報と呼ぶ。知覚情報は、目の前の事物についての感覚情報から知性による処理を経て形成される。知性は、感覚が集めた事物に関する情報を処理して知覚情報を形成し、それにもとづいて状況を認識して人間を環境に適応した行動へと促す。感覚と知性が協働してもたらすのは、生存の基礎となる状況の認識とそれにもとづく行為である。
知性は感覚が集めた情報を処理して知覚を形成し、知覚にもとづいて周囲の状況を認識する。認識は、知性は状況認識にもとづいて取るべき行動を決定し、身体に命令する。身体は知性の命令に従って行動することによって環境への適応を図る。感覚による環境の探知と情報収集、知性による情報処理と状況認識、それにもとづく行動の決定と命令、および身体の適応行動は、人間と自然との関わりにおいて進行する基本的なプロセスである。この情報入力から行動出力にいたる一連のプロセスが成立するのは、それぞれのプロセス段階における行為が統一された意識のもとでなされるからである。それらの行為が統一された意識のもとでなされずにばらばらにおこなわれたなら、入力情報と出力情報のあいだに合理的な関連性がなくなり、情報の収集と処理の努力も有意味な行動につながらない。すべてのプロセス段階が統一された意識のもとでおこなわれるからこそ、情報収集から身体行動までの一連の行為が特定の目的に向けて合理的に遂行されるのである。それぞれのプロセス段階における意識作用が統一された意識のもとでおこなわれるためには、すべての意識作用が同じ主語のもとに統御されていなければならない。こうした意識作用の主語をなすのは自我である。情報を収集する感覚と収集された情報を処理する知性が発達するには、両者を統御する機能として自我が誕生していなければならない。自我は感覚と知性の意識作用を統御すると同時に、同じ自我のもとに意識作用と身体を統合し、それによって統御された行動を可能にする。
生命の発現としての意識の作用は根本的に生きることに動機づけられている。意識の一次形態である感覚も、自然のなかで生存するために周囲環境を探知することを目的としている。感覚によって収集された情報を処理するために知性が発達した。感覚が集めた情報を知性が処理して知覚を形成し、それにもとづいて目の前にある事物が生きるのに有害であるか危険であると知性が判断すれば回避し、逆に生きるための栄養になると判断すれば摂取を促す。この周囲環境の情報の収集と処理は、先に述べた意識と自然の関係が所与と感覚と知覚によって、<与えられる-受ける-取る>という一連のイベントとして成就することと対応している。自然の事物が所与として与えられ、感覚がこれを受容し、知性がその情報を処理することによって知覚が成立する。意識は自分の意識として自己に向かうとともに、環境の意識として自己を取り囲んでいる周囲の自然に向かう。人間は意識によって自然と交流してつながりを保つ。人間と自然との関係において、意識は意識作用として能動的に自然に働きかけるが、それは自然の事物が所与として受動的に与えられることを前提としている。しかしまた自然の事物が所与として与えられることは、意識がそれを受け取ることによってはじめて成り立つ。なぜなら自然の事物を受け取るということがなければ、自然の事物は存在するだけで、人間に与えられたことにはならないからである。この点で「受け取る」という日本語は、意識と自然の基本的な関係をきわめて的確に言い表している。「受ける」ことは意識になにかが与えられてはじめて成り立つ。意識に与えられるものがなければ、意識がそれを受けることはありえない。しかしまた意識が「受ける」ことは、意識がそれを「取る」ことによってはじめて成就する。「取る」とは意識に受動的に与えられたものを、意識が能動的に取得することである。「与えられる」ことを所与、「受ける」ことを感覚、「取る」ことを知覚と解すれば、意識と自然の関係は基本的に所与と感覚と知覚によって成り立つ。感覚が集めた情報を処理して知覚を形成するのは知性である。感覚が環境を探知して直接環境から刺激を受けるという点で意識の一次形態であるのにたいし、知覚は感覚情報を知性が処理することによって形成されるという点で意識の二次形態とみなすことができる。
意識は自然を探知する側面では能動的であり、自然の事物が感覚に与えられる側面では受動的であり、さらにそれを処理して知覚を形成する側面では再び能動的である。先に掲げた「意識はその本質において関係である」という定義を人間と自然との一次的関係に即して再定義すれば、意識とは自然との<能動=受動関係>である。意識は自然にたいして能動的であるが、意識が自然にたいして能動的でありえるのは、意識が自然にたいして受動的であることにおいてである。意識の自然にたいする能動性は、意識の自然にたいする受動性において成り立っている。意識は根本的に自然との<能動=受動関係>として成立する。意識の本質は自然との<能動=受動関係>であり、自然の事物は意識と自然の<能動=受動関係>において意識に現れる。意識はそれ自体で能動的であると同時に受動的であり、意識が意識として成り立つためには、意識するものが意識に与えられなければならない。意識とは必ずあるものを意識することであり、なにものも意識しない意識というものはない。あるものを意識すること自体は能動的であるが、同時に意識する当のものが与えられる限りで受動的である。意識があるものの意識であるとは、あるものが意識に与えられることである。
人間と自然との交流において意識は自然の事物を意識する側面では能動的であるが、自然の事物が意識に与えられる側面では受動的である。すでに見たように、自我は「私が意識する」という構文で主語として意識作用を統御する。これは意識の能動的側面であり、自我は「私が意識する」という自発性においてみずからに顕現する。それと同時に自我は受動的側面では、意識内容を所与性において受容する。自我は、意識内容を所与性において受容することをとおして意識作用を統御する。自我が意識作用を自発的に統御する能動的意識と、意識内容を所与性において受容する受動的意識が一体となって具体的な意識が成り立つ。具体的な意識において能動的意識と受動的意識は完全に一体をなしていて切り離すことができない。具体的な意識作用において能動性と受動性は一体不可分である。この意識と自然の<能動=受動関係>は、人間と自然との関係が根本的に相互作用であることにもとづいている。
6.自然の一部
自然は、生物が生きるための最も基本的な環境である。自然は生物が生存するために必要不可欠なすべてのものを提供する。自然はすべての生物の生存基盤である。人間にとっても自然は基礎的な生存環境であり、人間は自然から生命を与えられて生きている。自然から生まれた人間は自然の事物で作られており、それゆえ絶えず栄養源として自然の事物を摂取しなければならない。人間は自然から生まれ、自然によって生きているのであるから、人間と自然の関係は人間がこの世界で取りむすぶあらゆる関係の基礎をなしている。この意味で人間と自然の関係を一次的関係と呼ぶことができる。
人間はこの世界に生まれて特定の環境におかれ、そのときどきの現実に直面する。現実とはそのつどの環境における人間と事物の諸関係の総体である。人間以外の生物が自然と直接的に密着して、自然そのものを自然環境として構成しているのにたいして、人間は自然と一次的関係にありながら生物のように自然と直接的な関係にはない。現実には人間と自然との関係は現実の諸関係によって媒介されているからである。人間と自然とのあいだには技術や生産や流通などの生産関係、さらには政治や経済や法律などの制度が介在している。その根底にはつねに人間と自然の一次的関係がある。その意味で現実とは現実の諸関係に幾重にも媒介された人間と自然との関係である。人間と自然の関係を基礎とする現実の諸関係は人間と自然の二次的関係ということができる。
二次的関係としての現実の諸関係は、人間と自然との一次的関係に基礎をおいている。複雑に絡み合った現実の諸関係を起源に向かってたどっていくと、必ず人間と自然の関わりにゆきつく。これは、現実の諸関係がどれほど複雑に発展しようといささかも変わらない。なぜなら人間は他のすべての生物と同様に自然から生まれ、自然の事物によって形成されており、生きていくために自然との関係を維持し、絶えず自然と交流しなければならないからである。自然との不断の交流は、人間が存在するための絶対的条件である。人間はもともと自然の一部であるという事実が、人間のあらゆる物質的生活と精神的生活の根本をなしている。
「自然の一部」という言葉はカール・マルクスの死後1932年に出版された『経済学・哲学草稿』にも登場する。そのなかでマルクスは人間と自然の関係を、次のように規定している。
「人間の普遍性は、自然が 1. 直接的な生命媒体である限りで、同様に自然が 2. 人間の生命活動の素材、対象、道具である限りで、全自然を彼の非有機的身体とするという普遍性のなかに実践的に現れる。自然、すなわちそれ自体が人間の身体でない限りの自然は人間の非有機的身体である。人間が自然によって生きるということは、自然は、人間が死なないためには、それとの不断の過程にとどまらねばならない彼の身体であるということである。人間の物質的・精神的生活が自分自身と関連しているということにほかならない。人間は自然の一部だからである。」
マルクスにとって人間は自然的存在であると同時に普遍的(=観念的)な存在である。自然的存在であるがゆえに人間はつねに自然と交流しなければならない。しかし同時に人間は普遍的存在であるがゆえに全自然を対象として活動する。マルクスにおいて「人間は自然の一部である」という表現は、人間は自然的存在であると同時に普遍的存在であるという矛盾を内包しており、その矛盾が人間と自然との弁証法的な関わりの原動力をなしていることが含意されている。
マルクスにおいて人間が自然の一部であることが人間と自然の弁証法的な関わりの前提をなしているように、人間が自然の一部であるとは人間が自然と直接的に一体化していることを意味するものではない。むしろ人間は自然の一部であることによって、自然から切り離されているのである。それでは人間は具体的にどの点で自然から切り離されているのだろうか。
第一に、人間は動物として大地としての自然から独立している。身体は鉱物のように大地と一体化しておらず、また植物のように直接大地に根を張ってもいない。固有の身体として自然から切り離された人間は地上を自由に移動できる。この点で人間は「動く物」である。
第二に、人間は固有の身体として自然から切り離されている。それゆえ人間は生命を維持するために絶えず自然と交流しなければならない。そのため間断なく呼吸し、絶えず自然の事物を摂取して物質代謝を行い、老廃物を体の外に排出する必要がある。人間は自然と交流することによってのみ生き続けることができる。
第三に、人間は意識的存在として自然から切り離されている。人間は意識を介して自然と交流し、自然との関係を維持する一方で、意識の働きによって自然の事物とはまったく異質な概念や観念を生み出す。人間は意識によって生物と自然と直接的な関係から離脱する。
人間は自然の一部であるが、それにもかかわらず自然から切り離されている。それゆえ人間は生きるためにはみずからのうちに自然を回復しなければならない。自然を回復するとは、自然との距離を埋めて自然と同化することである。基本的には生命の維持に必要な空気を吸い、水を飲み、栄養を取ることによって自然を体内に取り込むことである。身体は、自然の事物を体内に取り込んで身体の構成物質を合成したり、生命を維持するために必要なエネルギーに変換する。それと並行して、代謝の結果生じた老廃物を体外に排出する。身体は外被によって限定されているため、空気や水や栄養などを摂取する容量が限られているからである。身体は摂取と排出を並行して不断に継続しなければならない。自然の事物の摂取と排泄によって、身体は絶えず自然と同化して生き続けることができる。
自然を回復するために、人間は絶えず自然に働きかけて自然と交流しなければならない。人間は身体的プロセスと精神的プロセスの双方を介して自然と交流する。身体的プロセスは呼吸、栄養摂取、消化、排泄などの身体活動を含み、精神的プロセスはすべての意識作用を包含する。意識作用も身体活動も、自然から切り離された人間が、それでもなお自然の一部として自然との交流を維持するための活動である。人間のすべての活動は、根本的に人間とその生存基盤である自然との交流である。人間がこの世界で生きて営む活動は、現実の諸関係による媒介されて、究極的には自然と自然の一部である人間との抜き差しならない関係に遡源する。
1)デイビッド・ジョン・チャーマーズ 『意識の諸相』(太田紘史訳)