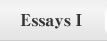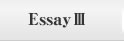第1章 世界論的視点
第1節 世界
1.世界論
本論で追求するテーマは「人間とはなにか」である。もとより人間は一人真空状態のなかで生きているのではない。人間は他の人間や事物のあいだに生まれ、それらに囲まれて生きている。人間はつねに他の人間と交わり、もろもろの事物と関わり、それらとさまざまな関係を結ぶ。生きるとは他の人間や事物に囲まれて、それらと不断に交渉することである。人間を取り囲む無数の事物と他の人間、それらが互いに入り混じって織りなす複雑きわまりない関係、そしてそこから生じる多種多様な出来事の総体として考えられるものを世界と呼ぶ。この総体としての世界を構成している無数の人間や事物を世界の構成要素という。世界の構成要素は、実在する事物や人間だけでなく、観念や想像、仮象や虚偽など、およそ考えられる限りのものを包含する。それゆえ世界はあらゆる構成要素の総体であると定義することができる。人間は世界に生まれてその無数の構成要素に囲まれ、それらと関わりながら生きる。人間の前に世界の構成要素が次々と立ち現れ、人間はそれら無数の他の人間や事物と関係し、それによって新たに世界の構成要素を生み出す。このようにして世界の構成要素は際限なく生じ、互いに複雑に絡み合いながら、かたときもとどまることなく変化する。ありとあらゆる構成要素を包摂する世界は、美しいものも醜いものも、高貴なものも下賤なものも、善も悪もいっさいがっさい呑み込んで変化する。
総体としての世界は、世界のあらゆる構成要素を包摂したものとして想定される。それゆえ世界を構成するいかなる要素も、総体としての世界を越え出ることはない。人間や事物を含むすべての構成要素は世界のなかに存在し、あらゆる出来事は世界のなかで起こる。いうまでもないことだが世界と地球の概念は一致しない。たとえ宇宙飛行士が宇宙ロケットに乗って地球の大気圏外に飛び出したとしても世界を越え出たことにはならない。それはあくまでも世界のなかで起こる出来事である。
人間は世界に生まれ、世界のなかで他の人間や事物と関わりながら生きる。それゆえ「人間とはなにか」というテーマを追求するには、最初に「世界とはなにか」について考察し、世界と人間との関係を明らかにする必要がある。「世界とはなにか」を問い、世界の特性を人間との関係において考察し、あるいは世界との関係から人間の特性を明らかにすることを世界論と呼ぶ。このような観点から立てられる問いは、たとえば「世界が存在するのはなぜか」、「世界はどのような構造になっているのか」、「人間はなぜ世界に生まれるのか」、「人間が生まれてくるのが世界であって別の場所でないのはなぜか」などである。これらの世界論的な問いにたいする答えを探るために、以下では主として世界の特性を表すキーワードとして「必然性・偶然性」および「因果性」、主として人間の特性を表すキーワードとして「所与性・事実性」および「共同性」を切り口にして世界と人間の関係に光を当てる。
2.必然性と偶然性
世界の構成要素としての人間と事物がそれぞれ相互に関わり、人間同士、事物同士、そして人間と事物のあいだで織りなす関係や出来事をおしなべて事象と呼ぶ。あらゆる事象が世界で起こるように、人間が生まれることも世界のなかの事象である。人間はおよそ生まれるならば、世界に生まれるほかはない。人間が生まれてくるのはつねに世界であって、それ以外の場所ではない。これについて人間に選択する権利はまったくない。世界に生まれることを拒むこともできなければ、世界に生まれたことを打ち消すこともできない。人間にとって世界に生まれることは、避けることのできない出来事である。だが、それは人間が世界に生まれることが必然的であるということを意味しない。必然性とは、字義的には「必ず然る」ようにあることである。これにたいして偶然性とは「偶(たまさか)に然る」ようにあることである。
必然性は因果必然性と根拠必然性に分けられる。因果必然性とは、事象がなんらかの原因の結果として然るようにあることである。世界における事象はことごとく因果的関係において成立している。因果的関係とは、過去と現在をつなぐ因果的な脈絡である。因果的関係を構成する原因と結果の連鎖を因果連関という。因果連関は原因と結果の連鎖であるから、因果連関の内部ではすべての事象はなんらかの原因の結果として然るようにある。それゆえ因果連関の内部では原因と結果の必然性が成り立つ。この因果連関の内部で成り立つ原因と結果の必然性が因果必然性である。因果必然性を定式化して「すべての事象は原因によって起こり、原因なしには何ごとも起こらない」という命題にしたのが因果法則である。因果法則によってすべての事象は原因と結果の関係によって説明される。それゆえ世界で起こるすべての事象は原因から生じた結果として把握される
根拠必然性とは、なんらかの根拠から然るようにあることである。根拠とは、物事が然るようにあることの理由となるべきものである。たとえば「人間はなぜ世界に生まれるのか」という問いで問われているのは、人間が世界に生まれる理由である。これを因果必然性に規定された原因への問いと誤解すると、「人間が世界に生まれてくるのは両親の生殖行為の結果である」などと答える。これは、、因果必然性と根拠必然性を同一視して、人間が世界に生まれる理由を生殖プロセスによって説明するものである。生殖過程そのものは因果的なプロセスである。人間の精子と卵子が子宮のなかで結合すれば受精卵が生じ、そこから人間が誕生する。この場合、精子と卵子の結合が原因となって受精卵という結果をもたらす。受精卵の発生という結果は、それに先立つ精子と卵子の結合という原因によって説明される。したがって精子と卵子の結合と受精卵の発生のあいだには原因と結果の関係が成り立つ。だが、そこにあるのは因果必然性であって根拠必然性ではない。根拠必然性で問われているのは、新生児が生まれるまでの原因と結果の連鎖ではなく、およそ人間が世界に生まれてくる理由である。
だが、人間が世界に生まれてくる理由はない。なぜなら人間が世界に生まれる事実に先行する根拠がないからである。人間が世界に生まれる事実に先行する根拠とは、人間が世界に生まれる動機や意図や目的である。人間はなにごとかに動機づけられることもなければ、具体的な意図を抱くことも、特定の目的をめざすこともなく世界に生まれる。人間はみずから選ぶことなく、ただ世界に生まれるがままに生まれる。人間が世界に生まれることは根拠必然性がなく、したがって偶然である。人間が世界に生まれたことは根拠に規定されない偶然であるから、生まれないこともありえた。人間が世界に生まれるのは、生まれないこともありうる偶然にすぎない。人間が世界に生まれるのは偶然であるから、人間はそれにたいして準備することも、抵抗することも、異議を唱えることもできない。人間が世界に生まれるのは偶然でありながら絶対に避けられない。むしろ人間が世界に生まれるのは偶然であるからこそ、それは予測不可能であり、どんな方法や手段をもってしても不可避なのである。
因果必然性の問いと根拠必然性の問いは、それぞれ事象レベルの問いと存在レベルの問いに対応している。事象レベルで世界を問う場合、問いは「世界はどのようにあるか」というかたちで定式化される。そこで問われているのは世界のあり方である。世界のすべての事象は因果法則に規定されており、その因果的なあり方を解明するのが科学である。世界の多様な事象の分類に応じて誕生して細分化された諸科学が、それぞれの分野で世界のあり方を探求する。それはあくまでも事象レベルの探求である。事象レベルの問いが「世界はどのようにあるか」であるのにたいし、存在レベルの問いは「世界はなぜあるか」である。この問いで問われているのは世界のあり方ではなく、世界が存在する根拠である。すなわち「世界が存在するのはいかなる根拠によってか」。しかし、人間が世界に生まれることが根拠のない偶然であるのと同じく、世界が存在するのも根拠のない偶然である。仮に世界が存在する根拠があるとしたら-どのような根拠が思いつかれようとも-根拠そのものがなんらかの根拠によって規定されているはずである。その場合、「世界が存在するのはなぜか」という問いは、「世界が存在する根拠があるのはなぜか」と問い返される。たとえば仮に「世界が存在するのは神が存在するからである」と答えたとして、「神が存在するのはなぜか」と問い返される。このようにして世界が存在する根拠への問いは無限に後退する。それ以上後退しない最終根拠は世界の存在そのものである。すなわち、世界の存在はそれ自体が根拠である。世界の存在自体が根拠であるとは、世界は存在するためにいかなる根拠も必要としないということである。人間が動機や意図や目的がなくただ世界に生まれてくるように、世界はいかなく根拠もなくただ存在する。世界は根拠なく存在するがゆえに、世界の存在は偶然である。これにたいして「世界が存在することには根拠があるが、人間には秘められているだけだ」といってもはじまらない。必然といい偶然といい、それはただ人間にとっての必然であり偶然だからである。もし人間にとっての必然や偶然でないとしたら、いったいだれにとっての必然であり偶然だろうか。
因果法則は事象レベルの問いには答えることができても、存在レベルの問いに答えることはできない。なぜなら事象レベルの法則である因果法則は事象の因果必然性は説明できても、そもそも因果必然性が存在するのはなぜかは説明できないからである。因果必然性とは因果法則に規定された事象同士の関係、すなわち「必ず然るようになる」ことである。因果法則はあらゆる事象を因果必然性によって説明するが、因果法則そのものが存在する根拠は説明できない。世界が存在する根拠がないように、因果法則が存在する根拠もない。仮に「因果法則が存在するのは因果法則に規定された結果である」と答えたとしても、同語反復に陥るだけである。因果法則が存在する根拠はなく、したがって因果法則は偶然に存在する。たとえ世界のあらゆる事象が因果法則に照らして必然的であろうと、因果法則そのものは偶然である。
3.因果性
ある事象が原因となってなんらかの結果を生むことを因果性と呼ぶ。事象が原因となって結果を生み出すのは、個々の事象がそれぞれ因果性を発揮するからである。世界のあらゆる事象が因果性を発揮し、その結果として新たな事象が生じる。事象そのものが因果性が発揮された結果であり、因果性のないところに事象は存在することもなければ生起することもない。因果性は事象を生み出し、それによって世界の構成要素を存在させる。因果性が世界の原動力となって世界の構成要素を生み出している。世界の構成要素は因果性によって生みだされているので、世界における事象はことごとく因果的関係で成り立っている。
しかしここで注意を要するのは、世界における事象が因果的関係で成り立っているということは、具体的な事象のレベルで必ず特定の原因が特定の結果をもたらすことを意味するものではないということである。事象の因果的関係を構成しているのは、原因と結果の連鎖からなる因果連関である。因果性を原動力とする世界は、無数の因果連関からなる。因果連関は他の因果連関とも連鎖し、全体として無際限の因果連関を形成している。そのなかでどんな因果連関も別の因果連関によって干渉される。干渉を受けた因果連関は引き続き因果的に進行するが、それは当初の因果連関とは異なる経過をたどる。たとえば川の水は重力の作用により高きから低きへ直線的に進むのが因果必然性である。しかし途中で倒木により水がせき止められたら、川は倒木を迂回して進む。この事象で水が高きから低きへ流れるのは因果的必然であるが、倒木によって流れが妨げられるのは偶然である。川がまっすぐ流れるのを因果必然性とすれば、倒木のために異なる流れ方をするのは因果必然性からの逸脱である。しかし樹木が倒れて流れが変わったのが偶然であるのは川にとってであり、樹木にとっては根が枯死したことを原因とする必然的な結果である。この場合、倒木にまつわる因果連関が川の流れの因果連関に干渉したのである。因果法則に従ってまっすぐ流れていた川は、倒木の因果連関に干渉された結果、あくまでも因果法則に従いながら倒木を迂回して流れる。その行先は切り立った崖になっていて、水はそこから滝のように流れ落ちるかもしれない。あるいは水は岩や立ち木にさえぎられて幾筋もの細流になって流れるかもしれない。あるいはまた倒木にさえぎられた水はどこにも流れることができずに、柔らかい土壌に浸透して辺り一面を湿地に変えるかもしれない。これらの結果はすべて川がまっすぐ流れることからすれば因果必然性からの逸脱であり、それゆえ偶然の結果である。だが、いずれの結果もそれぞれ因果法則に従っている点で必然的である。川の水がまっすぐ流れるのを妨げる要因は無数にあるが、それらの要因を個別に見ればいずれも因果連関を形成し、その限りで因果必然性を備えている。しかしそれぞれの因果連関がどのように遭遇し、いかなる結果を生み出すかはまったく偶然にゆだねられている。どんな因果連関も絶えず別の因果連関に干渉される可能性がある。あるいはむしろ、どんな因果連関も絶えず別の因果連関に干渉されて因果必然性から逸脱している。因果連関はつねに偶然性に脅かされている。その意味では必然性と偶然性は対等なレベルの対概念ではない。いわば偶然性の大海原に大小無数の因果必然性が浮かんでいるのである。
以上見るように、世界は因果的関係で成り立っているものの、実際には特定の原因が特定の結果をもたらすようにはなっていない。それは世界のあらゆる事象がそれぞれ因果性を発揮するからである。個々の事象がそれぞれ因果性を発揮すると、それらの作用が互いに干渉しあって、因果性が相殺されたり、増幅されたり、変容されたりする。個々の事象がそれそれ発揮する因果性が相互に干渉しあうので、因果性にもとづいて形成された因果連関は、同様に因果性にもとづいて形成された別の因果連関によって絶えず影響を受ける。そのため同じ原因が、時と場所によってそのつど因果性の相互干渉の影響を受けて異なる結果を引き起こす。こうして因果連関は所期の結果とは異なる結果を生み出す。しかも世界の原動力である因果性は、因果性によって生じた結果を一瞬たりとも結果のままにしておかない。因果性によって生じた結果は瞬時にしてそれ自体が原因となって新たな結果を生み出す。新たに生み出された結果も間髪入れずに原因となって因果性を発揮する。こうして一瞬ごとに生み出される因果連関が絶えず相互に干渉しあう。
たとえば「マッチを擦ると火が着く」と定式化された因果連関では、マッチを擦ることが原因であり、火が着くことが結果である。しかしたとえマッチを擦っても別の因果連関が干渉したら着火しない。たとえばマッチ棒の頭薬の燐が湿っていたり、マッチ箱の側薬がすり減っていたら火はつかない。マッチ棒を側薬に擦る力が弱すぎたら摩擦熱が起きず、強すぎたら軸木が折れてやはり火は着かない。ここにはマッチ棒の硬さや強度などの物理的要因だけでなく、マッチを擦る人間の筋力や運動神経、さらにそれらを制御する大脳皮質などの生理的要因が関与している。だが、これらすべての条件が整っても、マッチを擦った瞬間に風が吹いたら火は着かない。風の発生は気圧、気温、地形、気流などさまざまな周囲条件に規定されている。このように一つの因果連関には無数の要因が関与している。マッチを擦ったら火が着くことを因果法則で説明しようとしたら、考えられる方法は二つしかない。一つは、因果連関に関与する要因をすべて原因として数えあげることである。しかし因果連関は別の因果連関へと連なっており、それらに関与する要因の数は無限にあるため、この方法は途中で断念せざるをえない。もう一つは、因果連関に関与する無数の要因を無視して、人為的に設定した枠組みのなかで意図した因果的関係に合致する要素にだけ焦点を当てることである。実際には無数に存在する要因の不断の相互作用から特定の原因と結果をもたらす要因を取り出そうとしたら、思弁的操作によって意図的に限定された局面を切り取るほかはない。これは科学が実験的操作によって一定の条件のもとで仮説を実証するために採用している方法論である。
「すべての事象は原因によって起こり、原因なしには何ごとも起こらない」という因果法則は、因果性を原動力とする世界の構成要素の因果的関係を原因と結果の概念を用いて命題化したものである。それゆえ因果法則はもともと自然の側ではなく人間の側にある。それゆえ人間が因果法則を自然に当てはめて事象を原因と結果で把握しようとしても、自然の側では特定の原因と結果が結びつくようにはなっていない。古今東西の哲学者が因果法則について喧々諤々の議論を戦わせてきたのは、世界が因果的関係で成り立っていることは確からしく思えるにもかかわらず、いざ事象を特定の原因と結果の関係で把握しようとするとにわかに困難を帯びるからである。このことは根本的に「原因」と「結果」が自然の要素ではなく概念であり、したがって人間の頭のなかにのみあることに起因している。それは自然界にいかに多くの動物や植物や鉱物や天体が確固として存在していようとも、「実体」という概念は自然そのもののなかには存在しないのと同じである。因果法則は、人間が自然の多様性を整理するためにつくられたものである。整理の仕方がそれぞれの人間の考え方によって異なれば、原因と結果についての理解も異なるのは当然である。自然の多様性を整理する仕方は、プラトンのイデア論、アリストテレスの原因論、デカルトの機械論、スピノザの決定論、ライプニッツの観念論、ヒュームの経験論、カントの超越論的観念論、ヘーゲルの弁証論などと哲学者の数だけある。たとえばヒュームは「原因」と「結果」が自然のなかにはない点に着目して、因果法則を人間が頭のなかで作った「観念連合」として否定した。1)逆にカントは「原因」と「結果」が人間の頭のなかにある点に着目して因果法則を「純粋悟性概念」によって基礎づけ、この逆転の方法論をみずから「コペルニクス的転回」と呼んだ。2)
4.所与性と事実性
世界に生まれるとは、他の人間や事物や出来事など世界の構成要素のあいだに生まれることである。人間は世界に生まれてさまざまな世界の構成要素に取り囲まれる。人間が世界の構成要素に取り囲まれることは、人間にたいして世界の構成要素が与えられることである。人間に与えられる世界の構成要素を所与という。所与は与えられるものであるから、人間は所与にたいして受け身である。それゆえ人間は世界でその構成要素が与えられることによって受動的である。
人間にとって世界の構成要素は所与であり、人間がみずから生み出すわけではない。たしかに人間が自然に働きかけて、新しい事物を生み出すことは可能である。たとえば土地を耕して種を播き、成長した成果を穀物として刈り入れることはできる。このとき人間は機械なり道具なりを使って土地を耕すことで能動的に振る舞う。種をまく行為も、穀物を刈り取る行為も能動的である。しかし人間は土地が所与としてあらかじめ与えられているからこそ、土地にたいして働きかけることができるのである。同じことは種や穀物についてもいえる。耕した土地に種をまくのは、種が人間に与えられているからである。穀物を刈り入れることができるのも、土地を耕して種をまいた成果が人間に与えられるからである。土地も種も穀物も世界の構成要素として人間に与えられた所与である。活動のレベルで見れば、人間は土地や種や穀物にたいして能動的に働きかけるが、存在のレベルで見れば、それらはすべて人間に与えられた所与である。所与にたいして人間は根本的に受動的である。
人間にとって世界のすべての構成要素は所与として存在する。人間が土地を耕すのは所与として存在する土地に働きかけることである。その土地に穀物を実らせるのは、活動の結果を所与として存在させることである。あらゆる活動の能動性は、活動の結果を新たな所与として存在させることで発揮される。この点では芸術の創造活動も同様である。音楽ならば音を、彫刻ならば像を、絵画ならば色と形を人間に与えられる所与として生み出すのが創造である。
人間にとって世界のすべての構成要素は、根本的に所与として存在する。世界の構成要素が所与として存在することを所与性という。世界に生まれた人間は不可避的に多種多様な所与に取り囲まれる。人間が世界に生まれるとは所与のなかに投げ込まれることであり、それは世界の構成要素が所与として与えられることである。世界の構成要素は人間にとって与えられたものであり、世界に生まれた人間はそれらを所与として受けいれるほかない。世界において人間はいやおうなく数限りない所与と向き合う。人間には所与と向き合う以外の選択肢はない。人間はおよそ生まれるものであるならば世界に生まれる以外の選択肢がないように、生まれたからには所与として与えられる世界の構成要素を受けいれるほかはないのでる。
所与性は、人間と世界の構成要素との最も基本的な関係である。人間は世界に生まれることによって世界の構成要素と所与性の関係にはいる。所与性の関係とは、人間に世界の構成要素が所与として与えられ、人間はそれを所与として受け入れることである。人間が世界に生まれるとは所与のなかに投げ込まれて所与に引き渡されることである。世界に存在する限り人間は絶対に所与性から逃れることができない。人間にとって所与性は存在の条件として避けることができない。たしかに人間はなんらかの与えられた事物を意志的に拒むことはできる。この場合、与えられた事物は物品であったり報酬であったりする。人間はそれらをあえて拒むことによって、「自由意志」を立証することもできよう。しかし与えられた事物を拒むのは、それが与えられたものとして存在することを前提としている。つまり意志のレベルで与えられた事物を拒むことは、かえって存在のレベルで事物の所与性を証明するものである。
人間は世界で所与性において他の人間や事物と出会い、人間と事物が織りなす関係や出来事に直面する。存在のレベルで所与は避けられず必然であるが、事象のレベルで所与が然るようにあるのは偶然である。たとえば目の前の赤いバラは、昨日訪ねてきた友人が駅前の花屋で購入して持参したものであるが、友人が選んだバラの花弁の色は濃い赤ではなく淡紅色か白であってもよかった。それはバラでなくガーベラでもシクラメンでも、店頭で売っている他のどんな花でもよかった。友人が持参するのは花でなくワインかチョコレートでもよかった。そもそも友人はなにも持参しなくてもよかった。このように所与として与えられた事物が然るようにない可能性は無限に広がっている。然るようにない可能性が無限であるなかで、然るようにあるのは偶然というほかはない。しかしたとえ偶然であっても、目の前にバラがあることは否定できない。バラは、偶然性の大海原に否定しがたく浮かんでいる。目を閉じてバラの存在を打ち消そうとしても、それはかえってバラの存在の否定しがたさを裏づけることになる。たとえ所与として与えられた事物が然るようにあることが偶然であろうとも、世界の構成要素が現に所与として人間に与えられていることは否定できない。世界の構成要素がどれほど目まぐるしく入れ替わろうとも、そのつど特定の世界の構成要素が人間に与えられていることは不可避である。このように特定の世界の構成要素が人間に不可避的に所与として与えられていることを事実という。
人間が世界に生まれるのは根拠のない偶然である。しかし人間が世界に生まれ、世界のなかで所与にさらされ、所与と向き合うことは回避不能であり、変更のきかない事実である。目の前に赤いバラがあることも、その花弁が濃い赤をしていることも偶然であり、バラでないことも、その花弁がこの色でないことも可能である。しかし現に深紅の花弁をもつバラが然るようにあるのは事実である。目の前のバラは然るようにないこともありえた無限の可能性のなかで、これしかない事実として現にある。所与の無限の可能性のなかから事実が、あたかも大海から頭を突き出した孤島のように、まさに現にあるように浮かび上がっているのである。
人間が世界に生まれることは偶然であるが、同時に人間が世界に生まれることは絶対に避けられない。それは、さいころを振って出る目はまったくの偶然でありながら、いずれかの目が出ることは絶対に避けられないのと同じである。人間が世界に生まれたことも、そのなかで無数の人間や事物に取り囲まれていることも、そのつどなんらかの事象と遭遇することも、まったくの偶然でありながら変更のきかない事実である。偶然生まれた世界で人間に特定の世界の構成要素が与えられ、人間はいやおうなくそれらと向き合わされる。このとき世界の構成要素は、変更することも回避することもできない事実として人間に対峙する。事実が変更することも回避することもできないことを事実性と呼ぶ。人間は特定の世界の構成要素が与えられ、それらと不可避的に直面する。そのとき所与としての無数の人や物、それらが相互に織りなす複雑きわまりない関係、そしてその関係から生じる数限りない出来事が、事実性の圧力をもって人間に迫る。
世界に生まれた人間は、世界を構成する無数の要素のなかで生きる。人間は世界の構成要素を事実として受け入れ、それらの事実に立ち向かい、ときには事実に脅かされ、ときには事実から逃避する。あるいは逆に事実を求め、事実を享受し、失われた事実を哀惜する。個々の人間は、それぞれの世界で数限りない事実と向き合い不断に関わる。これらの事実には、個々の人間が世界に生まれる以前から存在していたものあれば、誕生後に新しく出現するものもある。世界で人間に与えられる無数の事実は、互いに絡みあい重なり合って繁茂し、事実性の森を形作る。世界とは果てしない偶然性の海に浮かぶ事実性の森である。
5.共同性
あらゆる構成要素の総体として定義された世界は唯一であり、二つと存在しない。あらゆる構成要素の総体が複数存在するというのは論理矛盾である。世界はいつでも、どこでも誰にでも妥当する普遍的世界である。しかしそのような普遍的世界は、実際には体験することもできなければ、記述することもできない。具体的に思い浮かべることすらできない。その理由の一つは、人間の知覚や想像力の射程は限られていて、世界が包摂するすべての構成要素を見渡すことはできないからである。だが、それより重要な理由は、個々の人間が実際に生まれ住んで暮らす世界は、知覚や想像のおよばない普遍的世界ではなく、具体的で個別的なこの世界だということである。人間が生まれてくるのも、人間が他の人間や事物と出会い、それらと関わるのも、つねに現在あるこの世界においてである。人間は誕生して以来この世界に住み、この世界に慣れ親しんでいる。人間はこの世界において他の人間と交わり、もろもろの事物と関わり、それらと限りなく多様な関係を結びながら生きる。この世界における個々の具体的な体験にもとづいて、はじめて全体としての「世界」の概念が形成されるのである。さらにこうして形成された世界の概念を抽象化という観念的操作によってどこまでも拡大することによって総体としての世界が理念として想定される。それゆえ普遍的世界は、実はすべての世界の構成要素を包含するのではなく、むしろそれらを捨象したうえに成り立っているのである。
この世界は、個々の人間にとって現在ある具体的で個別的な世界である。その意味でこの世界は普遍的世界にたいして限局された世界である。ここで、「限局」という言葉に否定的な意味合いはいささかも込められていない。むしろ世界は限局されてはじめて個々の人間にとって現実の世界となりえる。人間はこの現実の世界で好むと好まざるとにかかわらず現実の諸条件に規定されて他の人間および事物とのあいだで関係を結ぶ。特に人間がこの世界で他の人間と結ぶ関係を共同関係という。共同関係には夫婦関係、親子関係、 友人関係 組織における上司と部下の関係など、ありとあらゆる人間関係および社会関係が含まれる。人間がこの世界で互いに共同関係を結ぶのは、人間の本性にもとづいている。本性とは、生来備わっている特性である。この世界で互いに共同関係を結ぶという人間に生来備わっている特性を共同性という。人間同士の共同関係を基礎として共同体が形成される。共同体とは、生活上の共通基盤を核とする複数の人間の共同関係である。
人間に生来備わっている共同性の生物学的基礎は、人類が誕生して以来の進化の過程で確立された生存戦略にある。人類はおよそ700万年前にチンパンジーと枝分かれしたといわれている。以来、人類に属する約25のヒト種が分化したが、ホモ・サピエンスを除いてすべて絶滅した。このことから人類はあらゆる生物のなかでもきわめて弱い生き物であったことが推し量られる。本論で考察の対象とする人間はホモ・サピエンスである。ホモ・サピエンスが厳しい生存競争を生き延びるために講じたのは弱さを逆手にとった戦略であった。その戦略とは、他の人間と共同しなければ生存できないまでに深く他の人間に依存させるものであった。その端的な例として、人間の胎児は他のどんな哺乳動物にも見られないほど無力な状態でこの世に生まれてくることがあげられる。胎児は母親の体内で産道を通れるぎりぎりまで成長するのを待ち、その臨界点でどれほど身体的に未熟であっても母体外へ娩出される。その意図するところは、他の生物との生存競争を勝ち抜くために、母子双方の生命にとってきわめてリスクの高い方法で、胎児に他のあらゆる生物種を凌駕する大きな脳を持たせることである。この戦略は、まったく無力な状態で産み落とされた新生児が、確実に共同体によって養護されることを前提としている。この前提が確保されていなければ、ただでさえ過酷な生存環境のなかでこれほど危険なな出産方法を採用するはずがない。子供の出産と養護を直接引き受ける共同体は家族である。ホモ・サピエンスの進化の過程で確立された生存戦略は、家族共同体を原点とする共同体を構築することによって、巨大な脳を唯一の武器とする生物種の誕生と維持を図るというものである。
過去に地球上に登場しながら絶滅したヒト種のなかには、ホモ・サピエンスより体格がよく脳も発達していたネアンデルタール人も含まれていた。言葉も道具ももっていたネアンデルタール人が絶滅した原因はよくわかっていないが、直接気候変動などの外的要因に帰するのは単純にすぎよう。それほど大規模な環境の変化が起これば、同時期に生存していたホモ・サピエンスもその影響を被らないはずはないからである。ホモ・サピエンスがネアンデルタール人と全面的な戦争をした形跡もない。上述したホモ・サピエンスの生存戦略を考慮するならば、ネアンデルタール人が絶滅してホモ・サピエンスが生き残った理由は、過酷な環境下で子孫を残すことにかけてホモ・サピエンスが優位に立っていたためであろう。ホモ・サピエンスは種を維持するために家族の存続を最優先する共同体戦略を講じたことで、長期にわたる激烈な環境変化を生き延びることができたのではないかと推測されるのである。
共同性は、ホモ・サピエンスの進化の過程で形成されて人間の生来の特性となった。人間において共同性は本能にも比すべき遺伝的特性である。共同性を生来の特性とする人間は、共同関係へと生まれ出る。人間はこの世界に生まれることによって他の人間との共同関係にはいる。共同関係を基礎として生活上の共通基盤を核とする共同体が形成される。共通基盤がなんであるかに応じて多種多様な共同体が存在する。家族は性的結合、親族は婚姻、学校は教育、企業は経済活動をそれぞれ共通基盤とする共同体である。人間の生活様式が複雑になるにつれて、さまざまな共通基盤をもつ共同体が形成される。共同体は家族や企業のように水平的に並存するものもあれば、地方自治体と国のように包含関係にあるものもあれば、小学校・中学校・高等学校のように垂直的な階層をなすものもある。人間はたいてい家族と企業、地域社会と国家など、同時に複数の共同体に属する。これらの共同体からなる全体構造は、おおむね家族を最内円とし国家を最外円とする同心円に見立てることができる。といっても全体構造のなかで共同体を表す円が互いに並列したり交差したりする不規則な同心円であるが。すべての共同体に共通しているのは、人間は共同体のなかでそれぞれの立場や役割や機能をもって他の人間と交わることである。
この世界で共同関係へと生まれ出る人間は、生涯にわたりつねになんらかの共同体に属している。人間は生まれながらにして共同体の成員であり、一生そうあり続ける。人間がこの世界で営む活動は、すべて共同体における他の人間との関わりのなかでなされる。家庭で会話したり、喧嘩したり、和解したりするのも、会社で協議したり、交渉したり、協力したりするのも、それぞれの共同体の成員とのあいだでおこなわれる。学校で教える内容は共同体によって継承された文化であり、工場で生産するのは共同体の成員が必要とする製品であり、商店で購入するのは共同体によって生産された産物である。科学者が研究論文を発表し、小説家が本を書き、画家が絵を展示するのも共同体の成員に向けてである。人間は生まれてから死ぬときまでさまざまな共同体に属し、それぞれの共同体の成員として活動する。共同体は、人間がこの世界に生まれて生涯活動する場であり、人間はこの世界に生きている限りいかなるときもなんらかの共同体に属している。
この世界の範囲は、個々の人間がそれぞれ属する共同体によって規定される。人間がこの世界に生まれて最初に属する共同体は家族である。この世界に生まれるとは、家族共同体に生まれることである。家族は性的結合を基盤とする共同体であり、生殖によって子を作り、出産によって子を生み、育児によって子を育てる。身体的にまったく無力な状態でこの世界に生まれ出た新生児は家族によって手厚く保護され、必要な栄養が与えられ、心身の発達が促進され、言葉や知識を教えられる。家族は少なくとも子供が自分の足で歩けるようになるまでつきっきりで養護する。子供が学童年齢に達すると、学校共同体が長期にわたり子供の脳機能を発達させる訓練を施す。成長した子供は社会共同体に参加して生産に従事し、大人になるとみずから家族を形成して子を生み育てる。幼い子供にとって家族は全世界である。無力な幼児は家族によって全面的に養護されて、「一人前」の子供に育てられる。
子供が学齢に達すると、この世界は家族共同体の範囲をこえて学校共同体に広がる。学校には幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、専門学校などがあり、それぞれ児童、生徒、学生などの身分で教育を受ける。学校では文字の読み書きや集団生活の基本的ルールから、各教科に集約された全般的教養、さらには大学の専門課程における高度な知識まで教授される。教育とは各時代の共同体が所有する文化を次世代の共同体の成員に継承させることである。教育によって人間は共同体の文化を共有するとともに共同体の成員として育成される。
就業年齢に達すると、共同体の円周は企業共同体に広がる。就業年齢に達した人間にとって、この世界はそれぞれ従事する業界である。人間はだれしも生計を営むためになんらかの職業に就き、特定の業界に属する。業界と一口にいっても、その内容は自動車業界、航空業界、化学業界、鉄鋼業界、出版業界、放送業界、保険業界、不動産業界など多種多様である。しかもそれぞれの業界は多数の下位業界を含んでいる。自動車業界であればエンジン、サスペンション、バッテリー、ヘッドランプ、タイヤなどの主要コンポーネントから、ネジ、バネ、ボルト、ナットなどの機械要素まで、自動車部品の種類と同じ数だけ業界が存在する。少なくとも現役で働いている者にとって、自分が身をおいている業界が最も身近な世界である。
この世界は、それぞれの人間が活動する分野でもある。人間は生きている限り、職業か趣味かを問わず、いずれかの分野で活動する。一人の人間が複数の分野にわたって活動することもある。活動分野は、政治、経済、美術、音楽、文学、思想、教育、医療、福祉、娯楽、スポーツなど多岐にわたる。それぞれの分野が世界を形成し、政界、財界、経済界、芸能界、スポーツ界などと呼ばれる。さらにこれらすべての活動分野にはそれぞれ無数の下位分野がある。スポーツならば、野球、相撲、サッカー、スキー、テニスなど数多くあり、それぞれが「野球界」や「相撲界」や「サッカー界」など独自の世界を形成している。
家族、学校、企業などすべての共同体に共通するのは地域である。いかなる種類の共同体も、いずれかの地域に立地している。人間は特定の共同体に属することによって、その共同体が立地する地域を共通基盤とする共同体に同時に属する。そもそも人間は誰しもある時代にある国のある地域に生まれる。それは大都市であるかもしれないし、地方の小都市かもしれないし、農村か漁村かもしれない。人間は必ずいずれかの地域に住みつく。この世界はそれぞれの人間が住んでいる地域の景色によって彩られている。大都市に住んでいる人間にとっては、高層ビルや地下鉄、自動車の渋滞や人々の雑踏が基本的な世界の景色である。農村に住んでいる人間にとっては、四季折々に異なる趣を見せる山を背にして広がる畑や田んぼ、漁村に住んでいるならば漁港や魚市場やそれらの上で舞う海鳥がこの世界の見慣れた景色である。都会の景色も農村の景色も、自然的要素と人工的要素との複合的な産物である。人工的要素とは地域特有の政治的、経済的、社会的、文化的、その他もろもろの要因である。これらの要因は自然との関わりをとおして歴史的に形成されたものである。自然的要素と人工的要素が複合されて地域共同体を形成している。
以上、生活上の共通基盤を核とする共同関係としての共同体の代表的なものをあげたが、肝要なのはこの世界として多種多様な共同体が存在することに対応して、世界は唯一ではないということである。唯一の世界すなわち総体としての世界は、「世界とはなにか」という問いのもとで世界概念を反省したときに、抽象化の観念的操作によってこの世界をどこまでも拡大したすえに行きつく理念である。その意味で唯一の世界もしくは総体としての世界は「反省された世界」と呼ぶことができる。たいしてこの世界は「生きられた世界」である。共同体を実体的な基礎とする生きられた世界は無数に存在する。しかも世界は、一人の人間においてもそのつど属する共同体の数だけ存在する。人間は必ずいずれかの地域に住み、特定の言語を母国語とし、なんらかの分野で活動し、特定の業界に属しながら各々生活を営んでいる。それに応じて世界は地域でもあれば、活動分野でもあれば、業界でもある。居住地域や活動分野や生活環境などとして重なる複層的な構造をしているのが生きられた世界である。
1)デイヴィッド・ヒューム『人性論』
2)イマヌエル・カント『純粋理性批判』