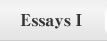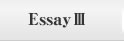第2章 自我論的視点
第1節 自我
1.自分
「人間とはなにか」を考察する過程で、人間はあるときは「自我」と呼ばれ、あるときは「自己」と呼ばれ、またあるときは「主体」と呼ばれる。いうまでもなくそれらは互いに別個の独立したものではなく、いずれも同じ人間の異なる側面にすぎない。考察する視点に応じて人間が自我または自己または主体として捉えられるのである。あえて単純化していえば、人間は意識の作用で見れば自我として、自分自身と向き合う方向で見れば自己として、現実の活動の局面で見れば主体として把握される。このように人間を異なる視点から見るのは、人間という存在をできるだけトータルに把握したいがためである。しかも自我は自我のみで、自己は自己のみで、主体は主体のみで完結するものではない。いかなる視点から見ようとも、本質的に他の人間や事物との関係が前提とされている。端的にいうと自己は他者を、自我は他我を、主体は客体をそれぞれ成立条件としている。他者や他我や客体との関係において、人間はいやおうなく自分以外の人間や事物にたいして開かれて、それらと密接な関わりをもっている。このように複合的でもあり開放的でもある人間を、たとえば意識のみに限局して完結的に論じるのは一面的にすぎよう。少なくともそれは「人間とはなにか」という総合的なテーマで問い求められているものに照らせばとうてい不十分である。
本論では方法論的な手順として「自分」から出発して「自我」、「自己」、「主体」の順に「人間とはなにか」について考察を進めていく。各段の考察は、それぞれ前段の考察の結果を踏まえておこなわれるため、段を追うごとに人間の概念もより総合的なものとなる。最後に到達する主体の概念は、本論の冒頭で提示された「世界の構成要素と関わりながら生きる人間」に相当する。
人間はこの世界に生まれて以来、生涯にわたり無数にある世界の構成要素と関わり続ける。あらゆる構成要素のなかで人間に一番身近なのものは自分である。人間にとって自分は他のどんなものよりも近しい存在である。というより自分は当の人間にほかならないのであるから「近しい」という距離を前提とした形容すら適当ではない。むしろ最初に自分がいて、自分についてのさまざまな了解をもとにして「自我」や「自己」の概念、さらには「人間」そのものの概念が作られるのであり、その逆ではない。つまり最初に人間の一般的な定義があって、そこから自我や自己の概念が導かれ、ようやく最後に自分についてなんらかの理解が得られるというものではない。それゆえ「人間とはなにか」を問うのであれば、人間にとって最も身近な自分から出発して、「自分とはなにか」を追求するのが妥当であり、肝要でもあろう。
生きるとは世界に生きることであり、世界に生きるとは世界の構成要素と関わることである。人間が世界の構成要素と関わる仕方は多様きわまりない。しかし人間と世界の構成要素との関りがどれほど多様であろうと、関わりのあらゆる場面でつねに意識が働いている。意識はそれ自体で意識の働きである。意識の働きではない意識、つまり実体的もしくは静態的な意識は存在せず、意識は意識の働きそのものである。意識の働きは、人間が生きている限り間断なく継続する最も基本的な精神活動である。意識の働きは、具体的には知覚したり、思考したり、意志したりすることとしておこなわれる。間断なく継続する精神活動において知覚や思考や意志などの意識の働きは互いに入り混じって絶えず変化する。思考や意志を伴わない知覚はなく、知覚のないところに思考も意志も生じない。たとえば数学の難問に取り組んでいるとき、本やノートに書かれた文字や図形や数式を見ながら、頭のなかで思考を複雑に巡らせ、その間ずっとこの難問を解こうとする強い意志が働いている。このような複合的で動態的な意識の働きから、思考なり知覚なり意志なりをあたかも化学物質のように単離することは不可能である。せいぜいいえるのは、絶えず変化する精神活動のなかでそのつどどの意識の働きが優勢であるかということである。たとえば数学の難問を解こうとしているときは思考が優勢であり、美しい光景を見ているときは知覚が優勢であり、忍耐が求められる場面では意志が優勢である。しかしまた知覚と思考と意志のいずれが優勢であるかすら判然とせず、ただぼんやりと過ぎていく時間もある。そのような場合も、目の前にあるものを見るとはなしに見たり、とりとめなく思いを巡らせるというように意識はつねに働いている。このように明瞭な意識から漠然とした意識まで含めた意識の働きを意識作用と総称する。
意識作用は、生きている限り間断なく継続する精神活動として絶えず変化する。しかしこの絶えず変化する意識作用にはつねに自分が随伴している。意識作用に自分が随伴しているとは、すべての意識作用において自分が意識されているということである。「自分が意識されている」といっても、自分が実体的な対象物として意識されているということではない。そうではなく、意識作用において自分が意識していることがつねに了解されているということである。具体的な意識作用、つまりそのつど優勢な意識作用で見れば、人間がなにかを知覚したり、思考したり、意志したりするときに、そのつど自分が知覚し、自分が思考し、自分が意志していることが了解されているということである。人間にとって自分が一番身近な存在であるといえるのも、そのつどの意識作用においてつねに自分が意識していることが了解されているからである。
すべての意識作用は、自分が意識することの了解のうえに成り立っている。逆にいえば、自分が意識しているという了解のないところに意識作用は成立しない。具体的には、自分が知覚していること、自分が思考していること、自分が意志していることを了解していない知覚や思考や意志はありえない。たとえばなにかを考えているとき、考えている内容が了解されているだけでなく、同時に自分が考えていること、あるいは考えているのは自分であることが了解されている。自分が考えているとは、自分が意識作用の動作主であることを意味する。意識作用の動作主を欠いた意識は存在しない。自分が知覚せず、自分が思考せず、自分が意志しない知覚や思考や意志は存在しない。意識作用の動作主がなく意識することは、意識が霊魂のように浮遊している状態でも想像しない限りありえない。意識作用は意識作用の動作主があってはじめて成り立つ。自分は意識作用の動作主としてすべての意識作用に随伴することによって、意識そのものを成り立たせているのである。
意識作用の基底でつねに了解されているのは、自分が意識していることである。この了解内容を言語化するならば、「自分が意識する」という主語と述語からなる構文で表現される。主語は「主たる語」としてそのつどの関心の対象を示し、述語は「述べる語」として関心の対象となるものの動作や状態を記述する。この構文で関心の対象となっているものは「自分」であり、自分がおこなう動作は「意識する」ことである。意識作用は根本的に自分が意識することとして成り立つ。自分が意識することは意識作用の成立条件であり、それゆえ意識作用の基底ではつねに自分が意識していることが了解されている。その了解内容を言語化すると「自分が意識する」と言表される。以下、この意識作用を言語化した構文を意識構文と呼ぶことにする。
意識作用の基底でつねに了解されているのは、自分が意識していることである。あらゆる意識作用につねに自分が意識作用の動作主として随伴していることが了解されており、その了解内容を言語化するならば「自分が意識する」という意識構文で表現される。このことは意識作用そのものが主語(動作主)と述語(動作)からなる統語的構造をなしていることを意味する。「自分が意識する」という意識構文で、「自分」が主語であることは、現実に自分が意識作用の動作主であることを反映している。「自分」が意識作用の動作主であることが言語表現に反映されて、「自分」が意識構文の主語の位置を占めるのである。意識構文は「自分」という主語がなければ文法的に成り立たないが、それは現実に意識作用そのものが意識作用の動作主である自分が存在してはじめて成立するからである。
人間にとって自分が最も身近な存在であると自覚されるのは、意識作用につねに自分が随伴しているからであるが、それは具体的な意識作用において自分が意識作用の動作主として了解されていることである。自分が意識作用の動作主として了解されることは、自分が意識に現れていることを前提とする。自分が意識に現れるとは、自分が自分に意識されて自分として了解されることである。意識作用においてつねに自分は意識に現れて自分として了解されている。自分が意識に現れて自分として了解されるというとき、一方で了解される以前に自分というものがあり、他方で意識があって、意識と自分が遭遇して自分の了解が生じるということではない。意識作用において意識と自分と了解は、それぞれ別のものではない。自分とは自分の了解であり、自分を了解するとは自分を意識することである。自分は自分を意識し、自分が自分を意識することによって自分が自分として了解されるのである。自分が意識に現れなければ自分は隠れたままであり、その場合は自分が意識されることも、自分が了解されることもない。自分が意識されることも了解されることもなければ、自分が意識作用の動作主として働くこともなく、その場合は意識作用そのものが成立しない。自分は意識に現れる限りで意識作用の動作主として働く。自分が意識作用の動作主として働くことを言語化すると、「自分が意識する」という意識構文で表現されて、自分が言表された意識構文の主語となるのである。
意識作用は、つねに自分が意識作用の動作主として随伴していることによって成り立つ。自分が意識作用の動作主として意識作用に随伴するとは、自分が意識作用の動作主として意識作用そのものを成立させることである。意識作用の動作主として自分が意識作用の動作主となるためには、意識作用において自分が自分に現れて自分として了解されていなければならない。しかしまた自分が自分として了解されるためには、自分を意識していなければならない。自分を意識していなければ自分を自分として了解することはできない。意識作用が成立するためには、自分が意識作用の動作主として了解されなければならず、そのためには自分を意識して自分として了解しなければならない。自分を意識するとは、自分を意識作用の対象として意識することである。したがって「自分が意識する」という了解は、意識作用の動作主である「自分が意識する」だけでなく、意識作用の動作主となる「自分を意識する」ことを内包している。この構造を言語化すれば、「自分が自分を意識する」ということになる。「自分が自分を意識する」という言表は、意識作用の動作主である自分が同時に自分を意識作用の対象として意識していることを含意している。
自分が意識作用の対象として意識されてはじめて、自分は意識作用の動作主となり、意識作用は自分が意識構文の主語となる意識として成立する。意識構文において自分が主語となる意識を自分の意識と呼ぶ。自分の意識とは、自分が意識作用の動作主として了解され、その了解内容を言語化した意識構文で自分が主語となる意識である。自分が意識構文で主語となることは、意識作用の動作主としての自分を意識して了解していることを前提とする。したがって自分の意識は、自分が意識作用の動作主として意識することと、自分を意識作用の対象として意識することを内包している。自分の意識において自分は意識するものであると同時に意識されるものである。自分が意識することと自分を意識することは一体であり、どちらか一方が欠けたら意識そのものが成り立たない。
自分の意識は、自分を意識作用の対象として意識することにおいて、自分が意識作用の動作主としてとして了解される意識である。意識作用は、自分が意識作用の動作主として了解されることによって成り立つ。といっても、それは必ずしも自分が意識作用の動作主として明確に自覚されているということではない。たしかに具体的な意識作用において思考したり、知覚したり、意志したりするのは自分であることが了解されている。これらの意識作用を言語化した意識構文でも自分は主語の位置を占めている。が、主語は人称的に明示されておらず、その限りで「意識しているのは誰か」という問いに答えることはできない。意識構文において人称的に明示された主語とは、「自分」が人称化されて表示された「私」である。「私」は二人称でも三人称でもない一人称として表示されており、その限りで「意識しているのは誰か」の問いに答えることができる。意識構文の主語が「私」として人称的に明示されることにより、「自分が意識する」という言表は「私が意識する」という言表に転化する。「自分が意識する」と「私が意識する」という言表を区別するために、前者を無人称の意識構文と呼び、後者を一人称の意識構文と呼ぶことにする。
意識作用は反省されると「自分が意識する」という無人称の意識構文で言表され、次に人称化されると「私が意識する」という一人称の意識構文に転化する。反省とは、意識作用そのものを対象化して観察することである。反省によって意識構文の主語を一人称の主語として明示できるのは、反省以前の意識作用のうちに自分が意識作用の動作主として意識され了解されているからである。反省以前の了解の段階では、自分はいうなれば意識作用に浸透するかたちで意識全体に現れている。意識全体に現れて了解されている自分に反省のレンズをとおして観察の焦点を当てると、意識全体に浸透していた自分が凝縮されて意識の前面に登場する。反省されて意識の前面に出た自分は、最初に「自分が意識する」という無人称の意識構文で言語化され、次に意識構文の主語である自分が「私」という人称詞で呼称されて一人称の意識構文の明示的な主語となる。一人称の意識構文は「私が意識する」という形式で言表され、思考や知覚や意志などの具体的な意識作用はそれぞれ「私が思考する」、「私が知覚する」、「私が意志する」という一人称の意識構文で言表される。
無人称の意識構文で自分が主語となる意識が「自分の意識」であるのにたいして、人称化された意識構文で私が主語となる意識は「私の意識」として了解される。ここにおいて、これまで考察してきた意識作用がつねに一人称の意識作用であったことが確認される。一人称の意識作用は意識に関する考察において特権的な位置を占めている。なぜなら意識もしくは意識作用はもともと「私が意識する」こととしてしか体験されないからである。世界には自分以外の人間も存在するのだから、二人称および三人称の意識作用も存在するにはちがいない。しかし意識について考察するのに二人称および三人称の意識作用を出発点とすることはできない。なぜなら自分が体験できるのは一人称の意識作用のみだからである。意識はそれ自体意識の働きであり、意識の働きは意識することであり、意識するとは「自分が意識する」ことである。それゆえ、二人称もしくは三人称の意識作用は自分には体験できない。自分が体験できない二人称もしくは三人称の意識作用について、少なくとも直接本人として語れることはなにもない。自分が体験できない意識作用について語ろうとすれば、自分の意識を考察することから得られた知見を二人称もしくは三人称の立場に投影する以外の道はない。それは科学者であると一般人でああるとを問わず、二人称、三人称の意識作用について論じるときの常套手段でもある。
2.自己性
意識全体に現れている自分の了解を反省によって対象化するとき、自分は「自分」という言葉で指示される。しかしながら反省以前に意識全体に現れている自分にとって「自分」という日本語は偶然的でしかない。反省以前の自分の了解をあえて表現しようとしたら、「みずから性」とか「おのれ性」といった抽象的な言葉で表すほかはない。「みずから(自)」も「おのれ(己)」も「自己」という言葉を構成する語である。そこで反省以前の自分を指し示す「みずから性」もしくは「おのれ性」を総称して自己性と呼ぶことにする。意識を反省することによって対象化された自己性が言語化されて「自分」という言葉で表される。反省によって言語化された「自分」と区別するために、反省以前の自分を<じぶん>と表記する。<じぶん>は非言語的な自己性の記号的表現である。反省以前の<じぶん>が反省のまなざしによって対象化されて「自分」という言葉があてがわれる。しかし、<じぶん>と表記される自己性にとって「自分」という言葉はまったく偶然的であり、共同体の約束事にもとづいてあてがわれた名称にすぎない。
自己性の了解が反省されて「自分」として言語化されるが、この言語化は自分ではないものの了解を前提としている。なぜなら反省以前の<じぶん>を対象化して「自分」として言語化するためには、<じぶん>を自分ではないものとの区別において認識することが必要だからである。自分を認識するさいに参照される自分ではないものとは、身のまわりにある物体や動物や植物や人間など、およそ自分以外のすべてのものである。自分の言語化は、自分を自分以外のすべてのものとの区別において認識することから始まる。自分を自分以外のものと区別するために、自分は自分ではないすべてのものと対比される。この対比によって自分は自分ではないすべてのものとは異なるものとして、それゆえ一種特別のものとして了解される。とりわけ自分以外の人間との対比において、自分以外の人間は自分とよく似ていながら自分とは異なる他の人間として了解される。これと相即して自分は他の人間との区別において他の人間ではないものとして了解される。自分と他の人間との対比によって人称的な区別が芽生える。自分は、他の人間との人称的な区別において一人称として了解される。一人称として了解された自分は一人称詞で呼ばれる。一人称を表わす言葉は「私」に限らず、「ぼく」でも「おれ」でもいい。幼児ならばそれぞれ親から呼ばれている自分の名前である「よしお」とか、その愛称「よっちゃん」などで自分のことを示そうとするだろう。重要なのは自分をなんらかの呼称で呼ぶことである。固有名詞も含めれば自分を表す呼称は無数にある。幼年期は「よっちゃん」、少年期は「ぼく」、青年期は「おれ」、成人したら「わたし」というように、一人の人間の一生をとおして変化することもある。あるいは同じ人間が公の席では「わたくし」、仲間同士のあいだでは「おれ」というように時と場合によって使いわけることもある。しかしいかなる呼称で呼ばれようとも、それによって共通して指し示されているのは反省以前の<じぶん>である。一人称の意識作用は意識作用の動作主である自分の了解のうえに成り立っているが、その基底には自己性の了解がある。「私」や「ぼく」や「おれ」といった本来偶然的な人称詞を理解できるのは、その基底にある反省以前の<じぶん>を了解しているからである。<じぶん>は、それ以上さかのぼることができない一人称詞の了解源である。「自分」よりも抽象度が高い「自我」や「自己」などの概念を理解できるのも、これらの概念の起源である<じぶん>が熟知されており、そこから意味内容が汲み取られるからにほかならない。
それではこうした自己性の了解を人間はいつ手に入れるのだろうか。発達論的にいうならば、自己性の了解はすでに胎児が母親の体内にいるときに芽生える。父親と母親の遺伝子が受精卵のなかで結合して胚が生まれ、そこから胎児へと成長して出産にいたる生命活動には一瞬の切れ目もない。この連続した生命活動の過程で<じぶん>の了解が生まれる。<じぶん>の了解は意識であり、意識の誕生は胎芽期における脳の発生時点までさかのぼる。しかし脳が発達するにつれて意識が<じぶん>の了解として出現するのであれば、意識がそのようなものとして生じるための要因がそれ以前からあったはずである。これを仮に「自己性の因子」と呼ぶならば、それは脳が発生する前から、したがってまた意識が誕生する前から存在していたにちがいない。受精卵から分裂するすべての体細胞と同様、脳も遺伝子によって形づくられる。自己性の因子は胎芽が形成される以前から受精卵に遺伝子として宿っていたのあろう。遺伝子とは遺伝情報にほかならず、自己性も父親と母親の生殖細胞を介して受け継がれる遺伝情報の一つである。自己性の因子を宿した受精卵は、胚盤胞となって母親の子宮に入って子宮壁に付着する。そこで胚盤胞は母親の血液から栄養を吸収して胎芽に成長する。それと並行して神経管が生じ、神経管が束になって脳が形成される。脳の活動が活発になるにつれて自己性の因子が徐々に顕在化し、やがて<じぶん>の了解として意識が芽生える。意識の発達は人間の脳の成長と密接に関連しており、受精後8週目までの胎芽期に脳の原型が形成され、徐々に意識が発達する。
意識が生じたころ胎芽から手足が分化して胎児となる。胎児は羊膜に包まれて羊水のなかに浮かんでいる。羊水は胎児を包み込みながら胎児の体のなかにも充満して胎児の体内を循環する。脳の神経中枢から手足の先まで神経回路が通じると、胎児は手で自分の顔や体を触ったり、口で指をなめたりする。胎児が自分の体を触ったりなめたりする動作で触るものと触られるものが出会う。ここでは触るものと触られるものは同じものである。本来触ることと触られることは別個の動作であり、触るものと触られるものも別のものである。その意味で触るものと触られるものが同じものであるというのは、稀有な事態であり、これを生じさせているのは<じぶん>である。胎児が自分の体に触る動作において、触るものも<じぶん>であり、触られるものも<じぶん>である。触るものと触られるものが出会うことができるのは、触るものと触られるものが同じ自分だからである。触るものと触られるものとの出会いにおいて、出会うのは自分であり、出会われるのも自分である。自分が自分に出会い、自分が自分に出会われることによって自己性が感得される。このとき非言語的な<じぶん>の了解が芽生える。まだ目が見えず耳も聞こえない胎児が頻繁に自分の体を触る行為を繰り返すのは、触るものと触られるものとの出会いにおいて感得される<じぶん>を確認するためであろう。この確認行為の結果生まれる自己性の了解が原初の意識である。意識は自己性の了解として発生する。自己性の了解としての意識は、みずからを指し示すという意味で自己参照的である。
母親の体外に娩出されてある程度成長した幼児に、母親をはじめとする大人は繰り返し同じ名前で呼びかける。それを何度も繰り返しているうちに、幼児はその名称が、どうやら自分を指しているものらしいことを理解する。幼児がそのように理解できるのは、母親の胎内にいるときから<じぶん>を熟知しているからである。名前を呼ばれてはじめて自分に気づくのではない。「太郎」や「花子」といった固有名詞は偶然的なものにすぎず、自分についての了解を喚起する力はない。固有名詞を何回連呼しようとも、それが指し示す当のものが存在しなければ言葉として機能しない。繰り返し同じ名前で呼びかけられることをとおして、幼児自身がそれをすでに熟知している<じぶん>と対応させるのである。このときはじめて幼児は自分を対象化する。自分を対象化するとは、自分自身を反省して言語的に把握することである。これと並行して幼児は自分自身を言語的に把握する意識操作を母親に投影し、「お母さん」または「ママ」などと呼ぶようになる。この意識操作の投影は、母親以外の人間にもおこなわれて、幼児は他の人間を名前で呼ぶことを覚える。
幼児が非言語的な<じぶん>を「自分」という言葉で表すようになるのは、いうまでもなく共同体からあてがわれた「自分」という言葉を覚えてからのことである。しかし「自分」という言葉が反省以前の<じぶん>を表すことができるためには、言葉とそれによって指し示される対象とのあいだに対応関係がなければならない。この対応関係は、意識作用を反省して<じぶん>を対象化し、これに「自分」という言葉を適用することによって成立する。しかしそもそも<じぶん>を対象化できるためには、自分ではないものを認識していなければならない。<じぶん>を自分ではないものと区別して認識することによって、はじめて<じぶん>は「自分」として対象化される。もし<じぶん>を自分ではないものとの対比において認識していなかったら、自分という言葉を他の人間や事物に適用することになり「自分」の概念は成立しないだろう。「自分」という言葉は自分以外のものとの対比において固有の<じぶん>に適用されることによって「自分」の概念が成立する。
「自分」の概念は自分でないものとの対比において形成される。そのため<じぶん>が「自分」として言語化されて「自分」の概念が成立するのと並行して、自分ではない人間は「他人」として把握される、さらに他人との相互参照において「自分」と「他人」が人称的に区別される。「自分」は一人称で表され、「他人」は二人称もしくは三人称で表される。自分を表す一人称は「私」に代表される人称詞で指示される。自分との相互参照において対象化された「他人」は、二人称の他人と三人称の他人とに区別される。二人称の他人は「君(たち)」や「あなた(たち)」などの人称詞、三人称の他人は「彼(ら)」や「彼女(ら)」などの人称詞で指示される。このように「自分」を含むすべての人称詞は、他人を含む自分以外のすべてのものとの相互参照によって形成されるが、その根底には相互参照の基準としてつねに非言語的な<じぶん>の了解がある。
発生論的には、生物は生きるために周囲の自然と同化しなければならず、そのために生物が周囲を探知する働きとして意識が生じた。意識作用は生物にとって必須の生命維持活動であり、この生命維持活動を効率的におこなう器官として神経が生まれ、神経の束として脳が形成された。この観点から見るならば意識の発生は脳に先行する。それゆえ、意識の発達は人間の脳の成長と密接に関連しているからといって、脳があるから意識があると無造作に断定することはできない。それは胃があるから食物を摂取するのではなく、摂取した食物を消化するために胃が形成されたのと同じ理屈である。脳はもともと意識によって周囲環境を探索する器官として発生した。哺乳類はもとより下等動物を含むほとんどすべての動物が脳をもっている。脳は意識の生体器官として生じたのであるから、当然ながらそれらの動物も意識をもっている。意識はそれ自体で環境の意識であるが、意識が環境の意識として成立するためには、意識が自己参照的に統一されていなければならない。意識が自己参照的に統一されているとは、意識が自己性の了解として、すなわち自己を指し示すように成立しているということである。意識が自己参照的に統一されていないと仮定したら、たとえ意識が環境を探知してもその結果はみずからにフィードバックされない。たとえば痛覚によって危険を探知しても、それはみずからの痛みとしてして自覚されず、したがって相応の回避行動にはつながらない。意識は生物が周囲を探知してみずからの生存を維持するのに適した行動を取るために発生したのであるから、この仮定はおよそ意識というものが存在する事実とあいいれない。意識が自己参照的であるのは、周囲を探知する環境の意識の本質である。この点では人間の意識も人間以外の生物、とりわけ動物の意識も変わらない。このことは動物も自己性の了解をもっていることを意味する。しかしながらわれわれにとって動物の自己性が具体的にどのようなものであるかはまったく不明であり、推測すらできない。なぜなら人間である限り「コウモリであることがどのようなことであるか」1)知りようがないからである。
3.私
意識作用はそのつどの思考、知覚、感覚、感情、意志、欲求などの複合体である。これらの意識作用を反省して対象化すると、意識構文の主語としてなんらかの一人称詞が浮上する。一人称詞は「他人」との区別において対象化された自分を表す概念である。自分の意味内容は、反省以前に了解されている<じぶん>に遡源する。意識構文の主語としての一人称を「私」で代表させるならば、「私」は、あらゆる意識作用に主語として随伴している。ことさらに意識作用を反省していないときでも、「私」が意識作用を言語化した意識構文の主語であることに変わりはない。意識作用を反省していないときとは、意識作用の動作主が明示的に意識されていない状態である。しかしその場合でも、意識のまなざしを意識作用そのものに振り向けると、にわかに意識作用の動作主である「私」が意識される。そのつどの具体的な意識作用は、それぞれ「私が思考する」、「私が知覚する」、「私が意志する」というように言表される。「私」を主語として「思考する」や「知覚する」や「意志する」を述語として言表できるのは、これらの意識作用においてつねに「私」が主語の位置を占めているからである。どんな文も主語があって(もしくは主語が含意されて)はじめて成り立つように、「私」は主語としてつねに意識作用に伴っている。もし意識作用に「私」が主語として伴わないことがあるとしたら、私の思考や知覚や感情に私のものではない思考や知覚や感情が入り混じることになる。それはいうなれば私の意識のなかに誰か別人の意識がはいり込むことである。しかしそのようなことは実際には想像すらできない。なぜなら私のものでない思考や知覚や感情を想像しようとしても、この想像自体が意識作用であり、そこにはつねに主語として「私」が伴っているからである。たとえば私がいまテレビを見ていて、このテレビを見ているのは実は私自身ではなく他人であると想像しようとしても、そのように想像するのは相変わらずこの私である。およそ意識作用は、同じ主語が連続していることによってはじめて成り立つ。思考も同じ主語が連続的に随伴していることによって成立する。あるときは私が考え、次の瞬間は他人が考えるとしたら、他人が考えているあいだは私の思考は停止し、思考そのものが欠如する。私が考える限り、考えているのはつねに「私」でなければならない。意識作用はそのつど「私が思考する」、「私が知覚する」、「私が意志する」こととして成り立ち、私が私でなくなれば私を主語とする意識も消滅する。
このように意識における主語の連続性を保証しているのは、「私は私である」という自己同一性である。自己同一性とは、自分が連続的に同じものであることである。自己同一性は、意識に目覚めた胎児が自分の体に触り、触るものと触られるものは同じものであると感得した瞬間まで遡源する。このとき胎児ははじめて自己性としての<じぶん>を了解する。以来、胎児は新生児、幼児、児童とへ成長していく過程で、この自己性の了解のうえに意識作用を活発化させていく。そのさい意識作用の基底にはつねに同一の自己性がある。自己同一性は、意識作用の基底で自己性が連続していることを表す概念である。「私は私である」という言表は、自己同一性を人称構文で表現したものである。意識はつねに私を主語とする意識として連続している。非人称的な自分を主語とする意識が「自分の意識」であるのにたいし、人称詞である「私」を主語とする意識は「私の意識」である。私の意識は、私が主語として了解されている意識であるが、私が主語になることは私を了解していることを前提とする。したがって私の意識は、私が意識作用の動作主として意識することと、私を意識作用の対象として意識することを内包している。私の意識において私は意識するものであると同時に意識されるものである。意識する私と意識される私は同一である。自己同一性は、この意識する私と意識される私が同一であることである。意識する私と意識される私が同一であるから、私が意識することと私を意識することが一体となって意識作用そのものを連続的に成立させるのである。
私の身体は、幼年期、青年期、壮年期、老年期と著しく変化するが、身体がどれだけ変化しても「私は私である」ことの自己同一性は維持される。たとえば老年期に「私は昔の私ではなくなった」と実感する場合、それは体力が落ちて若いときのように動けないとか、気力が衰えて昔のような情熱がなくなったということを意味する比喩的表現であり、「私は私である」ことにはいささかも変わりがない。むしろ「私は私である」という自己同一性のうえに立って、はじめて「私は昔の私ではなくなった」という言表が可能なのである。というのも現在の私と昔の私を比較して同じであるとか異なるとか判定することは、比較対象となる私をそれぞれ客観視する一方で、比較する私自身が変わらずに連続していることを前提しているからである。「私は昔の私ではなくなった」の言表における「私」は客観視された昔の私の状態と今の私の状態であって、意識作用の動作主としての私ではない。意識作用の動作主である私は、いかに状況が変化しようと同一のままである。もし私が同一でなく、私が私以外のものになったとしたら、その瞬間に私を主語とする言表は成り立たなくなり、「私は昔の私ではなくなった」と表明すること自体が不可能になるだろう。多重人格者がいて「私は私ではない」と主張したとしても、それはかえって私の自己同一性を証明することになる。なぜなら「私は私ではない」と主張するのはほかならぬ私だからである。「私は私ではない」という場合の主語は私であり、私が私として連続しているからこそ多重人格的状況を「私は私ではない」と言表できるのである。多重人格者が「私は私ではない」と口走った瞬間に本当に別人格になったとしたら、今度はその別人格が「私は私である」と断言するだろう。
「私は昔の私ではなくなった」という実感においても、「私は私ではない」という確信においても、つねに私が自己同一性を保つことができるのは、主語としての私がそこで言表されている事態を超え出ているからである。「私は昔の私ではなくなった」という言表で、主語としての私は「私は昔の私ではなくなった」という事態に埋没していない。たとえ身体としての私は老いたとしても、主語としての私が老いることはない。なぜなら私はつねに私であり、その限りで変化を超越しているからである。「私は私ではない」という主張の場合も、主語としての私は離人症的な状況に巻き込まれていない。「私は昔の私ではなくなった」と「私は私ではない」のいずれの事態にも共通しているのは、私を主語とする言表において私は主語として事態を超越している点である。私は自分の身体的・精神的状況を超越し、その視点から自分自身を客観視しているのである。自分の身体的・精神的状況がいかに変化しようとも、それを観察している私自身は変化しない。主語である私は観察する私として、観察される自分自身のあらゆる状況において変化を超越しているのである。
「私は私である」と言表される自己同一性は、「AはAである」の形式で表現される自同律とはまったく別ものである。自同律は論理の規則として要請されたもので、現実にはAはAでないかもしれないし、AはBになるかもしれない。たとえば氷は室温下で放置すれば溶けて水になり、やがて水蒸気となって霧散する。その場合、氷はもはや氷であるとはいえなくなる。それどころか氷は時々刻々と溶けているから、「氷は氷である」といった瞬間にもそれは一瞬前の氷ではなくなっている。自同律は、そうした事情はさておいて、水が氷点下で凝結して固体となった透明な物体を「氷」という言葉で命名する限りで「氷は氷である」とするという決めごとである。このような決めごとをするのは、「氷」という言葉が指すものが氷でないとしたら、およそ言葉を使う思考も会話も成り立たないからである。これにたいして「私は私である」という言表で表現される同一性は論理的な規則によって保証されているのではない。私は実体的な存在ではなく、私に現れる限りにおいて存在する。私が私に現れるとは、私が私に意識されることである。私は私に意識されてはじめて私として了解される。それゆえ私が私である根拠は、私が私に意識されて私として了解されることにある。そして私の了解は反省以前の<じぶん>の了解に由来し、それはまた意識に目覚めた胎児が自分の体に触り、触るものと触られるものは同じものであると感得した瞬間にまで遡源する。
自分を人称的に表現した「私」の概念は、自分を他人と区別することによって成立する。「私」の概念は自分の了解を基礎としており、自分の了解は自分ではないものとしての他人の了解を前提としている。自分ではないものとしての他人の了解が成立するためには、自分と区別された他人が存在していなければならない。自分とは異なる他人が現実に存在していることが、他人の了解が成立するための存在論的な前提である。この場合、自分と他人は共に存在するという意味で共存の関係にある。自分と他人を含む複数の人間が共存する関係は、現実には共同体として実現されている。共同体において他人と区別して把握された自分を人称的に呼称するために「私」の概念が生じる。一人称である「私」との相互区別において、他人は二人称(「君」など)または三人称(「彼」など)で呼ばれる。共同体で共存するのは複数の人間であるから、一人称、二人称、三人称のいずれも複数を表す呼称(「私たち」、「君たち」、「彼ら」など)がある。「私」をはじめとする人称詞は、自分と他人が共存する共同体のなかで生じる社会的概念である。
意識作用を言語化した意識構文には主語があり、主語がなければ意識構文も、そのもとになる意識作用は成立しない。一人称の意識作用を統御するのは一人称の主語である。たとえば思考の意識作用は、その構文「私が思考する」で「私」が一人称の主語となることによって成り立つ。この場合、思考の意識作用のうちに「私」が現れて了解されている。「私」の了解は、自分の概念を経由して反省以前の<じぶん>から汲み取られている。つまり、一人称の「私」は非人称的な自分を経由して、非言語的な<じぶん>から了解されているのである。「私」という言葉で指示されているのは「君」でも「彼」でもない「自分」であり、さらに「自分」という言葉で指示されているのは非言語的な自己性である。このように「私」という一人称詞は非言語的な自己性から了解されているのにたいし、一人称以外の人称詞、たとえば「君」や「彼」を理解するのに自分を経て自己性の了解にさかのぼることはない。なぜなら「君」も「彼」も<じぶん>の了解に遡源する概念ではなく、「私」という一人称が形成される過程でそれとの相互参照において派生した概念だからである。二人称および三人称の思考の意識作用は、それぞれ「君が思考する」や「彼が思考する」という主語と述語からなる構文で表現される。この構文で二人称および三人称の人称詞が主語の位置を占めるのは、一人称の場合と同じである。それは主語がなければ「君が思考する」や「彼が思考する」という構文が成り立たないから、というのは文法上の理由であって真の理由ではない。思考の意識作用の構文で二人称および三人称の人称詞が主語の位置を占めるのは、「私が思考する」という一人称の了解が二人称もしくは三人称に投影された結果である。思考の意識作用を主語と述語からなる意識構文で言語化することは、一人称の意識作用においてしか可能ではない。その理由は、一人称の場合にのみ主語である「私」を反省以前の非言語的な了解にさかのぼることができるからである。「君が思考する」もしくは「彼が思考する」という言表がおよそ理解可能な意味内容をもちえるのは、「私が思考する」という一人称構文に反映された意識作用の統語的構造が二人称および三人称の立場に投影されるためである。
4.自我
冒頭に掲げた「自分とはなにか」という問いに答えるために、反省以前の非言語的な<じぶん>から出発して、<じぶん>を言語化した「自分」の了解を経て、自分を指示する一人称詞としての「私」にゆきついた。「私」の理解は自分を経由して反省以前の<じぶん>の了解から汲み取られている。<じぶん>の了解は原初の意識であり、その起源は意識そのものの芽生えまでさかのぼる。<じぶん>と自分と私は、それぞれ別個の固定した概念ではなく、<じぶん>-自分-私という了解の過程である。しかもそれは一方向ではなく、<じぶん>の直接的な了解から出発し「自分」を経て「私」の概念へ進むとともに、「私」の概念の理解を「自分」を経て自己性の了解から汲み取る双方向の過程である。本論では、この<じぶん>-自分-私という双方向の自己了解の過程を包括的に自我と呼ぶ。以下に、このように理解された自我の特性を列挙する。
第一に、自我は反省以前の非言語的な<じぶん>である。
第二に、自我は他人との相互参照において言語化された「自分」である。
第三に、自我は他人との人称的区別において呼称された「私」である。
第四に、自我は意識作用を根本的に成り立たせている自己同一性である。
第五に、自我は意識作用を「自分が意識する」という構文で成立させる主格である。
第六に、自我は意識の背後に想定された実体ではなく、意識に現れる限りで存在する。
以上挙げた自我の特性のうち、第一の特性から第四の特性についてはすでに述べたので、ここでは第五の特性と第六の特性について論じる。
「私が意識する」という一人称の意識構文において、意識作用は「私」という名詞と、「意識する」という動詞が主格の格助詞「が」によって結合されている。主格とは、文の主語となる資格を意味する文法用語である。だが、文法は天からの授かりものではない。文法に主格があるのは、現実に文の主語となる資格を有するものが存在するからである。反省された意識作用を言語化した一人称の意識構文で「私」が主語である文法上の理由は、「私」という語に主格の格助詞が付加されているからである。しかし、この構文で「私」に主格の格助詞が付加されている現実的な理由は、「私」という人称詞で表現された自我が意識作用を統御しているからである。意識作用において自我が主体として取る能動的な構えが主格である。意識作用の動作主である自我は能動的な構えで意識作用を統御している。そのため意識作用を言語化すると、意識作用の動作主である自我が主語となって「自分が意識する」という意識構文で表現されるのである。自我は意識作用の動作主であるから、意識作用を言語化した意識構文では必ず自我が主語となり、自我が主語とならない意識構文はない。
現実の精神活動において自我は主格の構えで意識作用を統御する。自我は主格の構えで意識作用そのものを主格主語と述語動詞からなる統語的構造において成立させる。一人称の意識作用は言語化されて「自分が意識する」という意識構文で表現される。この意識構文で自我は「自分」として言表され、主格の格助詞「が」が付加されて主語の位置を占める。この格助詞は、「意識する」という言葉で表現される意識作用の動作主が「自分」であることを文法的に示している。が、それは現実に意識作用の動作主が自分という言葉で表現された自我であることを反映したものである。意識作用は、言語化すれば「意識する」という言葉で表される精神活動であり、意識作用の動作主は「自分」という言葉で表される自我である。さらに自分が反省されて「私」として人称化されると、意識作用は「私が意識する」という一人称の意識構文で言表される。
自我が主格の構えで意識作用を統御するとは、「自分」が主語となって意識作用を「自分が思考する」、「自分が知覚する」、「自分が意志する」などの統語的構造で成立させることである。主語は、文法の規則に従い文を成立させる「主たる語」である。一人称構文で主語はなんらかの行為を言表する文を成立させる。ここで行為は意図的なおこないと定義する。思考は意図的におこなう心の働きである。行為を言表する文、たとえば「私が思考する」という一人称構文は、文法上「私」という主語がなければ成立しない。しかし主語がないと文が成立しないのは文法の規則に反するからではなく、現実に行為する主体が存在しなければ行為は成立しないからである。思考する主体がいなければ思考は成り立たない。誰も思考しない思考というものは存在しない。思考する主体は、言表文においては主語のかたちで表される。たしかに、日本語の言表では主語が省略されることがしばしばある。だが、それは主語となる主体が存在しないからではなく、逆に言表文で省略できるほど明瞭に存在しているからである。
意識作用は意識する主体としての自我に統御されてはじめて成り立つ。自我に統御される意識作用を反省して言語化すると「自分が意識する」という構文で言表される。自分が反省されて自我が人称化されると「私」となって、意識作用は「私が意識する」と言表される。この場合、「私」は代表的に選択された自我の一人称代名詞にすぎない。実際の意識作用では反省の強度によっては、非人称的な「自分」が了解されているだけのこともあれば、人称的な「私」が明示的に意識されることもある。いずれの場合も意識作用の基底にはつねに非言語的な自我としての<じぶん>があり、主格の構えで意識作用を統御している。自我が主格の構えで意識作用を統御できるのは、自我が世界の構成要素との関りにおいて基本的に能動的な構えを取っているからである。
以上見たように、文法上の主格の現実的な基礎は、一人称の意識作用における自我の基本的な構えにある。しかし、自我が能動的な構えを取るのはけっして意識作用にのみ限定されるものではない。自我は意識作用そのものを統語的構造において成立させることにより、意識作用のうえになされるすべての活動を統御する。思考や知覚や意志などの精神活動が意識作用を基礎としており、したがって自我によって統御されていることは見やすいところである。しかしまた走る、泳ぐ、食べるなどの身体活動も意識作用と一体化しており、したがって自我によって統御されている。この場合、身体活動の自我による統御は、それぞれ「私が走る」、「私が泳ぐ」、「私が食べる」などの構文で言語化される統語的構造でおこなわれる。身体的動作とその基礎にある意識作用が自我を主語とする統語的構造で統御されているのでなければ身体活動は成立しない。自我による精神活動と身体活動の統御を言語化した構文で自我が主語となっているのは、現実に自我が人間のあらゆる活動を統御しているからである。
個別言語はそれぞれ固有の文法をもっているが、世界の構成要素との関りにおける自我の基本的な構えは、すべての人間に共通している。それゆえ、たとえ一人称主格の表現形態は言語によって異なるとしても、主格表現それ自体は自我の基本的な構えを反映したものとしてすべての言語に共通して存在する。たとえば主格を構成する格助詞の「が」は、同じ膠着語である韓国語にもガ(가)音として存在する。日本語と韓国語では意識作用における自我の能動的な構えが、主格を形成する格助詞に反映されている。言語学的に屈折語に分類される欧米語には、このように主格を形成する助詞はない。だが、それはいうまでもなく主語となる資格としての主格が存在しないことを意味するものではない。主格はラテン語などのように語形や、ドイツ語などのように冠詞や、英語や孤立語に属する中国語などのように語順で表現される。つまり主格はすべての言語でそれぞれの言語の特質に応じた形態で表示されているのである。このことは一人称主格が言語の種類にかかわらず普遍的なものであることを示している。それはとりもなおさず自我の能動的な構えとしての主格が、言語活動を含む人間の活動全体の基本構造として普遍的であることに根差している。
第六の特性によると、自我は実体的なものではなく意識に現れる限りで存在する。自我はそれ自体意識であるから、自我が意識に現れるとはみずからに現れることである。自我がみずからに現れるのは、つねになんらかの具体的な意識作用においてである。これを、「自我は意識作用においてみずからに顕現する」という。ここで「顕現」という言葉は、「現象」という言葉が事象が現れることを意味するのにたいして、自我がみずからに現れるという意味合いで用いられている。自我は意識作用においてみずからに顕現し、その限りで存在する。自我が顕現するとは、自我が自我に意識されることである。自我が自我に意識されるのは、自我がみずからを意識することである。自我がみずからを意識することを自己意識という。といっても意識と自己意識は本来別のものではない。意識はもともと「自分の意識」であり、潜在的に自己意識である。潜在的な自己意識において意識されている自分が、人称化されて「私」と呼称されることにより顕在的な自己意識となる。自分の意識が自分が意識することと自分を意識することを包含することに対応して、顕在的な自己意識は「私が意識する」と「私を意識する」の両面を包含している。この自己意識の両面は表裏一体をなしており、「私を意識する」ことがなければ「私が意識する」こともない。自己意識は「私」の意識であり、「私」の意識でない自己意識はありえない。自己意識とは「私が意識する」と同時に「私を意識する」ことである。
意識作用には、つねに自我が<じぶん>-自分-私という双方向の了解の過程として随伴している。これは、実際に意識が働く場面で自我はつねに「私」として明示的に意識されているわけではないことを含意している。意識は必ずなんらかの具体的な内容を含んでいるが、この具体的な意識を反省して主語は誰かと問うときにはじめて「私」が明示的に意識されるのである。たとえば私が絵を見ているとき、私の意識はさしあたり絵に向かっている。このとき直接意識されているのは私ではなく絵である。しかしその場合でも絵の意識の背景で、私が絵を見ていることは了解されている。その証拠に、この私の了解に注意を向けて絵を見ている意識の主語を尋ねると、いつでも私が意識の水面上に急浮上する。絵を見ている意識を反省すると、その意識作用には私が主格の構えで随伴していることが確認される。この了解の過程を図式化するならば、絵に集中しているとき意識はもっぱら「絵の意識」であり、「私」は背景に退いている。だが、この意識作用を反省すると絵の意識は「絵を見ている(私の)意識」となり、さらに反省の強度が増すと「(絵を見ている)私の意識」へと移行する。反省の前とあとで絵そのものの表象内容にまったく変化はないが、反省によってそれまで意識の前景にあった絵の意識が背景に退き、逆にそれまで背景にあった意識の主語が前景に出てくるのである。
自我はすべての意識作用を主格の構えで統御する。これは「私」が主語となって意識作用を反省した場合に「私は意識する」という一人称の意識構文で成立させることを意味する。「私」とは他人との相互参照によって人称化された自我である。「私」として人称化されない自我は非人称的な「自分」であり、「自分」の了解は非言語的な<じぶん>から汲み取られている。この<じぶん>-自分-私という了解の過程を離れて自我を考えようとすると、自我はたちどころに実体化されて「自我」という名称をもった対象物に転化する。対象物をどれだけ子細に分析してみても自我の核心にいたることはできない。なぜなら分析する人間の自我はつねに分析のこちら側にいるからである。こちら側とは分析する人間の意識の側であり、それにたいして対象物は意識の「向こう側」にある。対象物を分析するメスの切っ先は、けっして分析者自身には向けられない。
1)トマス・ネーゲル 『コウモリであるとはどのようなことか』(永井均訳)