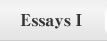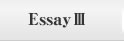序文
本論で追求するテーマは「人間とはなにか」である。といっても人間一般の概念を規定することではなく、あくまでも現実に生きる具体的な人間を対象とする。それはこの世界に生まれ、生き、老いて死んでいく生身の人間である。
いうまでもなく人間はそれ自体において生物である。人間はだれしもこの世界に生物として生まれ、生物として死んでいく。生物は太古の海に誕生して以来、何十億年という歳月を経て進化してきた。この長い年月にわたり生物を生かし続けてきたのは生の主体性である。生の主体性はなによりも本能に具現化されている。本能は生物が生きて活動するための原動力である。本能は大別すると、ひたすら生きようとする生存本能と、どこまでも生き続けようとする生殖本能からなる。生存本能と生殖本能は個々の生物においてそれぞれ体細胞と生殖細胞として体現している。これらの細胞が自己増殖することによって生物は太古から現在まで存続してきた。生物個体として人間も基本的に体細胞と生殖細胞から構成され、生存本能と生殖本能によって生かされている。
人間は生物として他のすべての生物と同じ進化の軌跡をたどった。それと同時に人間は他のいかなる生物にも見られない進化の道を歩んだ。その契機となったのは言葉である。人間は自分を取りまく周囲の生存環境を認識する方法として言葉を獲得した。それはたとえばコウモリが周囲の環境を認識する手段として超音波を手に入れたのと同じく進化史上の出来事だった。言葉を獲得すると、言葉は人間のなかに精神を生み出した。精神は細胞の自己増殖ならぬ観念の自己増殖によってまったく独自の進化を遂げた。
それぞれまったく異なる進化の軌跡をたどる生物としての人間と精神としての人間が、一つの身体のなかで共存しているのが人間である。両者は矛盾と対立を孕みながら一人の人間において統合されている。このような矛盾と対立を孕んだ人間をどこまで統一された全体として捉えることができるか、本論はその試みである。
本論では人間を生物と精神が統一された全体として捉えるために、人間を複数の視点から考察する。具体的にいうと、世界論的視点、自我論的視点、主体論的視点、言語論的視点、時間論的視点、空間論的視点、存在論的視点、個体論的視点、そして生命論的視点である。タイトルは「哲学的人間論」とした。その意味するところは文字どおり「人間とはなにか」を哲学的に論じることであるが、生身の人間を考察するのに哲学的概念はあまり役に立たない。というのも哲学的概念はもともと伝統的な哲学の枠組のなかで用いられているので、本質的に多視点的な人間に適用するには必ずしもふさわしくないというのが理由の第一である。
もう一つの理由は、哲学的概念は多くの哲学者の手垢がついており、どれがだれの手の跡だかわからない状態にあるからである。そのような概念を振りかざして、自分でなにかわかった気になったり、他人にわからせた気になったりするのは絶対に避けたく、哲学的概念の使用は極力控えることにする。どうしても使わざるをえない場合は、そのつど概念の範囲を厳密に定義する。哲学的概念を使わないぶん、いきおい造語的な表現が多用されることになろうが、それは生身の人間の実像にできるだけ肉薄するためにはやむをえない。それらの造語が生身の人間の生臭さをいささかでも映し出すことを願う。