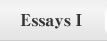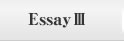第4章 言語論的視点
第2節 概念
1.事物の概念化
言語は人間と自然との関係における生存環境の認識方法である。生存環境を認識するために、人間は周囲の事物を同定する。事物を同定するとは、事物を知覚にもとづいて特定のものとして把握することである。事物を特定のものとして把握する過程で事物の言語化がおこなわれる。先に言語化は「了解の内容を言葉で表現すること」(第2章第1節)と定義されたが、ここで「事物に関する了解の内容を統語的構造において表現すること」と具体化することができる。事物に関する了解の内容とは、感覚によって与えられた事物に関する情報すなわち感覚情報である。感覚情報が知性によって統語的に処理されることにより事物は特定のものとして把握される。その結果、目の前の事物は「これは〜である」という主語と述語からなる構文で言語化される。事物がこのような形式で言語化されるのは、事物の認識がこの構文で表現される統語的構造をなしていることにもとづいている。
具体的にいうと、この構文の主語をなす「これ」という指示詞は、認識主体に所与として与えられた事物を指示している。ここで用いられている指示詞が「それ」でも「あれ」でもなく「これ」であるのは、目の前にある事物が認識主体との近接的な空間的関係において把握されていることによる。指示詞「これ」によって指し示された事物は、助詞「は」によって主語として認識主体に提示される。主語として提示された事物は、断定の助動詞「である」によって特定のものとして同定される。たとえば目の前にある事物が木であれば、最初に所与として与えられた事物が指示詞「これ」により認識主体によって指示され、次に助詞「は」により認識主体に主語として提示され、最後に助動詞「である」により「木」として同定されて、「これは木である」と言表される。この言表形式は、認識主体が指し示す事物を特定のものとして同定する認識の構造を言語化したものである。
事物を同定するためには、事物に関する感覚情報を知性が処理して知覚を形成することが必要である。知覚とは、感覚情報にもとづいて事物を特定のものとして把握することである。事物を特定のものとして把握することは、事物を「これは〜である」の構文で判断することによっておこなわれる。この判断は、それにもとづいて知覚が成立することから知覚判断1)と呼ぶことにする。知覚判断は、事物の感覚情報から知性による処理を経て形成される知覚情報を統語的構造で表現したものである。
事物の感覚情報から知性の処理によって知覚判断が形成されるプロセスにおいて、知性は最初に感覚が集めた感覚情報を分節化する。分節化とは、さまざまな感覚情報を一定のまとまりのあるものに区分し、それらを相互に関連づけることである。分節化された感覚情報を相互に関連づけるのは、感覚情報をまとめて特定のものとして把握するためである。感覚情報を分節化し相互に関連づけて特定のものとして把握することを綜合という。たとえば目の前の事物を見て、茶色や緑色や赤色を識別し、それぞれの色の境界を見定め、それらの形を判別し、こうして分節化された感覚情報を相互に関連づけて綜合する。綜合の結果、目の前の事物について、「これは赤い」、「これは緑色である」、「これは丸い」など事物の性質もしくは状態に関する知覚判断や、「これは葉である」、「これは実である」など事物そのものに関する知覚判断が形成される。これらの個別的な知覚判断を組み合わせて、「これは赤い実である」や「これは緑色の葉である」という複合的な知覚判断が得られる。さらに複合的な知覚判断をまとめて「緑色の葉が生い茂った木に赤い実がなっている」という全体的な状況認識が生じる。
知覚判断は事物の感覚情報を分節化して綜合することによって形成されるが、そのためには所与として与えられた個々の事物が統語的構造で認識されなければならない。その結果、事物は「これは〜である」という構文で同定される。事物がなんであるか同定されるところのもの、いいかえれば事物を事物として成り立たせているものが事物の本質である。事物はさまざまな特徴を有するが、それらの特徴は本質的特徴と偶有的特徴に分けられる。本質的特徴は事物の本質を構成する特徴であり、事物が事物であるために必須の特徴である。これにたいして偶有的特徴は事物の本質を構成することなく、それらが欠けても事物は事物として成り立つ。本質的特徴の基準は共通性である。共通性とは複数の事物に共通して存在していることである。たとえば根や幹や枝や葉があることは複数の木に共通しているので、木が木であるための本質的特徴とみなされる。これにたいして枯れ枝や幹にあいている穴などは必ずしも共通していないので偶有的特徴とみなされる。共通性を基準として事物の類が形成される。類とは、共通性の基準で弁別された本質的特徴を有する事物の集合である。根や幹や枝や葉があることを共通の特徴とする事物は「樹木」という類を形成する。しかし、事物に共通の特徴は固定したものではなく視点によって変わる。それに応じて事物の類も変わる。同じ樹木のなかでも葉が広くて平たいという特徴が共通している樹木があれば、それらは広葉樹という類を形成する。さらに広葉樹のなかで冬になると葉が枯れて落ちるという特徴が共通している樹木は落葉広葉樹に分類される。
感覚が目の前の事物の特徴を感受して知性に伝えると、知性はそれらの特徴を共通性の基準に照らして本質的特徴と偶有的特徴に弁別する。さらに知性は抽出された本質的特徴を綜合して事物の本質を形成する。それによって事物はその本質において把握される。事物をその本質において把握することを事物の本質把握2)という。これまで述べたことから明らかなように、本質把握は本質が事物に備わっていてそれを直接観取するというものではない。事物の感覚情報から知性が本質的特徴と偶有的特徴を弁別し、抽出された本質的特徴を事物の本質として事物に帰属させるのである。樹木の例でいえば、地中に根を張っていること、幹があること、枝が伸びていること、枝に葉や実がついていることなどが本質的特徴として抽出される。これらの本質的特徴を集約して、事物は「地中に根を張り、幹から複数の枝が分かれ、それぞれの枝が多数の葉や実をつけるもの」などと定義される。このように事物の本質的特徴を集約して定義された内容が事物の本質である。
事物の本質を命名することによって概念が形成される。概念とは命名された事物の本質である。事物の本質に与えられる名前を名称という。事物の本質に与えられる名称は、個物を表す固有名ではなく、事物の類を表す一般名である。たとえば「地中に根を張り、幹から複数の枝が分かれ、それぞれの枝が多数の葉や実をつけるもの」という事物の本質に「樹木」という名称を与える。これによって事物は概念として把握される。事物を概念として把握することを事物の概念化という。事物の概念化は、<事物-本質-概念-名称>という一連のプロセスである。
以上、事物を概念として把握プロセスを説明の便宜から経時的な順序で記述したが、いうまでもなく事物を認識するたびに概念が一から新たに形成されるわけではない。概念はすでに認識する人間の頭のなかに存在する。数多くの概念が認識する人間の記憶にそれぞれの特定の名称で保存されているのである。目の前の事物を認識する局面で、感覚情報から本質的特徴を抽出して綜合することによって知覚情報が形成されると、記憶のなかでそれに対応する概念が検索される。知覚情報が記憶に保存されている概念と照合されて一致すれば、この概念が事物に適用され、事物は対応する概念の名称で呼ばれるのである。
個々の事物は概念の名称で呼ばれることによって類に分類される。たとえば目の前の赤い実は「林檎」という名称で呼ばれることによってリンゴという類に分類される。リンゴを「林檎」という名称で呼ぶのは、リンゴをミカンやナシと区別するためである。リンゴを「林檎」と呼ぶことによって、リンゴはミカンやナシから区別されるだけでなく、カキ、モモ、ブドウなどすべての果物から区別される。リンゴはリンゴ以外のすべての果物から区別されると同時に、野菜とその下位分類であるすべての果菜類、葉菜類、根菜類や、穀物とその下位分類であるすべての主穀、雑穀、菽穀、擬穀からも区別される。上位分類でもリンゴはリンゴ以外のすべての被子植物や裸子植物から区別される。さらにリンゴはリンゴ以外のすべての植物から区別されることにより、ありとあらゆる動物や鉱物から区別され、最終的にリンゴ以外のいっさいの存在物から区別される。このようにある一つの事物を概念化することは、森羅万象を分類することにつながっている。もちろんそのために発話者は博物学者である必要はない。目の前にある事物を共同体が定めた概念の名称で呼びさえすればいいのである。
類を形成する基礎となる概念は、他の概念から区別されるように互いに境界されている。この境界にもとづいて、概念の内包と外延が生じる。概念の内包は事物から本質的特徴が抽出されて集約された本質と一致する。概念の外延はその概念が適用される事物の範囲である。ある概念の外延に含まれる事物は、それらの事物に共通の特徴を本質的特徴として備えている。概念の内包を構成する特徴情報の量に応じて概念の外延が変化する。概念の内包の情報量が多ければ多いほど概念の外延は縮小し、情報量が少なければ少ないほど外延は拡大する。概念はその外延に含まれるすべての事物が共通の本質的特徴を備えているという点で普遍的である。他方、個々の事物は共通の特徴のほかに、それぞれ異なる特徴を備えていることにより個別的である。
ここで留意すべきは、事物の概念化といっても、概念化されるのは事物そのものではなく、事物の意識だということである。事物の意識は、一次的には感覚によって収集された事物に関する感覚情報であり、二次的には、事物の感覚情報が分節化と綜合を経て形成された知覚情報である。しかし感覚によって収集された感覚情報が知性に処理されて直ちに全体知覚が形成されるのではない。樹木の知覚が成立するためには、目の前の事物は最初に個々の要素、たとえば幹や枝や葉や根などに分節化され、それぞれの感覚情報が綜合されて知覚情報が形成される。次に、幹や枝や葉や根などの個々の要素について綜合された知覚情報が記憶のなかで検索されて、記憶されている幹や枝や葉や根などの概念と照合される。照合の結果、知覚情報と記憶されている概念が一致すれば、個々の要素は「幹」や「枝」や「葉」や「根」という名称で概念化される。そのさいに個々の要素はそれぞれ「これは幹である」、「これは枝である」、「これは葉である」という知覚判断によって同定される。木の構成要素に関するそれぞれの部分知覚が互いに関連づけられて全体知覚が形成される。この全体知覚が記憶されている樹木の概念と照合されて一致すれば、目の前の事物は木として同定されて「木」の名称が適用されるのである。
事物の概念化において概念化されるのは事物そのものではなく、事物の意識であるということから導かれるのは、言葉は事物そのものの表現ではなく事物の意識の表現であるということである。事物の概念化は事物そのものを意識することから出発するが、事物の意識が言語化されることによって事物と概念の二重化が起こる。樹木の例でいえば、自然の側には木と呼ばれる事物があり、心の側には木の概念がある。自然の側にあるのは具体的な個物としての木であり、心の側にあるのは木の本質的特徴を集約した概念である。概念は、その概念の外延に含まれるすべての事物に共通の本質的特徴を集約したものであるから普遍的である。事物を概念化することにより、事物は必然的に個物と普遍へと二重化される。この二重化は事物の概念化の不可避的な結果である。事物の概念化によって自然の事物と概念への二重化が起こり、それによって人間は自然との直接的関係から離脱して概念を仲介する関係にはいる。事物と概念の二重化は自然との関係において人間を他のすべての生物と異ならしめている決定的な要因である。
2.概念の構造
概念は事物と本質と音声の三項構造からなる。事物とは、第一義的に自然の事物である。自然の事物は人間の意識から独立して存在する。人間は自然の一部として自然とつながっているが、同時に身体と意識によって自然から切り離されている。そのため人間は呼吸や鼓動といった身体の自律的な生命活動に加えて、意識活動をとおして自然と交流しなければならない。意識がつねにあるものの意識であるのは、意識が身体を介して絶えず自然と交流していることに根差している。意識は根本的に身体を介する心と自然との関係であり、その関係は能動的であると同時に受動的であ。受動的側面では自然の事物が意識に所与として与えられ、能動的側面では意識が所与を知覚する。自然との関係で受動的側面を受けもつのが感覚であり、能動的側面を受けもつのが知性である。感覚は自然の事物について感覚情報を収集し、知性が感覚情報を概念化して知覚情報を形成する。知覚情報は周囲の状況に関する高度な認識を可能にし、人間が生存するために必要かつ適切な判断と行動の基礎を提供する。
概念化の三項構造における本質とは、事物を事物として成り立たせているものである。本質は、事物を成り立たせているものとしてつねにその事物に帰属される本質的特徴からなる。これにたいして偶有的特徴は、つねに事物に帰属していないため事物の定義において考慮されない。感覚が目の前の事物について感覚情報を知性に伝え、知性はそれらを本質的特徴と偶有的特徴に弁別する。知性は弁別された本質的特徴を綜合して事物を本質において把握する。本質把握は事物の概念化の前提となる手続きである。概念化は事物の本質を言葉で表して概念とすることであるが、その前提として事物の本質が把握されていなければならない。本質的特徴を綜合して形成された知覚情報にもとづいて事物の本質が把握される。この本質が記憶に保存されている概念と一致する場合に、この概念に対応する名称が事物に割り当てられる。
概念化の三項構造において音声とは、事物の知覚を言葉で表現するために適用される言語音である。言語音として確立された音声を音韻という。目の前の事物の感覚情報を収集するのは感覚であり、収集された感覚情報から木の概念を形成するのは知性の役割である。ここで知性が実行するのは、感覚によって提供された目の前の事物の感覚情報から本質的特徴を弁別し、それらを集約して事物の本質を把握し、この本質に対応する音声を適用することである。事物の概念化は、知覚情報にもとづいて把握された事物の本質に対応する音声を適用することによって完成する。このとき事物の本質は概念となり、音声は音韻となる。個々の事物はそれぞれ異なる特徴を備えているので個別的であるのにたいして、個々の事物に共通の特徴を抽出して形成された概念は普遍的である。これに対応して直接個々の事物を発音する音声は、それぞれだみ声、甲高い声、訛りなどそれぞれ特徴を備えて個性的であるのにたいして、概念に適用される音韻は普遍的である。といっても実際に普遍的な音韻が発音されるわけてはない。概念を書きあらわす文字が字体を問わず、達筆であろうと悪筆であろうと、普遍的な記号でありえるように、概念を表す音韻も実際には話者の個性的な音声で発音されるしかないのである。
概念に適用される音は、知性が直接事物から聞き取ったものでもなければ、感覚から提供された事物の情報のなかに見いだしたものでもない。知性はそれを事物でもなく感覚でもない別のところから取り出してきたのである。「別のところ」とは人間の共同体である。言葉は共同体の、この場合は特定の言語共同体の約束事である。事物の概念を特定の音で呼ぶことは、共同体を構成する共同主体のあいだで任意に決めたことである。たとえば木は「キ」、「シュ」、「ナム」、「バウム」、「アルブル」、その他どんな音で呼ばれても構わない。とにもかくにも日本語を共通語とする言語共同体では、木は「キ」の音で呼ばれて概念化される。事物としての木は自然が生み出したものであるが、「キ」の音で呼ばれる概念は人間が作り出したものである。たしかに「木」の漢字は象形文字で枝が伸びた立木を表しており、その限りで自然の形象と関係があるといえるが、それを「キ」の音で呼ぶのは純粋に共同体の決め事である。2)
3.言葉と意識
意識は本質的に自然との関係であり、第一義的に自然の事物の意識である。意識は自然の事物の意識として事物に即している。意識は事物に即している限りで「即物的」な状態にある。しかし同時に意識は「観念的」な側面も備えている。というのも意識は事物と関係すると同時に、意識が関係している当の事物がなんであるかを問うからである。この本質把握の志向性は意識の本性である。意識は事物と関係しながら、事物の本質を問う。意識は事物がなんであるかを問い、みずからその問いに答えるべく事物を概念化する。事物の本質は、その事物がなんであるか判断することを可能にする本質的特徴からなる。本質把握において、この判断に寄与しない偶有的特徴は捨象される。意識は事物の本質的特徴からその事物の本質を規定し、規定された本質に特定の音を適用して事物を概念化する。意識が事物をその本質において把握することにより、意識は事物の意識であると同時に事物の本質の意識でもある。つまり、意識は目の前の事物を意識することにおいて、その事物の本質を意識しているのである。事物の本質を意識するとは事物を概念化することであるから、事物を意識することにおいて事物は個物と概念に二重化しているのである。
意識はその一次的形態である視覚や聴覚や触覚などの感覚をとおして自然の事物と関係する。意識が感覚をとおして関係する事物をその本質において把握することにより、事物は概念化される。事物を概念化するには、事物についての感覚情報を言葉を介して分節化する必要がある。言葉によって分節化されない意識を想像するならば、直接自然の事物に即した状態、つまり言葉が介在せず感覚が事物そのものと密着した状態である。言葉が介在しなかったら、意識はこのような即物的状態に沈んだままであろう。そこでは知性が働いて感覚が集めたデータを処理して知覚を形成し、それにもとづいて取るべき行動を決定することもない。ただ感覚が環境から受ける刺激にたいして生体が直接反応するだけである。言葉が介在することによって意識は事物の意識でありながら事物から離脱する。意識が事物から離脱するとは、事物が概念化されることによって事物と概念の二重化が起こるということである。意識が事物の意識であることに依然として変わりはないが、意識は事物そのものに密着するのではなく、いわば言葉のフィルターを介して事物と接するのである。
動物にも意識はあるが、動物の意識と人間の意識の決定的な違いは、事物と概念の二重化に起因する意識の幅にある。事物と概念の二重化により、人間の意識は事物に張りついた即物的状態を離れる。人間が動物とは比較にならない高度な思考能力をもつことができたのは、事物と概念の二重化において意識が事物に張りついた状態を離脱して即物性から解放されているからである。人間は事物の概念化により意識の即物性から解放されることによって、目の前の具体的な個物に拘束されずに自由に思考できるようになったのである。
ここで忘れてならないのは、概念化によって形成される概念そのものは普遍的であるが、概念化は意識の本質把握にもとづいており、本質把握は目の前の具体的な個物から出発していることである。事物の概念化は意識に自然の事物が与えられていることを前提とする。概念化は、具体的な個物から本質的特徴を抽出して本質を把握するプロセスとしておこなわれる。「これは木である」という知覚判断で事物を同定する場合、「木」と同様に「これ」という指示詞も概念であり、したがって普遍的である。「これ」という指示詞は、すべての事物を指すのに適用できる。しかし、実際に「これ」という指示詞が適用されると、この言葉で指示される当のものは、目の前の具体的な個物に限定される。意識は具体的な個物から出発して本質を把握し、把握された本質を固定するために特定の名称が適用される。名称とそれが適用される個物とのあいだに必然的な関係はない。自然において意識に与えられるのは、「木」という言葉でもなければ、木一般の概念でもなければ、「キ」の音でもなく、あくまでも個物としての木である。それはこの世界に二つとない色や形や匂いや肌触りをもった具体的な個物である。
空腹の人間が木になる実をとって食べようとするとき、その実を「リンゴ」と呼ぶにせよ、他の種類の実もひっくるめた「果物」という言葉で捉えるにせよ、あるいはなにもかも一緒くたにして「食べ物」の概念に包摂するにせよ、それらの概念が指しているのは共通して目の前にある具体的な個物である。リンゴ-果物-食べ物と概念の抽象度を高めようとも、木の枝からもぎとった甘酸っぱい実が食欲を満たすことにいささかも変わりはない。目の前にある事物を「リンゴ」と呼ぼうと「果物」と呼ぼうと「食べ物」と呼ぼうと、概念化のプロセスにおいて意識はつねに具体的な個物から出発するが、そのさいも意識は具体的な個物にとどまり続ける。事物の本質把握と概念化によって形成された概念が事物の概念であるためには、概念化のプロセスを逆にたどって個物を指示するのでなければならない。
概念化のプロセスにおける個物の指示には、知覚の場合と想像の場合がある。知覚の場合に概念が個物を指示するとは、事物を目の前に捉えて概念を適用することである。たとえば目の前にある事物を見ながら、「これはリンゴである」という知覚判断によってその事物に「リンゴ」という概念を適用する。この場合、目の前の事物は最初に指示詞「これ」で指示され、助詞「は」によって主語として認識に提示される。次に「リンゴ」という言葉で認識に提示された事物にリンゴの概念が適用され、最後に「である」によって事物と概念が結びつけられる。想像の場合に概念が個物を指示するとは、知覚の場合とは逆に概念の名称を聞いて頭のなかに事物の像を思い浮かべることである。たとえば「木」という言葉を聞いて、記憶に保存されている木の概念に対応するイメージを想起する。この場合、針葉樹林に囲まれて育った寒冷地帯の人間と、広葉樹を見慣れている温帯の人間では、記憶されている木のイメージがかなり異なる。このことは、本来普遍的であるはずの概念がもつイメージは、実際にはそれぞれの個人の経験に規定された差異があることを意味している。概念の名称は共同体の決め事であり、したがって共同体内では普遍的に通用する。しかし概念のイメージは個人の経験に即して形成されるので個人差がある。個人差を伴うという点で概念のイメージは本質的に曖昧であらざるをえない。その一方で、概念のイメージにつきまとう個人差が概念の曖昧さの源泉となっているという事実は、概念がそれぞれ経験から形成された個人的なイメージを介して具体的な個物に向かっていることを如実に物語っている。
事物の概念化は、事物の抽象という意識の一方向の働きではなく、事物と概念のあいだの抽象と指示という意識の双方向の働きである。事物の概念化そのものは意識の本質把握にもとづいておこなわれる。本質把握で把握されるのは事物の本質的特徴である。意識は目の前の事物について本質的特徴を抽出し、それらの本質的特徴にもとづいて事物の本質を規定する。周囲の事物に関する意識は感覚を起点として、感覚が収集した周囲の情報を知性が処理する。感覚情報は言葉を介して概念に分節化され、分節化された概念は統語的に関連づけられて理解を形成する。さらに個々の事物の概念的な理解が相互に関連づけられて状況認識が生まれる。感覚による事物の直接的な意識が知性によって概念化され、概念化された意識に特定の音が適用されて語が作られる。 たとえば赤い色を表す「赤」という語が形容詞としてリンゴと結合されて「赤いリンゴ」という句を形成する。この句に「なる」という動詞が結合して「赤いリンゴがなっている」という節が作られる。さらにこの節が、関連する知覚を表現する他の節と組み合わされて「緑色の葉が生い茂った木に赤いリンゴがなっている」という文が作られる。語から句、句から節、節から文、文から文章へと発展するにつれて状況認識は複雑さを増す。
概念が相互に関連づけられて状況認識が形成されることにより人間を取り巻く周囲の生存環境にたいする意識が構造化される。その結果、人間は自分を取り巻く状況を俯瞰できるようになり、複雑で高度な状況認識をもつことが可能となる。感覚が収集した周囲の情報を知性が処理して概念化し、そうして形成された概念を相互に関連づけて全体的な連関を構成する。自然の概念化が進むにつれて言葉が発達し、言葉の発達に伴い概念化される自然の範囲が広がる。こうしてますます広範な自然が、互いに関連づけられた概念によって再構成される。自然を概念化するとは、自然を言語で再構成することにほかならない。「自然を再構成する」といっても自然そのものを作り変えるというようなことではなく、自然の事物を概念で把握することによって自然全体を体系的に認識することが可能になるという意味である。3)
4.言葉と自己意識
事物の概念化によって事物と概念の二重化が生じ、その結果として意識は事物の意識と概念からなる幅をもつ。意識は事物の意識であることにおいて自分を意識しており、意識はそれ自体で自己意識である。それゆえ事物との関係だけでなく、自己との関係においても概念化による二重化と、それにもとづく意識の幅を認めることができる。事物の概念化の基礎をなすのは事物と本質と音声の三項構造であったように、自己の概念化の基礎をなすのも三項構造である。異なるのは、自己の概念化の三項構造で事物に相当するのは自己である点だけである。事物の概念化では事物が具体的な個物であることに対応して、自己の概念化では自己は個としての自己である。個としての自己とは、これまで<じぶん>と表記してきた言葉以前の自己である。それは「みずから性」または「おのれ性」というべきもの、総じて「自己性」である。
自己との関係における三項構造で本質は、自己はなんであるかという問いにたいする答えとなるものである。本質は、そのものがなんであるか言表することを可能にする本質的特徴からなる。自己の本質的特徴として「自分であること」、「私という人称詞で指示されること」、「意識作用の主語となること」、「自己同一性を有すること」などが挙げられる。これにたいして「勤勉」や「短気」などの特徴は自己に帰属するものではなく偶有的である。本質的特徴から「自己」やその人称化である「私」の概念が生じる。「自己」や「私」の概念は、「自我」の概念に置きかえることもできる。自己が概念化されることによって個としての自己もしくは<じぶん>と、「私」や「自我」などと呼ばれる自己との二重化が生じる。事物の概念化において意識はと事物の意識と概念とのあいだの幅をもつように、自己の概念化においても自己意識は個としての自己もしくは<じぶん>と、「私」もしくは「自我」などの概念とのあいだの幅をもつ。
「自分」の概念は、言葉以前の<じぶん>に「ジブン」という音声を適用することによって形成される。「自分」は、知性による本質把握の結果得られた普遍的・抽象的・観念的な自己概念である。そのため人間はだれしも自分のことを「自分」という言葉で指示できる。自己をその本質において把握しようとすると、必然的に自己は「自分」という言葉で概念化される。しかし概念化の基礎をなす自己の本質的特徴そのものは、個としての自己もしくは<じぶん>の了解から汲み取られている。事物との関係において具体的な個物そのものは概念化されないように、自己との関係において個としての自己、すなわち言葉以前の<じぶん>は概念化されない。つまり、「自分」の概念が生じる源である個としての自己もしくは<じぶん>が言葉によってからめとられることはない。 自己意識は<じぶん>の了解から出発して「自分」の概念へ進むとともに、「自分」の概念の理解の源泉を自己性の了解にもっている。
「自分」の概念と同様、「私」の概念は個としての自己から本質的特徴を抽出して形成された本質に「ワタシ」という音を適用することによって形成される。「私」の概念は普遍的であり、一人称詞としてだれでも使用でき、また理解できる。しかし、こうして形成された普遍的な自己概念としての「私」は、実際の発話においてはそのつどの個としての自己を指示する。事物の概念化で意識が事物を概念で捉えると同時に具体的な個物に向かうように、自己の概念化において意識は自己を概念で捉えると同時に個としての自己に向かう。発話者が「私」というとき、それは自己を万人に共有される一人称詞によって提示すると同時に、だれとも共有されない個としての自己を指している。それというのも「私」の概念の了解内容は、個としての自己もしくは<じぶん>の了解から汲み取られているからである。
自我論的考察において確認したように、「自我」は意識にたいして一人称として顕在化した限りにおいて存在する。自我は実体的なものではなく、意識の統御の働きにおいて「私」として顕現する。意識の統御の働きにおいて「私」として顕現するのは自己である。自己は言葉以前の<じぶん>の了解であり、この了解を言葉で表す人称詞が「私」である。自己意識は、「私」という言葉で言語化されて反省的な自己意識となる。自己を「私」という言葉で概念化することによって自己が明示的に意識される。しかし、自己と「私」という言葉のあいだに必然的な関連性がないことはすでに指摘したとおりである。自己の概念を表す言葉は、「私」以外に一人称を表すどんな名称でもよい。「私」に代わるいかなる名称を用いようと、自己意識は言葉によって分節化されて成立する。言葉がなければ自己意識はなく、あるのは動物的な主体の意識のみであろう。「自然との関わりにおいて自発的かつ能動的であること」(第3章第2節)の定義に合致する限りで、昆虫や魚類や鳥類や哺乳類を含めた動物はすべて主体である。しかし、動物はたとえ主体ではあっても自己意識をもたない。その理由は、動物は自己を自己として表す言葉をもっていないからである。
事物の概念化と自己の概念化のいずれが先におこなわれるかという議論は意味がない。事物の概念化の要諦は、事物の意識において事物の本質を把握することである。それによって人間の意識の幅は事物と本質にまたがるように拡大する。他方、自我の概念化の要諦は、意識に現れる自己の本質を把握することである。それによって自己は「私」という言葉もしくは「ワタシ」という音で呼ばれる。「私」もしくは「ワタシ」と呼ばれる自己は、主体としての人間の活動を主語として統御する自我である。人間の活動は自我が主語として統御することによって成立する。意識作用も人間の活動に含まれる限り、自我が主語となることによって意識作用が成り立つ。事物の概念化において、たとえば私が外界の事物を木として把握するとき、その意識作用を自我が主語として統御しなければならない。しかし、自我が意識作用を統御できるためには、自己の概念化によって自我が確立されていなければならない。自我が確立されていなければ、事物が「私」を主語とする統語的構造において意識されることはできない。「私」が主語となるという観点では自己の概念化は事物の概念化に先行する。他方、意識は基本的に外界にたいして開かれており、自然の事物を受け入れるように構えている。それゆえ意識はつねにあるものの意識であり、事物の意識でない自己意識は存在しない。この観点からは事物の概念化が自己の概念化に先行する。ようするに事物の概念化と自己の概念化は互いを前提として成り立ち、どちらか一方が欠けても成立しないのである。
5.言語の意味
「言語の意味」というとき、この問いそのものが多義的である。問いの内容として考えられるものを挙げると、
(1)言語そのものの意味、すなわち言語の本質への問い(「言語とはなにか」)。
(2)言語がもつ意味、すなわち意味の本質への問い(「言語における意味とはなにか」)。
(3)実際に使われる言葉の意味への問い(「特定の言葉の意味はなにか」)。
(4)言語が有する意義への問い(「共同体における言語の意義とはなにか」)。
このうち(4)については前節で、(1)については本節ですでに論じたので、ここでは(2)言語における意味の本質と、それに関連して(3)実際に使われる言葉の意味について考察する。
言語における意味は、意味するものと意味されるものによって成り立つ。意味するとは、対象とするものが主体の関心の脈絡に組み入れられ、それによって理解の志向性が満たされることである。理解の志向性が満たされることによって「わかった」という心理体験が生まれる。言語において意味するものは音声や文字などの言語媒体であり、意味されるものは言語媒体によって指示される事物である。言語媒体が事物を指示することによって、事物は意味されるものとなる。言語媒体が指示することがなければ、事物は事物そのもののままであって意味されるものとはならない。事物が意味されるものとなるためには、言語媒体によって指示されなければならない。しかし言語媒体そのものは意味ではない。たとえば「リンゴ」という音声は<リ・ン・ゴ>という一連の音素からなり、これらの音素のいずれにも意味は宿っていない。他方、言語媒体によって指示される事物も意味ではない。「リンゴ」という言葉で指示されるものは目の前に存在する果物であるが、果物は物体であって意味ではない。言語の意味は言語媒体そのものでも、言語媒体によって指示される事物そのものでもなく、両者の関係のうちにある。意味は、事物を指示する言語媒体と言語媒体によって指示される事物との関係によって成り立つ。言語媒体と事物は互いに指示し、指示される関係にある。これを指示関係という。しかしながら言語媒体はそれ自体では事物を指示できない。たとえば「リンゴ」という言葉(名称)は、音声であれ文字であれ、直接事物としてのリンゴを指示できない。なぜなら「リンゴ」という言葉自体は、本来リンゴの事物と無縁のものだからである。実際に「リンゴ」という言葉が「リンゴ」と呼ばれる事物を指示しているように思えるのは、リンゴの概念がこの指示関係を仲介しているからである。概念が言葉と事物の関係を仲介することによって、言葉が概念を指示し、概念が事物を指示する。その結果、言葉と事物のあいだに対応関係が成り立ち、言葉は事物を指示できるのである。
言葉の意味を理解するとは、言葉とその言葉が指示する事物との指示関係を理解することである。たとえば「リンゴ」という言葉を聞いて、知覚の場合ならリンゴの実物を指差し、想像の場合ならリンゴのイメージを思い浮かるとき、言葉と事物の指示関係が理解されているということができる。知覚と想像のいずれの場合も、「リンゴ」という言葉はリンゴの事物を指示し、リンゴの事物は「リンゴ」という言葉で指示される。言語の意味とは、この言葉と事物の指示関係である。「リンゴ」という本来リンゴの実物とは無縁の言語媒体が「リンゴ」と呼ばれる事物を指示できるのは、リンゴの概念がリンゴという言葉とリンゴの事物との指示関係を仲介しているからである。概念に仲介されて言葉が事物を指示することを指示性という。言語の指示性は、概念が言葉と事物の指示関係を仲介することにもとづく。また、概念が言葉と事物の指示関係を仲介することは、概念がそれ自体で完結しておらず、言葉が指示対象である事物と緊密に関係していることに根差している。概念が事物と緊密に関係していることは、すでに見たように事物の概念化が事物と概念のあいだの抽象と指示という意識の双方向の働きであることに起因する。概念が言葉と事物の指示関係を仲介できるのは、概念が事物の概念化において目の前の事物もしくは記憶に保存された事物のイメージと結びついているからである。言語の意味とは、概念によって仲介された言葉と事物の指示関係である。
ここで「言語の意味」と「言葉の意味」を区別するならば、言語の意味とは、上記の(2)言語がもつ意味であり、言葉の意味とは、(3)実際に使われる言葉の意味である。言語の意味は概念によって仲介された言葉と事物の指示関係であり、言葉の意味はこの指示関係にもとづいて生じる言葉の意味内容である。言葉の意味を理解するとは言葉と事物の指示関係を理解することであるが、それは人間にとってなかば先天的に身についた能力である。ここで「なかば先天的」というのは、事物の本質把握は人間独自の認識方法として人間に先天的に備わっているが、事物の本質把握によって形成された本質に名称を与えて概念化するためには言葉を学習しなければならないからである。とまれ事物の本質把握の能力は人間に生まれつき備わっているので、日本語の言語共同体に属する子供ならば就学年齢に達する前でも、「リンゴ」や「イヌ」といった基礎的な言葉の意味を理解することができる。子供が言葉の意味を理解できるとは、たとえば「リンゴ」という言葉を聞いて、テーブルの上においてある果物籠からリンゴを取り出すことができるということである。子供が果物籠からリンゴを取り出せるのは、「リンゴ」という言葉が目の前の赤い果物を指していることを理解しているからにほかならない。このとき子供の頭のなかで起きているのは、リンゴという言葉を聞いて記憶されているリンゴの概念を構成する本質的特徴と目の前の事物の本質的特徴を照合して、両者が一致することから目の前の個物をこの概念の外延に含まれると判断することである。
子供は自宅で飼っている犬も、公園を散歩しているよその家の犬も同じく「イヌ」と呼ぶことができる。このとき子供は、「イヌ」という言葉が特定の個物の名前ではなく、犬という類の名称であるということを理解している。「イヌ」という言葉は犬の概念に与えられた名称である。概念は事物の本質把握にもとづいて形成され、事物の本質把握は複数の事物に共通する特徴を抽出することによってなされる。複数の事物に共通する特徴からそれらの事物の本質が把握され、これに名称が与えられて概念が作られる。このようなプロセスを経て形成される概念は、個物の固有名称ではなく個物を包摂する類の名称である。子供が異なる場所で異なる個体の犬をいずれも「イヌ」と呼ぶのは、子供が明らかに「イヌ」という言葉が個体としての犬の固有名称ではなく犬という類を表す一般名称であることを理解していることを示している。
念のためにいうと、子供はリンゴや犬という言葉の意味を理解しているが、それはリンゴや犬という言葉と事物の指示関係を理解しているということであり、これらの言葉の辞書的な意味を知っているということではない。辞書に収録されている事項の説明は、辞書の編集者が収録語に関する情報を最大限収集し、「林檎」4)であれば植物学、「犬」5)であれ動物学などの専門知識も借用して定義したものである。編集者は長年かけて習得した文章力を発揮して、できるだけ客観的な知識や情報を簡潔に定義することに注力する。辞書的意味は、編集者によって客観的な定義の最大公約数として選択されたもので、本来の言語の意味とは完全に別物である。子供は犬やリンゴという言葉の意味を理解するために、辞書に書かれている知識をまったく必要としない。子供が言葉の意味を理解するために必要とするのは、事物の本質把握と概念化によって生じる言葉と事物の指示関係のみである。言葉の意味を理解するとは、言葉と事物の指示関係を理解することである。辞書に記載されている説明文も、書かれているすべての語句がそれぞれ言葉と事物の指示関係によって意味を与えられているのである。
リンゴという言葉の意味はリンゴ本体のなかにはなく、リンゴという言葉のなかにもなく、その言葉が事物としてのリンゴを指示することのうちにある。ある言葉の意味内容は、その言葉と事物の指示関係を仲介する概念の内包と等しい。概念は、感覚が直接受容した事物の情報から抽出された本質的特徴を綜合し、これに対応する名称を適用することによって形成される。事物は、このような本質把握と概念化を経て名称が与えられる。あるいは目の前の事物を特定の名称で呼ぶことによって、事物の本質把握と概念化がおこなわれる。事物を名称で呼ぶことは、事物を本質において把握することであり、さらに把握された本質から事物の概念をつくることである。このような<事物-本質-概念-名称>の認識論的プロセスは、人類が進化の過程で獲得した能力であり、人間に生得的に備わっている。人間は生まれつきそのような仕方で認識するようになっており、それ以外の認識方法は不可能である。幼い子供が特別の訓練を受けることなく、補助的に誘導するだけで言葉を話すようになるのも、生まれながらにしてそのような認識方法を身につけているからである。
他方で、本質把握と概念化の対象となる事物は経験において所与として与えられる。経験の基礎は、主体としての人間が所与として与えられた事物を知覚することである。知覚するとは、感覚によって与えられた事物の感覚情報を特定のものとして受け取ることであり、それは知性によって事物を概念化することである。事物を概念化するためには、事物についての感覚情報をもとに知覚情報を形成し、本質把握と概念化の手続きを経て概念に相応の名称を割り当てなければならない。事物の概念に割り当てる名称は、言語共同体によって決められているため、それぞれ属する言語共同体が決めた事物の名前を学習する必要がある。人間の認識能力もしくは認識方法としての言語は先天的に備わっているが、言語の素材である言葉そのものは経験的に学習しなければならないのである。
言語における指示とは、音声や文字などの言語媒体によって事物を指し示すことである。言語媒体としての言葉と、言葉によって指示される事物との指示関係において意味が生じる。しかし、<リ・ン・ゴ>という一連の音素が直接、つまりいかなる認識論的な手続きを経ることなく物体としての果物を指示することは不可能である。同様に「林檎」の文字が認識論的な手続きを経ることなく直接事物を指示することもない。ここでいう認識論的な手続きとは、本質把握にもとづく事物の概念化である。概念は、<事物-本質-概念-名称>という認識論的プロセスを経て形成される。そのため発話された言葉の意味を理解しようとするなら、このプロセスを逆方向にたどらなければならない。つまり、特定の名称で呼ばれる言葉を聞いてその意味を理解しようとしたら、その語の概念を把握しなければならず、概念を把握するためには記憶に保存されている概念の本質的特徴を想起して、それらの特徴を備えた事物を表象しなければならない。たとえば「キ」という音で呼ばれる語の意味を理解するためには、木の概念を捉えなければならず、そのために記憶にある木の本質的特徴を想起してそれらの特徴を備えた事物のイメージを想像するか、または目の前に知覚していなければならない。このように、ある名称を聞いてその語の意味を理解するためには、<事物-本質-概念-名称>という概念化のプロセスとは逆の指示関係のプロセス、すなわち<名称-概念-本質-事物>というプロセスをたどる必要がある。この概念化と逆方向の指示関係のプロセスが言葉と事物をつなぎとめて、言葉と事物の指示関係を成立させているのである。
事物の概念化では目の前の事物から抽出された本質的特徴にもとづいて心的領域に概念が形成され、それが音韻と結合して言葉が生じるが、このとき同時に意識は目の前の個物に向かっている。つまり意識は概念化のプロセスによって目の前の事物から方向を転じることなく、プロセス中も依然として目の前の個物を捉えているのである。概念化のプロセスを経て形成された言葉が、このプロセスを逆にたどって個々の事物を指し示すことができるのはそのためである。意識は、事物の感覚情報から概念を形成する働きにおいては事物から言葉に向かうが、言葉の意味を理解する働きにおいては概念から事物に向かう。事物の概念化は、抽出された本質的特徴から概念が形成された時点で完了する一方向の運動ではなく、同時に概念から事物に向かう双方向プロセスである。
この事物と概念のあいだの双方向プロセスにおいて、事物の特徴を探知するのは感覚であり、事物の特徴を本質的特徴と偶有的特徴に弁別するのは知性である。目の前の事物について、感覚によって事物の構成要素に関する情報が知性に伝えられ、知性がそれらの情報から本質的特徴を抽出して本質を把握し、これに既定の名称を適用して概念化する。木の例でいうと、目の前にある事物の構成要素である幹や枝や葉や根に関する感覚情報が知性に伝えられ、知性がそれらの感覚情報から本質的特徴を抽出して本質を把握して、それに「木」という名称を適用する。それによって目の前の事物は「これは木である」という知覚判断で同定される。しかし知性が幹や枝や葉や根などを木の構成要素として判断するためには、それらの要素自体も概念化される必要がある。つまり、目の前の事物の概念化がおこなわれ、その事物が「木」という言葉で呼ばれるためには、木の構成要素について感覚が提供する感覚情報がそれぞれ「幹」や「枝」や「葉」や「根」などの言葉で概念化されなければならない。そのためには木の個々の構成要素について「これは幹である」、「これは枝である」、「これは葉である」などの知覚判断が形成されなければならない。さらにこれらの要素に樹皮や木質や色や硬さなどの感覚特徴も加えたら、それらについても同様の認識論的手続きが必要である。追加の感覚特徴として樹皮が茶色で木質が硬い幹を感覚が感受したら、これらの特徴自体が言語化されなければならない。その結果、「これは茶色の硬い幹である」という知覚が形成される。このように感覚は個々の事物について多様な特徴を受容できるが、感覚が受容する特徴が多様であればあるほど、それらを概念化した知覚の内容は豊富になる。それは感覚が受容するあとから、感覚が次々と感覚情報を概念化するからである。事物の知覚において感覚がどれほど多様な事物の特徴を探知しようとも、知性はどこまでも感覚のあとを追い、感覚が受容した特徴を瞬時に言葉に変換して概念化する。
知性はどこまでも感覚のあとを追うといっても、感覚を追い越すことはけっしてない。知性が感覚を追い越すとは、知性が感覚に取って代わることであるが、そのようなことは認識の構造からけっして起こらない。自然の一部である人間が自然と交流するために、感覚は自然の事物を直接受容する。感覚が個々の具体的な事物を直接受容するのにたいして、事物をその本質において把握するのが知性の役割である。知性は感覚が感受した事物の無数の感覚特徴から偶有的特徴を捨象して本質的特徴を抽出し、抽出された本質的特徴にもとづいて本質を把握して概念を形成する。形成された概念とその名称は、同じ本質的特徴を有するすべての事物に普遍的に妥当する。自然の事物が個別的・具体的・物体的であるのにたいして、概念は普遍的・抽象的・観念的である。自然の事物をその個別性、具体性、物体性において受容するのが感覚の役割であるなら、知性の役割は感覚によって供給された自然の事物の直接的な情報から、言葉を介して事物の普遍的・抽象的・観念的な概念を作り出すことである。そのために知性は感覚が供給する事物に関する情報の概念化に専念する一方で、事物そのものの受容は全面的に感覚にゆだねるのである。
自然の事物の概念化によって事物と概念への二重化が起こり、人間は事物との直接的関係から離脱するが、感覚のレベルで事物から離れるわけではなく、また離れることはできない。なぜなら自然の事物は所与として人間に与えられており、感覚はそれを受容するために発達した意識形態だからである。そもそも人間の意識作用が成立するために、自然の事物が所与として人間に所与として与えられていることが大前提である。意識はそれ自体で環境の意識であり、意識の一次的形態である感覚は個々の事物と緊密につながっている。感覚が事物と緊密につながっているからこそ、事物の諸特徴を探知して感覚情報として知性に伝えることができるのである。たとえ人間が概念化によって事物との直接的関係から離脱しても、意識が概念化の基礎をなす事物の諸特徴を完全に手離すことはない。概念が知性の産物であるのにたいし、感覚が探知するのは自然の事物であり、人間は感覚をとおしてそれらと直接的につながっている。事物の情報を収集して知性に提供するのが感覚の役割であり、そのために感覚が自然の事物とつながっていることは、概念が成立する前も成立したあとも変わりはない。感覚がつねに事物とつながっていることが、最終的に言語の指示性を担保するのである。
1)ここでいう「本質把握」は現象学における「本質直観」とは異なる。フッサールにとって本質は普遍的なもの(形相、類、イデー)である。フッサールは現象学的還元を経ることによって本質を判断や推論などの知的操作を介さずに直接観取することができると考え、これを直観(Anschauung)と呼んだ。本論では、本質は直接観取されるものではなく、事物の本質的特徴と偶有的特徴の弁別という知的操作によって把握(begreifen)され、それが言語化されて概念(Begriff)になると考える。
2)カントは『プロレゴメナ』で経験的判断を経験判断(Erfahrungsurteil)と知覚判断(Wahrnehmunssurteil)の二種類に区別している。経験的判断はさしあたって二つの感覚を結び合わせたにすぎない知覚判断であって主観的にしか妥当しないが、この結合が判断の必然的条件であるカテゴリーによってなされると客観的に妥当な判断すなわち経験判断となる。本論でいう「知覚判断」は「これは〜である」という形式で言表される判断であり、カントの定義に準じるならば『プロレゴメナ』の「経験判断」にほぼ相当する。
3)言語による自然の再構成について、ソシュールは、『一般言語学講義』(町田健訳)のなかで次のように述べている。「哲学者と言語学者が常に一致して認めてきたのは、記号の助けがなければ、2つの観念を明確に、そして定常的に区別することはできないだろうということである。それ自体として考えてみると、思考は星雲のようなもので、必然的に境界を定められたものは存在しない。だから、あらかじめ確定している観念はないし、ラングが登場する前に区別されているものはない。」ここから明らかなように、ソシュールの場合に言語が境界を定めるのはあくまでも観念同士のあいだであって、自然にたいしてではない。これを言語が自然そのものに境界を定めるというように拡大解釈すると言語決定論にいきつく。言語学者の丸山圭三郎は『言葉と無意識』のなかで次のように書いている。「幼児にとって対象物というものは、それが名前をもった時にはじめて知られ、存在する。そうしてみると、ロゴスとしての(名=言葉)があってはじめて世界は分節され、実質的なもろもろの差異が構造的同一性で括られることによって存在を開始するのであるから、ロゴスが生み出したカテゴリーこそが、一見自存的実体と思われていた<指向対象>だと言わねばならない。」丸山はここで「名前をもった時にはじめて…存在する」とか「存在を開始する」と書いているが、存在は認識に先行する。言葉は存在を認識する方法であり、言葉に事物を存在させる力はない。意識は本来あるものの意識であり、あるものとは意識に所与として与えられた具体的な個物である。意識は所与として具体的な個物から出発して本質を把握する。把握された本質を固定化するために命名することによって概念が生じる。概念の名称そのものは命名された事物と必然的な関係はない。しかしながら具体的な個物から抽象されて形成された概念は、意味内容を確保するためにあくまでも具体的な個物とつながっている。丸山の場合は、命名することによって事物は「指向対象」になると考える。丸山が定義する指向対象はシニフィエによって誕生する。指向対象はシニフィエの意識内容である。事物はシニフィエで命名されることにより指向対象となり、その結果意識内容に転じる。丸山は言葉によって分節された指向対象を事物と等置することによって観念論に陥らざるをえない。
4)「林檎:バラ科の落葉高木。また、その果実。葉は卵円形。4、5月ごろ、葉とともに白または淡紅色の5弁花を開き、のち球状の赤色などの実を結ぶ。甘酸っぱく白い食用部は、花托の発達したもの。ヨーロッパ中部から南東部の原産。日本には明治時代に欧米から紅玉・デリシャスなどの品種が導入され、青森・長野などで栽培。古くは、在来の和林檎などをさした。」(デジタル大辞泉)
5)「犬:食肉目イヌ科の哺乳類。嗅覚・聴覚が鋭く、古くから猟犬・番犬・牧畜犬などとして家畜化。多くの品種がつくられ、大きさや体形、毛色などはさまざま。警察犬・軍用犬・盲導犬・競走犬・愛玩犬など用途は広い。」(デジタル大辞泉)