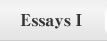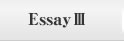第4章 言語論的視点
第1節 言語
1.文化
主体論的考察において見たように、 人間と自然の関りの基本構図である<主体-客体関係>において、主体としての人間は客体との関わりをとおして能力を形成する。能力は、主体が客体に働きかける場面で発揮される主体の諸特性である。主体は客体への働きかけにおいてその能力を発揮すると同時に、客体との相互作用をとおして主体の諸特性を発展させる。一方、人間は生来共同性を特性としており、他の人間と共同関係を結んで共同体を形成する。共同体のなかで主体が客体と関わるのはつねに他の主体との共同関係においてである。共同関係において個々の主体によって形成された能力は、その成果をとおして共同主体に共有される。個々の主体の能力とその成果が共同主体によって共有されることを共有化という。逆に、共同主体によって形成された能力は、共同関係を構成する個々の主体によって獲得される。共同主体によって形成された能力が個々の主体によって獲得されることを学習という。
この場合、能力の共有化も学習も一方通行ではなく必ず双方向で進行する。個々の主体の能力とその成果の共有化だけが一方的におこなわれることがないのは、個々の主体を離れて共同主体は存在せず、個々の主体の能力を共同主体が共有することは、共同体を構成する多数の個々の主体が獲得することにほかならないからである。共同体による能力の共有化は、実際には個々の主体による学習の過程として実行される。特定の主体の能力が共同主体によって共有されることは、共同体を構成する個々の主体によって学習されることである。個々の主体の能力の共有化が一方向でおこなわれることはないように、共同主体がもつ能力の学習が一方向でおこなわれることもない。なぜなら個々の主体が共同主体の能力を学習することは、共同主体の能力が個々の主体に獲得されることをもって終結せず、個々の主体は共同主体から学習した能力を共同主体にフィードバックするからである。この場合、共同体を構成する個々の主体は共同主体から学習した能力を基礎に、それぞれの能力を発展させて客体との関わりにおいて発揮する。その成果をとおして個々の主体によって獲得された能力が共同主体により発展したかたちでフィードバックされて共有される。このようにして主体の能力と能力の成果は、共同体を構成する個々の主体による学習と共同主体による共有化のプロセスによって共同体内で伝達されて拡散されるのである。
共有化によって共同主体に共有され、学習によって個々の主体に獲得され、共同体によって継承される主体の能力を文化という。文化は、学習によって獲得され、共有化によって共有され、共同体によって継承される共同主体の能力である。文化は人類が地球上に誕生して以来の進化の過程で確立されて、現在まで継承されてきた。文化が原動力となって、人類は他の生物との生存競争に勝ちぬくことができた。その意味で文化は、共同性を生来の特性として他者と共同して生きる人類の生存戦略の所産である。
人類の最古の文化は言語と技術である。言語は人類が自然のなかで生存競争を勝ちぬくための生存戦略によって生み出された。言語は人間が自然を認識する能力である。人間は言語を獲得したことにより自然をまったく独自の仕方で、つまり概念で認識することが可能になった。さらに人間は認識手段としての言語を意思伝達手段として用いることによって認識を他の人間と共有することができた。そのため言語は共同体における主体間の意思伝達手段として学習され共有化された。学習と共有化によって、人間が自然を認識するための先天的な能力である言語は文化となった。
人間は「自然の一部」としてたえず自然と交流しなければならず、そのために自然の事物を人間が使用できるように加工する必要がある。人間は言語能力によって自然を概念で把握し、概念にもとづいて自然を加工するための手段として技術を発明した。技術を手にいれたことにより自然を効率的に加工できるようになった。技術は言語を介して学習され、共同体内の他の主体と共有化された。共同主体によって獲得された技術は言語を介して文化として継承された。それにより技術の連続的な発展が可能となった。こうして人類は、言語と技術という二つの文化の相乗作用により加速度的に進化したのである。
文化の本質は、共同主体によって共有された能力が次世代に継承されることである。生物学では「獲得形質は遺伝しない」というのが定説とされている。たしかに親世代の体細胞が後天的な要因によってどれほど変化しようとも、遺伝をになう生殖細胞が影響を受けない限り子世代には遺伝しない。そのため生物の場合は、突然変異が生じない限り進化は起こらない。しかし人間は先行世代が獲得した能力を文化として後続世代に継承することができる。後続世代は継承した文化を学習と共有化によってさらに拡大して次世代に引き渡す。この文化の継承を、何千、何万という世代にわたり繰り返してきた結果、人類は他のいかなる生物とも比較できないほど大規模な進化を遂げたのである。
2.言語の誕生
本論において「言語」と「言葉」を厳密に区別しない。しいていえば「言語」は言語規範、言語活動、言語能力などの総称として用いる。この場合、言語は包括的に共同体の言語体系を意味する。他方、共同体の個々の成員が使用する言語は「言葉」と呼ぶ。言語を言語体系とするならば、実際に使用される言葉はいわば言語の素材である。言語は共同主体が客体としての自然と関わる場面で発揮される主体の能力である。能力としての言語は、特に「言語能力」とも呼ぶ。言語能力を発揮する活動は「言語活動」、言語活動を規制する規範は「言語規範」という。
言語は、進化の過程で人間が生存環境を認識する方法として誕生した。以来、言語は人間が先天的に身につけている能力となった。本論にいう能力とは、主体の客体への働きかけにおいて発揮されて、客体になんらかの改変をもたらす主体の特性である。自然を加工する技術とは異なり、言語は自然に物理的な改変をもたらすものではない。言語は加工すべき自然の事物を認識することに発揮される。人間は自然の事物を了解し言語化することによって認識する。この自然の言語化は、人間が自然のなかで生存する必要性から生み出された認識能力である。自然の認識において人間が他のいかなる生物とも根本的に異なるのは、目の前にある事物について、それがなんであるか問うことである。事物がなんであるか問うとは、事物をその本質において把握することである。人間は進化の過程で事物をその本質において把握する手段として言語を獲得したのである。
目の前の事物がなんであるかを認識するために、感覚が周囲の情報を収集し、知性がそれらの情報を処理して知覚を形成する。事物を知覚にもとづいて特定のものとして認識することを同定という。事物の同定は言葉によっておこなわれ、典型的に「これは〜である」という判断としてなされる。この判断によって事物は、それがなんであるかにおいて、すなわち事物の本質において認識される。人間を取り囲む自然の事物が言葉で特定され、個々の自然の事物がなんであるか把握されることによって、人間の周囲環境にたいする認識は格段に正確で緻密なものになった。人間はその認識が高度になったことにより、そのつどおかれた状況で取るべき行動をより的確に選択できるようになった。その結果、人間は他の生物との生存競争において圧倒的に優位に立つことになったのである。
人間以外の動物も、それぞれ進化の過程で独自の認識能力を身につけることによって現在まで生き延びてきた。たとえばコウモリは超音波を出してその反射音によって自然の事物を把握する。人間の8~10倍の視力を備えたワシは高い上空1キロメートルから地上の獲物を見つけることができ、約1900個の嗅覚受容体をもつアフリカゾウは遠くの水源を探しあてられる。動物のように発達した聴覚や視覚や嗅覚をもたない人間が身につけた認識能力が言葉であった。人間が言葉を獲得したのは、それまで水中に生息していた魚類が陸に上がり、あるいは陸上を闊歩していた恐竜が空を飛ぶようになったのと同じく、進化史上の出来事である。
人類は言葉をもつことにより、それまでの地球の歴史になかった方法で自然と関わるようになった。人間は自然を言語化して事物をその本質において認識した。本質とは複数の事物に共通なものである。人間は個々の事物からそれらに共通なものを抽出することにより、普遍的なものを認識できるようになった。自然界に存在するのはすべて個別的なものであり、普遍的なものは存在しない。普遍的なものは観念として人間の頭のなかにだけ存在する。普遍的なものが人間の頭のなかに観念として存在するのは具体的なものとしてではなく、抽象的なものとして、すなわち言葉としてである。人間は言葉を用いて自然の事物を本質において認識することにより、具体的な個物にとらわれない普遍的・抽象的・観念的な思考が可能になった。その結果、人間は直接的な視野を越えて自然を俯瞰して、多角的、多面的に認識できるようになった。人間はこの高度な認識にもとづき自然のなかでさまざまな方策を企図した。企図の成果は言葉を介して共同体の成員によって共有化され、文化として伝承された。生物は地球上に出現してからこのかた遺伝的進化の軌道をたどってきたが、生物としての人間もその例外ではない。しかし人間があらゆる生物と決定的に異なるのは、言葉をもった瞬間に遺伝的進化の枠を超え出て文化的進化の軌道に乗ったことである。文化的進化を重ねて、人類はますます拡大発展し、地球上に巨大な文明を築いたのである。
3.言語の学習
言語は共同主体によって共有されて共同体によって継承されるが、実際に言葉を使用するのは共同体に属する個々の主体である。言語は主体による客体としての自然の認識能力として誕生した。この場合、言葉は第一義的に客体としての自然の認識手段である。人間は自然の認識にもとづいて思考する。それゆえ言葉は思考の道具である。しかし人間の意識作用は、思考のほかに意志や感情も含んでおり、これらすべてが言葉で表現される。総じて言葉は主体の意識の表現手段である。意識を言葉で表現するとは発話することである。発話することによって主体は自分の意識内容、たとえば意志や感情や思考を他者に伝達することができる。したがって言葉は第二義的にコミュニケーションの道具でもある。当然のことながら、自分の意識を表現する手段と、それを他者に伝達する手段は同じ言葉でなければならない。なぜなら、自分の意識を表現して他者に伝えるためには、自分と他者が所属する共同体を構成する共同主体によって共有された伝達手段を使用しなければならないからである。共同主体によって共有された伝達手段を用いて自分の意識を表現するためには、伝達手段としての言葉を学習する必要がある。学習は個々の主体が共同主体によって共有された能力を獲得する過程である。個々の人間は言葉の学習をとおして、身体的にも精神的にも共同体に参入するのである。
共同体において個々の主体が言葉を使用するためには、それぞれが言語能力を培わなければならない。そのためには個々の主体は、共同主体によって共有された言語を学習する必要がある。言葉の学習は、主として幼児と両親のあいだで始まる。幼児は両親が繰り返し話しかけてくる音声を耳にしているうちに、自分が特定の音声で呼びかけられているらしいと思うようになる。やがて幼児はその音声が自分を指していることを理解する。これは人間の精神の発達史において、次のいくつかの点で画期的な瞬間である。
第一に、幼児が特定の音声で呼びかけられていることに気づいたとき、幼児にとって自分に呼びかける音声は単なる音の響きではなく名前となる。音声は名前となることにより、音そのものとはまったく別の機能をもつ。それは記号としての機能である。記号はそれ自体は音声や文字などの媒体であるが、記号が指示するのは媒体自体とは別のものである。たとえば両親が幼児に呼びかける「タロウ」という音声はそれ自体は音声媒体であるが、名前としては幼児を指示する記号である。音声を記号として把握することによって、幼児は音声媒体から音そのものと、その音によって指示されている内容を聞き分ける。音そのものは両親の声であり、音によって指示されている内容は名前である。だから幼児は、父親から母親の声とは異なる声で名前を呼ばれても、それが自分を指していると名前であると理解する。これは幼児が音声を聞いて、媒体としての音と、その媒体によって伝達される指示内容を弁別している証左である。
第二に、自分に呼びかけられた音声が自分を指していることを理解するとき、幼児は自分を対象化する。対象化とは、記号が指し示すものを記号の指示対象として把握することである。記号はそれ自体とは別のものを指示するのであるから、幼児は特定の音を自分を指示する記号として把握することにより、その記号で指し示された自己を対象化する。自己を対象化するとは、自己を反省して自己との一体性から離れて自分自身にたいして距離をとることである。この自分自身にたいする距離はそのまま両親との距離に反映される。幼児は自己との一体性を離れて自己を対象化するように、両親、とりわけ母親との一体性からも離れて母親を対象化する。幼児は特定の名前で指示される自己を認識するとともに、母親を自分とは異なる他者として認識する。幼児は対象化された自己を特定の名前で把握するとともに、他者としての母親のことも特定の言葉で呼ぶことを覚える。母親を表す言葉は「ママ」や「おかあちゃん」などいろいろあるが、いかなる呼称を用いようとも本質的なことは、自己と他者を特定の名前で呼ぶことによってそれぞれを対象化することである。
第三に、幼児は自分が特定の名前で呼ばれていることを認識し、両親を特定の言葉で呼ぶことを覚えるのと並行して、身のまわりのすべてのものにもそれぞれ名前があることを理解する。身のまわりの事物を名前で呼ぶことは、自分や両親やその他の家族をそれぞれの名前で呼ぶのとは本質的な違いがある。なぜなら、事物を名前で呼ぶのは、事物を種類として把握することだからである。たとえば一匹の犬を見て「ワンワン」と指さす幼児は、別の犬を見ても「ワンワン」と呼ぶ。それは「ワンワン」という言葉が特定の犬を指す固有名詞ではなく、犬という種類を表していることを幼児が理解していることを意味する。この成長段階で幼児はすでに普遍的・抽象的・観念的な思考を開始しているのである。
人間の成長のきわめて早い段階で経験するこの出来事が引き金となって、幼児は猛烈な勢いで言葉を学習する。それは幼児が属する共同体の言語に関する約束事を身につける過程でもある。というのも、幼児が使用する言葉は共同体が提供するものであり、その言葉を使用するための規則は共同体が定めるものだからである。幼児は自分に呼びかけられた音を名前として把握することに始まり、家族にも身のまわりにあるすべてのものにも名前があることを理解し、それらの名前を覚えることによって言語共同体に参入する。身のまわりにあるものを名前で呼ぶことは、潜在的には世界のすべての構成要素を対象化することである。世界を対象化するとは、対象化された世界を心的領域に受容することである。幼児の言葉の学習能力は、実に目を見張るものがある。言葉を覚えるにつれて、幼児の心的領域は対象化された世界を受容すべく急速に拡大する。1)
4.言語共同体
この世界で人間は必ずなんらかの共同体に生まれ、その共同体で使用されている言語を学習する。同じ言語を使用する共同体を言語共同体という。言語共同体のなかで生きていくためには、当然それぞれの共同体で話されている言葉を身につけなければならない。そのため人間はこの世界に生まれると同時に言葉を学びはじめる。言葉は共同体の共有財産であり、共同体の成員と共同体との絆である。それゆえ特定の言語共同体に生まれた人間は、必然的にその共同体が共有している言葉を習得することになる。言葉を習得するにつれて、共同体とのつながりを深めていく。言葉は共同体との絆であると同時に、この世界への窓口でもある。共同体の言葉をとおして人間はこの世界に開かれ、この世界の事物や他の人間と関わる。人間は共同体の言葉を用いてこの世界の事物を理解する。この世界で他の人間と対話するのは、共同体の言葉を介してである。自分自身と対話するのも、つまり思考するのも共同体の言葉によってである。総じて人間は共同体が共有する言葉、すなわち母国語をとおしてこの世界を了解している。人間にとってこの世界は基本的に母国語環境である。
言葉は意識の表現手段であると同時に意識の伝達手段である。意識は音声または文字で表現されることによって可聴的もしくは可視的となる。可聴化もしくは可視化された意識は、言葉として他者に伝達されることができる。この伝達の局面で言葉は意識の伝達手段として機能する。意識は人間の心の働きであり、心の働きは外から他者が見ることも感じることもできないが、言葉で表現することによって他者に伝達できるようになる。言葉がなければ人間は意識を表現することも伝達することもできず、人間同士の意志疎通は不可能である。人間が他者と共同して共同体を形成するのは人間に生来備わっている共同性にもとづいているが、実際に共同体を維持できるのは言葉を介して互いに意思を疎通させることができるからである。人間は、言葉を介して他者と意識を伝達しあうことにより共同体を維持発展させるのである。
人類の意識が言葉を獲得するまでに進化した段階で、人間はなんらかの共同体に属していた。すべての人間は家族共同体、集落共同体、地域共同体などの共同体に属していた。共同体において人間は共同体の成員すなわち共同主体として互いに協力しなければは生きられなかった。目の前にある自然の事物が食べられるものであるか食べられないものであるか、周囲の状況が安全であるか危険であるか、巨大な猛獣をいかに一致協力して仕留めるかなどといったことを共同主体間で伝達することは共同体にとって死活問題であった。それゆえ言葉は共同体において共同主体間の意思伝達手段として発達した。しかし、だからといって言葉が人間同士のコミュニケーションの道具として誕生したと考えるのは単純にすぎる。たしかに、言葉は共同体によって意思伝達手段として用いられ発達した。言葉は共同体の財産として共同体に属するすべての人間に共有されていた。そのため言葉はコミュニケーションの道具として発明されたと考えやすい。だが、もし人間が言語という先天的能力を備えていなかったなら、言語がコミュニケーションの道具として発明されることはなく、意思伝達手段として用いられることもなかったはずである。そもそも意思伝達は伝達すべき内容がなければおこなわれない。言葉によって伝達される内容は自然の認識である。言葉が自然の認識手段として確立されない限り、共同主体間で意思伝達手段として言葉を用いることはないだろう。
言語が発生した先史時代は比較的小規模な共同体が無数に乱立し、それぞれの共同体の成員は目の前の自然の事物を指さしながらさまざまな音で呼んだことだろう。小さい共同体はより大きい共同体による征服や合同をとおして次第に拡大し、その過程で事物を表す音記号が統一されていった。この統一の過程で共同主体による共有化と個々の主体による学習が並行しておこなわれた。当初さまざまな音で呼ばれていた事物の名前を統一する共有化のプロセスは、個々の主体がそれを学習して獲得するプロセスをともなった。共同体のなかであらたに生を受けた成員にとっては、最初から自分が属する共同体内で使用されている言葉を身につける以外の選択肢はない。異なる共同体間で交流がおこなわれるようになると、コミュニケーションの必要から互いの言語を伝達可能にするための調整がおこなわれた。たとえば自分たちよりも軍事や経済の面で優勢な共同体が、同じ事物を異なる音で呼んでいたら、自分たちの方を変更して相手に合わせるというようなこともなされたであろう。やがて有力な共同体のなかから強大な共同体が出現すると、武力で弱小な共同体を滅ぼしたり併合したりして言語の統一化が促進された。そして国家が成立すると、多様な地域の方言や俚言を内包しつつ言語体系が確立されて言語共同体が成立した。
特定の言語共同体において、言葉が他者とのあいだの意識の伝達手段であるためには、言葉が互いに理解できるものとして、すなわち言語体系として確立されていなければならない。そのため単語や文法など言葉を構成する要素は、共同体の約束事として厳密に規定される必要がある。なぜなら、言葉が厳密に規定されていなければ言葉を介して他者と意識を正確に伝達しあうことができないからである。人間の意識を表現する手段である言葉が頻繁に変化したら、意識を他者に正しく伝達できなくなり、共同体内のコミュニケーションは成立しなくなる。そのため共同体の言語統制機関によって言葉にたいして基本的に変化しないことが要請される。
しかし、言葉がもつ本質にもとづき、この要請に応えられることはけっしてない。言葉は第一義的に意識の表現である。意識は原理的につねにあるものの意識である。意識はあるものの意識であるから、つねに具体的な内容からなる。この場合、意識の内容となるのは、およそ意識の対象となりえるすべてのものである。それは人間が心のなかで考えていることや、視覚や聴覚や嗅覚などの感覚がとらえた事物や、それらを取り巻く周囲の状況などである。しかし人間が考えることや、感覚が感知することや、周囲の状況などはもとより一定不変ではない。人間が自然と関わり、あるいは人間が人間と関わる過程ですべてのものが時々刻々と変化する。意識の対象が変化すれば、意識の内容も変化するのは必然である。意識の内容が変化すれば、意識を表現する言葉も変化する。言語の基本的な特徴、たとえば膠着語、屈折語、孤立語などの形式や、インド・ヨーロッパ語族、アルタイ語族といった語族や語派、さらにはそれらに蔵する各言語に固有の特徴は変わらないか、変わるとしてもきわめて長い時間かかる。が、その枠組みのなかで使用される語彙や語法はめまぐるしく変化する。たとえば新しい技術の開発や発見によってそれまでになかった製品なり産物なりが生み出されたら、あらたに命名しなければならない。さまざまな分野で技術革新が起こるたびに新しい言葉が爆発的に増える。外国から新しい文物がはいってきたらあらたに造語するか、それができなければ外国語をそのまま借用する。さらに社会生活の進展にともなって新語や流行語が続々と誕生する。共同主体が共有する言葉を個々の人間が獲得する過程が学習であるのにたいし、個々の人間が使用する単語や語法が他者と共有される過程は共有化である。伝染病が一人の罹患者から同じ環境下におかれた多数の人間に短期間で伝播するように、たった一人の若者が発した造語なり言い回しなりが同じ文化的素地のある若者のあいだであっというまに広まる。あるいは一人の技術者があらたに開発したシステムに新語を提案し、それが技術者仲間に受け入れられ、さらにマスコミに取り上げられたら一般に用いられるようになる。一人もしくは少数の人間の慣用的な語法から逸脱した発語が次第に多くの人間によって共有されていく。逸脱した語法は、ごく最初のうちは共同体によって「文法の誤り」や「言葉の乱れ」として規制される。しかしそれも時間とともに広く定着すれば、標準的な語法として認められるようになる。
特定の共同体に生まれた人間が自分の意識を表現しようとしたら、そのときどきの共同主体によって共有されている言葉を学習によって身につけるほかはない。共同主体によって共有された言葉は、教科書や文法書や辞書によって語彙から語法のレベルまで厳密に規定されている。理想的には、言葉はある共同体を構成する全員によって共有された完全な言語体系ということになろうが、現実にはそのようなものは存在しない。地域によって方言もあれば、社会階層によっても異なる。特定の集団だけに通用するジャーゴンや隠語もある。ひきもきらず新しい単語や表記が生まれる一方で、使われずに死語となる言葉もある。新しい言い回しが誕生するのと並行して、従来の言い回しは古臭くなり、やがて廃れる。したがって国民全員に普遍的に妥当する「完全な言語体系」というものはもともと存在しえない。せいぜいいえるとしたら、さまざまなレベルの共同主体のあいだで使われている言葉の最大公約数である。しかし最大公約数は計算対象となる整数が入れ替われば変化するように、言葉はそれぞれのレベルの共同主体のあいだで絶えず変化しているので、言葉の最大公約数も一定ではない。そのことは辞書や文法書がけっして一種類ではなく多数存在し、しかも続々と新しいものが誕生していることからも明らかである。
生物が地球上に発生して以来、遺伝的進化が連綿として続いているように、言葉は誕生して以来、かたときも休むことなく共同体を構成する個々の人間による学習と共有化によって継承されてきた。言葉はどの時点をとっても、それぞれの共同体において学習と共有化によって形成された成果である。言葉は学習によって個々の人間に拡散し、共有化によって共同主体に共有される。言葉の学習と共有化の過程は、いうなれば言葉の新陳代謝である。絶えず新しくなる言葉は言語共同体によって継承される。言葉は変化しないことによって存続するのではなく、つねに変化し続けることによって存続するのである。
1)幼児が驚くほど短期間で言語を習得することから、チョムスキーは人間は生まれつき「普遍文法」をもっていると仮定した。普遍文法は人類のすべての言語に共通する最も基本的な文法であり、どんな人間にも先天的に備わっているとされる。だが、文法は天からの授かりものではなく、現実の反映である。言語は進化の過程で生存環境の認識手段として誕生した。個別言語の文法が基本的な点で共通しているのは、認識構造がすべての人間に共通していることを反映した結果である。