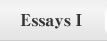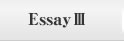第5章 時間論的視点
第3節 歴史
1.過去の証拠
これまでの考察で確認したように、主体の現在の体験は選別されて記銘され、過去の体験として記憶され、想起によって現在に再現される。しかし想起によって現在に再現された過去の体験は、想起という心の働きによって一時的に現在に存在するにすぎない。想起するのをやめれば想起された過去の体験もたちまち消滅する。想起を再開すると、同じ過去の体験が再び現在に呼び戻される。この一事からさえ記憶も想起も主体の心のなかでのみ起こるものであることは容易に納得できる。記憶するのも、記憶された内容を想起するのも、現在における心の働きである。記憶と想起という心の働きを少しでも反省してみるならば、それらはいずれも現在起きているということがまざまざと実感される。記憶も想起も現在における心の働きであることが実感されるにつれて、過去は過ぎ去ってもはや存在しないという確信が強まる。記憶された体験は過ぎ去った体験であり、想起されることにより既在性の存在様態で「すでにあった」ことと了解されて現在に存在する。記憶と想起は現在における生々しい心の働きをとおして現在の存在を確信させる。このように過去の存在を確かめようとして探求のまなざしを心の内に向けるならば、過去の存在は最終的に疑問の余地がないまでに否定されるのである。
だが、ひとたび探求のまなざしを心の内から心の外に転じるならば、過去の存在を証言する証拠はいたるところにある。過去のありとあらゆる事柄を記録した膨大な文書、過去のさまざまな情景を写し取った無数の写真、過去の事象を時系列的に記した歴史書や教科書など、どれひとつとっても過去は人間の心のなかできまぐれに想起されたものではなく、人間の外に歴史として厳然と存在することを雄弁に物語っている。過去の存在を証言する証拠は溢れんばかりにある。それらはどれも過去が存在することを抗いがたい説得力をもって主張する。過去の事象を記した文書や画像は一般に史料と呼ばれる。文字で書かれた文字史料をはじめとして、過去の事象や情景を写した絵画や写真や映像なども画像史料として史料に含まれる。史料は主体の体験や事象を記録した一次史料と、一次史料にもとづいて作成された二次史料に区別される。一次史料は基本的に主体が直接体験したことの記憶や観察した事柄を記録したものである。一次史料には過去の事象が直接的に、つまり当事者の体験や記憶や観察にもとづいて記録されている。これにたいして二次史料には過去の事象が間接的に、つまり一次史料にもとづいて記録されている。二次史料は主体が直接体験しておらず、一次史料を収集し整理もしくは集成したものである。
ここで過去の存在について考察するにあたって時間論的な視点から問われるのは、史料は過去の存在を証明するかということである。もし史料が過去の存在を証明すると結論づけるとしたら、その論拠となるのは、過去の事象を記録した文書や画像が存在する限り過去は存在するはずだというものである。つまり、史料が過去の事象を記録したものであるならば過去の事象は存在し、過去の事象が存在するならば過去は存在するという論理である。つきつめていえば、歴史がある以上、過去は存在するということだ。たしかに過去の事象を記録した膨大な史料が残されているのであるから、過去の事象は存在したといえるだろう。だが、過去の事象が存在したということと、過去が存在するということは同じではない。過去の事象が存在したというのは過去に属することであるが、過去が存在するというのは現在の事柄である。過去は文字どおり「過ぎ去った」のであるから、それが現在存在するということはありえない。せいぜい過去は存在したといえるだけである。同様に、過去の事象を記録するというのも正確ではない。過去は過ぎ去ったので、過去の事象を記録することは不可能である。記録するのは過去の事象ではなく、あくまでも現在の事象である。記録された現在の事象が過ぎ去って過去の事象になるのだ。記録された現在の事象が過去の事象となることによって歴史が生まれるのではないか。そうだとして過去の事象と歴史はどのような関係にあるのか。過去の事象そのものが歴史なのか、それとも過去の事象の記録が歴史なのか。過去の事象あるいは過去の事象の記録はどのようにして歴史となるのか。そもそも歴史とはなにか。このように見てくると、過去の存在を考察するにあたって歴史を避けてとおることはできない。歴史はいかなる時間論的懐疑も寄せつけないほど厳然と存在しているように思える一方で、「歴史とはなにか」というごくシンプルな問いにたいして同程度にシンプルな答えは用意されていないようだからである。
2.記憶と記録
準備的な定義として、記号とは、記号自体を指示するのではなく他のなんらかの事物を代理で指示するものである。たとえば信号機の赤が記号として指示するのは赤い色そのものではなく、歩行者が歩くのをやめて立ち止まり、車がその走行を停止することである。この場合、記号は特定の交通状況において人間が交通法規に従って取るべき行動を指示する。ただし、記号が交通法規を指示するものであるためには、記号が記号として受け止められなければならない。記号が記号として受け止められるとは、記号が指示するのは記号自体ではなく記号以外のものであると了解されることである。記号が記号として受け止められなければ、信号機の赤は赤い色のままにとどまる。さらに記号が記号として受け止められたうえで、記号は具体的になにを指示しているか解釈されなければならない。記号が具体的になにを指示しているか解釈されなければ、記号の指示機能は果たされない。信号機の赤は停止を表す交通信号であると解釈されて、はじめてそれは交通法規に従った行動を指示することができるのである。
史料そのものは文書や画像として現在に存在するが、史料に記録されているのは過去の事象である。それゆえ史料となる文書や画像は、史料それ自体を提示するのではなく過去の事象を指示する記号とみなすことができる。過去の事象を記録した文書や画像をおしなべて過去の記号と呼ぶことにする。過去の記号によって指示されるのは、過去の事象である。過去の記号によって指示される事象は共通して「すでにあった」という本質的特徴を備えている。過去の事象はすべて本質把握によって「すでにあった」ものとして了解される。「すでにあった」ものという了解は、「既に在った」ものとして既在性の了解という。既在性の了解には、「かつて存在した」、「かつて起きた」、「かつて発生したがいまはない」などの了解が包含される。過去の記号によって指示されるものは「すでにあった」という既在性において了解される。既在性において了解されるとは、既在性の存在様態で存在することである。過去の記号によって指示される事象は、既在性において了解される仕方で現在に存在する。
世界は不断に生成変化しており、その過程で限りなく膨大な事象が発生しては次の瞬間に消滅する。発生した膨大な事象の大部分は永久に消え去る。この不断に変転する膨大な事象のごく一部分が記号に変換されて保存される。事象が記号に変換されることを記号化と呼ぶ。記号化は、具体的には事象を文字で書き留めたり、画像に表現したりすることである。事象を記号化することによって保存する作業が記録である。現在の事象は記号化されることによって記録されて保存される。記録された事象は保存されることによって過去の事象となる。保存された過去の事象の記録は、史料として現在性の存在様態で、すなわち「いまある」ものとして了解される仕方で現在に存在する。これにたいして史料に記録された過去の事象は、既在性の存在様態で現在に存在する。過去の事象を記号化して記録した史料も、史料によって記号化された過去の事象も、それぞれの存在様態で現在に存在する。
主体の現在の体験が記憶されると、想起によって現在に再現される。しかし想起によって再現された主体の体験は一時的に現在に再現されるにすぎず、想起するのをやめれば想起された体験も消滅する。記憶も想起も主体の心のなかでのみ起こり、他人には知覚できない。これにたいして主体の現在の体験が記号化されると、他の主体によって知覚できるかたちで保存される。主体の体験は記号化されることにより、他の主体が知覚できる記録として保存されるので、当の主体が消滅しても消え去ることはない。事象が文字や画像によって記号化されたら、事象が消滅したあとでも文書や絵画として残る。保存された文書や絵画は現在性の存在様態で現在に存在する一方、文書や絵画に記録された事象は既在性の存在様態で現在に存在する。
過去に存在した人間も記号化されることによって記録として保存される。記録として保存されることによって、過去の人間は不断に現在へと送り込まれる。歴史上の登場人物、たとえば織田信長に関する記録は、生前から公的な文書や私的な書簡や第三者による報告など数多く存在した。それらは信長と同時代に記録された一次史料に分類される。一次史料が作られたのは信長と同時代におけるそのつどの現在である。信長の死後は、一次史料にもとづいて『信長公記』をはじめとする伝記や軍記物が次々と生み出された。これらの記録は二次史料に分類される。二次史料が生み出されるのは、信長の死後におけるそのつどの現在である。一次史料であれ二次史料であれ記号化されるたびに信長は現在へと送り込まれ、既在性の存在様態で現在に存在し続ける。
保存されている過去の事象の記録は、現在における人間の体験を記号化することが出発点である。体験とは人間が経験の地盤で主体として客体と関わることである。主体が体験した事象を記号化することによって事象は記録される。記録されて保存されたすべての事象に人間が関与している。この場合、人間が主体として事象と関わり、したがって当事者がその体験を記憶しているケースもあれば、他の人間が主体として関与した事象を第三者が観察して記録に残すケースもある。主体が体験した事象の記憶と、主体の体験が記号化された記録、あるいは主体以外の人間の体験が記号化された記録との関係は、典型的に次のようなケースが想定される。
(1)主体の体験が記号化されて記録として保存されるケース
家族で沖縄に旅行に行き記念撮影をする。旅行から帰って写真を見ると、主体の体験が直接想起によって頭のなかに再現される。この場合は、想起された体験の内容と、写真によって記号化された体験の記録が一致している。
(2)変容した体験の記憶が記号によって修正されるケース
子供の頃、家族だけで東京デズニーランドに行ったと思っていたが、後年写真を見て友人の家族も一緒だったことを思い出す。この場合は、想起された主体の体験に、記号化された過去の体験が重ねられて、記憶された体験の内容が修正される。
(3)失われた記憶が記号によって呼び覚まされるケース
箪笥の奥から出てきた昔の写真をはじめて見たとき、最初はなんの写真かわからなかったが、見ているうちに記憶が徐々によみがえる。幼いころの自分の顔や、かすかに覚えている友人の顔や、背景の様子から小学校のときの運動会の写真であろうと推定する。運動会は本人が主体として体験したことであり、その体験がおぼろげながら想起される。この場合は、本人が体験を直接想起するのではなく、過去の事象を指示する記号のうえに主体の体験の記憶が投影されて過去の体験が再現される。
(4)主体が体験していない事象が記号化されて記録として保存されるケース
第二次大戦中に撮られた運動会の写真は、本人が体験していない過去の事象を指示する。軍事教練色の強い競技種目や服装などから解釈して戦争中の運動会の模様を撮影したものであると推定される。運動会に参加したのは過去に存在した主体であり、写真を見ている本人は主体としてこの事象に関与していない。そのため過去の事象を指示する記号のうえに本人の体験の記憶が投影されることはない。それゆえいかなる形でも想起という意識作用は起こらない。この場合は、過去の主体が体験して記号化された事象が、現在の主体によって仮想的に追体験される。
これらのケースから記憶と記録を対比してそれぞれの特徴を際立たせるならば、記憶によって再現されるのは記憶する主体の体験であり、記録によって再現されるのは現在の主体の体験であるか過去の主体の体験であるかを問わず過去の事象である。主体が体験することは記憶に保存され、想起によって現在に再現されるが、記憶された体験は当人が忘却すれば消滅し、当人が死ねばそれを想起する可能性は完全に消え失せる。これにたいして記録された事象は記号として保存され、事象自体が消滅し、あるいは事象を記録した主体が死んだあとも残る。記憶の場合は主体の体験が想起されることによって現在に再現されるのにたいし、記録の場合は過去の事象が記号で指示されることによって現在に再現される。いずれも現在に再現されることに違いはないが、記憶の場合は主体が体験したことが<記銘-記憶-想起>のプロセスを経て再現される。この場合、再現された記憶の内容には直接「すでにあった」という既在性の了解が伴っている。このプロセスは終始主体の頭のなかで進行し、再現された結果も主体の頭のなかにのみあり、主体以外の人間は覗き見ることができない。他方、過去の事象の記録は、記号化されて人間の外に存在する。記憶が想起によって個人の頭のなかで再現されるのにたいし、記録は記号として現前しており、そのため体験した当事者以外の人間も知覚することができる。しかし記号が過去の事象を指示する記号として機能しえるためには、最初に去の事象を指示するものとして受け止めらなければならない。記号がそのようなものとして受け止められなければ、記号は記号のままで事象の記録とはなりえない。しかも記号そのものが特定の過去の事象を指示する機能を備えているわけではないので、具体的にいかなる過去の事象を指示するかを記号自体から特定することはできない。そのため記号を知覚する者は最初に記号を記号として受け止め、さらにその記号が具体的になにを指示しているか解釈しなければならない。解釈の結果、記号はなんらかの特定の過去の事象を指示していると把握される。それゆえ記録の場合は、過去の事象は<知覚-解釈-把握>のプロセスを経て現在に再現される。
3.事象の記録
主体の体験は記号に変換されることによって保存される。主体が体験したことの一部は記憶に保存され想起によって再現されるが、記憶に保存された過去の体験は主体の頭のなかで変容し、薄れ、あるいは完全に忘れ去られる。それにたいして記号によって保存された過去の事象はそうした変容をこうむらない。もちろん写真などの物理的な記録媒体が時間の経過とともに変色したり劣化したりすることはあるし、破棄や焼失によって物理的に消滅することもある。しかし記号化された事象は個人の記憶に比べればはるかに長期にわたって保存される。記憶に意図的な記銘と非意図的な記銘があるのに対応して、記録にも意図的な記録と非意図的な記録がある。意図的な記録とは、なんらかの事象を事実として残すことを意図して記号化することである。意図的に記録することにより、同時代に発生した事象を事実として後世に伝えることができる。この場合、記録された事象が「史実」であるか否かは問わない。確かなのは、ある事象を事実として残そうとする記録者の意図のみである。したがって記録者の作為が介在する余地もおおいにある。他方、非意図的な記録とは、発生した事象を事実として後世に残すことを意図したわけではないが、結果として後世の視点から意図的な記録と同等もしくはそれ以上の証言効果をもつことがある。
事象を意図的に記録する手段はさまざまあるが、その筆頭にあげられるのは言葉である。言葉は文字または音声によって表現されるが、音声を保存する術がなかった時代には、口伝を除けば文字が記録媒体であった。文字自体は直接過去の事象を指示しない。文字は概念を伝達し、伝達された概念が過去の事象を指示するのである。文字は、文字によって伝達される内容を素材的に構成しない。つまり文字は太字であろうと細字であろうと、黒字であろうと赤字であろうと、明朝体であろうとゴシック体であろうと、文字によって伝達される概念の内容には影響しない。この点で文字は抽象的である。文字はその抽象性のゆえに具体的な事物から観念的な思想まで幅広く表現できる。そのため文字を使って古文書から、日記、伝記、回想録、史書、歴史小説、新聞、書簡、備忘録にいたるまで、まさしく森羅万象が文字で記録された。その結果、膨大な過去の事象が文字に書き留められ、文字史料として現在に保存されている。
文字が抽象的な記録媒体であるのにたいし、画像は具象的な記録媒体である。なぜなら画像は、記録する媒体であると同時に、表現される素材でもあるからである。文字と違って媒体の色や形は表現される内容を構成する。画像を意図的な記録の手段として最大限に活用したジャンルは歴史画である。歴史画は過去に起きた事象を現在に再現することを目的としたものと、同時代の事象を記録して後世に残すことを目的としたものがある。フランス新古典主義の画家ジャック=ルイ・ダヴィッドの作品で見れば、過去の事象を再現した油彩画として1787年に描いた『ソクラテスの死』がある。過去の事象を再現したといっても、プラトンの『パイドン』に登場する場面を画家が想像力によって脚色したものであり、いうまでもなくこれが史実である保証はまったくない。同時代の事象の記録の例としては、同じくダヴィッドが1804年に描いた『ナポレオン一世の戴冠式と皇妃ジョゼフィーヌの戴冠』があげられる。パリのノートルダム大聖堂を舞台として、ナポレオンはじめ妻のジョゼフィーヌや時の教皇ピウス七世、各国大使など多数の人物が登場する。高さ約6メートル、幅約10メートルの大画面に描かれている200人近い人物は、ナポレオンの招待を受けて出席しているので全員名前を特定できるという。それ以外にも当時不仲だったために出席していなかったナポレオンの母親と兄に加えて、他界した甥まで描きこまれている。したがってこの絵は史実を正確に反映した記録というより、ナポレオンの権勢を後世に伝える意図で描かれた創作にちかい。
歴史画以外にも記録を目的としたジャンルもある。たとえば静物画のなかには17世紀オランダに始まる狩猟画というジャンルがあり、裕福な市民や貴族が狩猟の成果を記録することを目的として制作させた。あるいはヨーロッパの王侯貴族は自分たちの威容を後世に伝えるために宮廷画家を雇って肖像画を描かせた。そうした例はあるものの、静物画や肖像画や風景画などは基本的に記録を目的としていない。といっても画面にそれぞれの時代背景が描き込まれることにより、意図せず事象の記録となりうる。たとえばフランドルの画家ピーテル・ブリューゲルが1565年に描いた『雪中の狩人』は同時代の風景描写を目的として、画面には猟犬を引き連れて戻ってくる狩人、冬に備えて屠殺した豚の毛を焼く男女、凍った池のうえでスケートやコマ回しに興じる子供たちなどが細かく描きこまれている。近景の狩人から中景の子供たち、そして遠景に配された豆粒のような人物にいたるまで全員が無名である点で、ダヴィッドの『ソクラテス』や『戴冠式』とはまさに対照的であるが、写真がなかった16世紀オランダの農民の生活の克明な記録となっている。
19世紀になってフランスで新しい記録媒体として写真が登場すると、そのときどきの事象をよりリアルに写し取ることが可能となった。それによって写真はそれまで絵画がになっていた記録の役割を肩代わりすることになる。その余波を受けて多くの画家が失職する一方で、ナダールのように画家から写真家に転身する者も現れた。他方、絵画はクロード・モネが1873年に発表した『印象・日の出』を転機に、意識的に写実性から離脱する方向へと進んだ。「印象」という言葉は当時の美術評論家にとっては蔑称にすぎなかったが、モネにとっては主観性の宣言であった。写実性の呪縛から解き放たれた絵画は、その後印象主義、フォービズム、キュービズム、抽象表現主義などへと展開して近代絵画の百花繚乱をもたらした。
19世紀末に映画が誕生して、再現のリアリティーが格段に増した。当初は音声のないサイレント映画だったが、1920年代に音声を入れたトーキーが登場した。さらに1930年代にそれまでのモノクロ映画に代わってカラー映画が上映されるようになった。映像のもつ卓越したリアリティーのために、最初期から記録を目的とするドキュメンタリー映画が作られた。しかしドキュメンタリー映画は必ずしも事象の客観的な記録ではない。そもそもなにを記録するかを選択する時点で製作者の主観が介入する。さらにそれをどのような視点から記録するかということになると、製作者の思想に決定的に左右される。たとえば1925年にセルゲイ・エイゼンシュテイン監督によって製作された「戦艦ポチョムキン」は記録映画の体裁をとってはいるが、内容的には共産主義のプロパガンダ映画である。その一方で、直接記録を目的としないフィクション映画でも、登場人物やそれを取り巻く時代背景などがそのときどきの事象を伝えることによって記録の役割を果たす。たとえば1953年に公開されたグレゴリー・ペックとオードリー・ヘプバーン主演の「ローマの休日」は、某国の王女がローマに駐在しているアメリカ人記者と恋に陥るという架空の話だが、ロケ地となった1950年代のローマの遺跡や街の情景をリアルに伝えている。
文字、絵画、写真、映像などの記録媒体によって記録された過去の事象は既在性に属する。つまりそれらの記号によって指示された過去の事象は、既在性の存在様態で存在する。記録された過去の事象は「すでにあった」ものとして了解されている。この場合、記号そのものは「いまある」という現在性の存在様態で現在に存在するが、その記号によって指示される事象は「すでにあった」という既在性の存在様態で現在に存在する。「未来」という言葉で了解されているものが未在性の存在様態であったように、「過去」という言葉で了解されているものは既在性の存在様態である。既在性の存在様態とは、「いまある」こととしての現在および「まだない」こととしての未来の了解と相互参照され、これらとの対比において成立する「すでにあった」ことの了解である。この了解を離れて過去そのもの、すなわち実体的な過去が存在するかのように思念するのは空想でしかない。なぜなら過去は体験として記憶に保存されるか、それとも記録として記号化されるかのいずれかによってしか存在しえないが、記憶も記号も現在にのみ存在するからである。
文字は抽象的な記録媒体として、画像は具象的な記録媒体として過去の事象を指示する。たとえば紫式部が書いた「源氏物語」は平安時代の貴族社会という過去の事象を概念を介して指示する。この物語を題材にして作成された「源氏物語絵巻」は物語本文から抜粋した詞書を画像化したもので過去の事象を色と形で直接指示する。文字と画像という記録媒体と過去の事象は、指示するものと指示されるものの関係にある。文字や画像を記録媒体と呼ぶのにたいして、建造物や工芸品など、それ自体において過去の事象が現前している事物を歴史的事物と呼ぶ。たとえば平等院鳳凰堂は約千年におよぶ年月を経て現在あるがままの現物として存在している。記録媒体と異なり歴史的事物の場合は、現物と過去の事象は指示するものと指示されるものの関係にはなく両者一体となっている。抽象的な記録媒体である文字と、具象的な記録媒体である画像と、現物としての歴史的事物は、それぞれ過去の現れ方に違いはあるが、いずれも現在性の存在様態で存在する。文字と画像の記録媒体によって指示される過去の事象は、既在性の存在様態で現在に存在する。現物において現示される過去の事象は、現在性の存在様態に既在性の存在様態が重なって現在に存在する。
存在する事物はすべて潜在的に歴史的事物でありえる。なぜなら自動車であれ家具であれ食器であれ、すべての事物がそれぞれ誕生するまでの「前史」をもっているからである。机の上にある本の成立の因果連関をたどればはてしなく過去にさかのぼることができるように、どんな事物も過去のさまざまな事象の因果連関から成立している。しかし事物そのものに「源氏物語」や「源氏物語絵巻」のように特定の過去の事象を指示する機能があるわけではない。事物を歴史的事物として把握するためには、最初に事物が過去の事象を指示する記号として受け止められなければならない。そもなければ事物は事物そのものとして完結し、過去の記号として働かない。事物が過去の記号として働くためには、それを知覚する側が事物をそのようなものとして把握しなければならない。そのためには事物を特定の過去の記号として解釈する必要がある。たとえば屏風に南蛮船や荷揚げされた貿易品や宣教師の一行が描かれているのを見て、その絵は南蛮貿易を記録したものであると解釈する。それによって屏風は、安土桃山時代に製作された南蛮屏風であると判断されて歴史的事物となる。
屏風に南蛮貿易の様子が描かれている例のように、現存する歴史的事物には過去の事象が現前している。これにたいして遺跡の場合は、その現存する姿において過去の事象が欠如している。むしろ遺跡はその欠如において過去の事象を指示する。墳墓の遺跡は、石と穴のほかにはなにもない空間が、いまはないが「かつてあった」ものを指示する記号である。土木工事で掘削した土のなかに人工的な石片が混じっていたら、それらはなんらかの歴史的事物の一部である可能性がある。だが、土木作業員が発見した時点で石片は過去の事象を指示する記号として受け止められていない。石片がそのような記号として受け止められるためには、考古学的関心の対象とならなければならない。考古学者が調査した結果、石片は約三千年前に作られた縄文土器の破片であると解釈されたとする。工事現場から掘り出された石片は、考古学者の関心の対象となることによってはじめて過去の記号となる。その結果、石片は考古学者の調査と研究を経て歴史的事物とみなされる。
4.コンテクスト
過去の記号が過去の記号として受け止められて特定の過去の事象を指示するためには、最初にそれらの記号が人間の関心の網に捕捉されなければならない。人間の関心の網に捕捉されるとは、記号が関心の視点から把えられて互いに関連づけられることである。記号を捕捉する関心の網をコンテクストと呼ぶ。コンテクストは、過去の事象を指示する記号を現在の人間の関心の視点から関連づけてまとめたものである。コンテクストはそのつどの現在の人間の関心の視点から構成される。したがってコンテクストは永続的に固定されたものではなく、そのつどの現在の人間の関心に応じて変化する。過去に構成されたコンテクストが、現在の人間の関心に照らして無視され、やがて忘れ去られて消滅することもあれば、逆に忘れられていたコンテクストが現在の人間の視点から光が当てられてよみがえることもある。いずれのコンテクストも現在の人間の関心が動機となって構成されている。
ココンテクストはさまざまな過去の記号が因果的あるいは内容的に関連づけられることによって成り立っており、どの記号をどのように関連づけるかによって多種多様なコンテクストが生まれる。関連づけの仕方が変わればコンテクストも変化する。新しい記号が既存のコンテクストに組み入れられればコンテクストの内容が更新される。更新とは、コンテクストが新しい記号をみずからのうちに組み入れ、あるいはそれと入れ替えに古い記号を無効化するなどして、それ自体において新しくなることである。が、どれほど新しいコンテクストが生まれようと、既存のコンテクストと無関係であることはできない。新しいコンテクストはつねに既存のコンテクストとつながりながら、新しい内容を獲得する。既存のコンテクストとつながりのないところに、まったく新しいコンテクストが生じることはありえない。コンテクストは絶えず新しく生み出されるが、そのすべてがなんらかのかたちで既存のコンテクストと関連している。いかなるコンテクストも既存のコンテクストとの関連なしには成立しない。それは過去の事象を指示する記号を関連づけたコンテクストは、もともと人間の関心の網として成立しているからである。記号は人間の関心の網に捕捉されて、はじめて過去の記号となる。網の目が一つだけ独立して存在することはできないように、関心の網の目は次々と触手を伸ばして拡大する。関心の網は、およそ人間の関心がおよぶ限り、すべての事象の範囲を覆っている。
すでに指摘したように、記号が過去の事象を指示するためには、記号が記号として受け止められ、特定の過去の事象を指示するものとして解釈されなければならない。記号が特定の過去の事象を指示するものとして解釈されるとは、記号がコンテクストに組み入れられるということである。ある記号が過去の事象を指示するか判断するには、既存のコンテクストを参照しなければならない。。記号は既存のコンテクストを構成している記号と関連づけることができる場合に、はじめて過去の事象を指示する記号としてそのコンテクストに組み入れられる。たとえば新たに発見された古い書簡に朱印が押してあり、印面文字が「天下布武」と読めるところから、この書簡は「織田信長」のコンテクストを構成する朱印状と関連づけられ、過去の記号としてコンテクストに組み入れられる。
歴史的事物はそれ自体において過去の事象が現前しているが、直接特定の過去の事象を指示することはできない。歴史的事物に現前しているものが過去の事象を指示する記号として働くには、具体的にいかなる過去の事象を指示しているか解釈されることが必要である。そのためには事物そのものが記号としてコンテクストに組み入れられなければならない。現存する平等院鳳凰堂がそれ自体において過去の事象を現示することができるのは、「平安時代」のコンテクストにおかれて「平安時代に建立された建造物」として解釈されることによってである。
歴史的事物が現物としてそれ自体で過去を現示するのにたいして、文字は抽象的な記録媒体として概念を伝達する。伝達された概念は、コンテクストに組み入れられて特定の過去の事象を指示する。たとえば「ビロード」という言葉は、素材としてはパイルを織り出した織物を意味するが、これを服飾のコンテクストにおくとドレスの素材を指し、内装のコンテクストで見ればカーテンの素材を指す。ビロードを「南蛮貿易」のコンテクストにおけば、16世紀にポルトガル人によって日本に持ち込まれた文物のひとつである。南蛮貿易というコンテクストのキーワードをなす「南蛮」という言葉は、もともと中華思想の視点から南方の未開民族を指した呼称である。この中華思想の視点に立ちながら、これに16世紀の日本人の視点が加わって、南方より船で日本にわたってきたポルトガル人やスペイン人を南蛮人と呼ぶようになった。南蛮人の渡来は1543年ポルトガル船の種子島漂着にはじまり、1639年南蛮船の入港禁止令によって幕を閉じる。後世の歴史家はこの約100年間を「南蛮時代」としてくくり、その視点からポルトガル、スペインをはじめとする西洋諸国とのあいだでおこなわれた貿易を「南蛮貿易」と呼んだ。また貿易商や宣教師によって伝えられたキリスト教を中心とする文化を「南蛮文化」と称した。このように南蛮文化は、もともと中華思想の視点から出発して、16世紀の日本人の視点におきかえられ、さらに後世の歴史家の視点から構成されたコンテクストである。
南蛮文化というコンテクストは、それと並行して起こった安土桃山文化のコンテクストと密接に関連している。安土桃山文化は、織田信長と豊臣秀吉が天下統一に邁進した安土桃山時代の文化を意味する。安土時代という呼称は、1579年信長が琵琶湖畔の安土に築いた城に由来する。安土城は築城後わずか数年で焼失したが、残された史料から前例を見ない絢爛豪華な城であったことが推測され、信長の権勢を象徴するものとしてその名をとって安土時代と称した。もちろん安土城が焼失したことも、みずからの治世が安土時代と呼ばれていることも信長自身のあずかり知らぬことである。他方、桃山時代の呼称は、秀吉が晩年に伏見に築いた城の跡地に桃の木が植えられたことに由来する。しかし伏見城内で没した秀吉本人にしてみれば、その死後まもなくして伏見城が廃城となったことや、その跡地に多数の桃の木が植えられて桃山と呼ばれたことや、そこからひるがえって自身の治世が「桃山時代」と呼ばれるようになったことは知るよしもない。安土時代も桃山時代も後世の史家の視点で構成されたコンテクストにもとづく時代区分である。
人間はだれしも自分が生まれる前の歴史には主体として関与しておらず、したがってそれについての記憶ももっていない。その場合、人間は過去の歴史を所与として受け入れるしかない。しかし歴史そのものは人間の関与なくして形成されない。歴史の発生源は主体としての人間と客体としての現実の関りの体験であり、歴史の成立は過去における無数の主体の存在を前提としている。歴史が生まれるためには過去に存在した人間が主体として歴史の形成に関与していなければならない。歴史の発生源は、人間がそれぞれの時代で主体として客体と関わる体験である。この場合、客体とは同時代における他の人間や事物とそれらの相互の関係、すなわち主体を取り巻く環境と、その環境において主体が直面する現実である。主体としての人間が客体としての現実と関わるところに出来事が生じる。出来事は主体によって体験される。主体によって体験されない出来事はありえない。しかし過去に生きた無数の主体がそれぞれの現在で客体としての現実と関わることが、そのまま歴史になるのではない。これら無数の主体の体験が歴史になるためには、最初にそれらの体験が記号化される必要がある。つまり体験が文字や画像や映像などの記号に変換されなければならない。過去に存在した無数の人間によってどれほど多くの体験が積み重ねられようと、記号化されない限りそれらが歴史の舞台に登場することはない。主体が体験した出来事がすべて記録されるわけではないが、当然のことながら主体が体験しない出来事は記録されない。出来事を記録した文書なり過去の記号となり史料として既存のコンテクストに組み入れられことによって、出来事は歴史的な出来事となるのである。
過去の人間の体験が歴史となるための前提は、なによりもその体験が記号化されることであるが、人類が生まれてこのかた想像を絶するほど膨大な体験が記号化されることなく永久に消滅した。人類が積み重ねてきた膨大な体験のうちで記号化されたものはごく一部にすぎない。しかもそれらの記号の多くは火災や戦争、地震や洪水などの自然災害、焚書や偶像破壊など人為的な破棄も含め、ありとあらゆる原因で消失したり毀損したりした。それゆえ現在まで残されている記号は、まさに奇跡といってもいいほどに稀少である。しかしまた、記号化された体験が史料となるためには記録として現在に送り届けられなければならない。記録は現在に届き、そして現在の人間の目に留まってはじめてその存在を得る。未発見の古文書のように、たとえ記号化されてどこかの蔵の奥に保存されていようとも、現在の人間がそれを見つけなければ存在しないに等しい。過去の人間の体験が記号化され、幸運にも戦火や自然災害や人為的破棄を免れて現在まで残っている記録だけが史料となるのである。だが、史料がただちに歴史を形成するかといえば、そうではない。歴史を形成するためには史料は現在においてコンテクストに組み入れられなければならない。史料から歴史が成立するためには現在の人間が史料を検証し、そこに散らばるおびただしい数の記号を集めて互いに論理的に関連づけることが必要である。記号は特定のコンテクストのもとで互いに関連づけられて整合性をもったまとまりとなるる。既存のコンテクストは無数に存在しており、その大部分は伝承されるが、消滅するものもある。それと同時に絶えず新しいコンテクストが生み出される。過去の事象を指示する記号は、文字や画像や映像など多種多様な媒体によって数限りなく生み出されている。それに伴って歴史を織りなすコンテクストも増え続け、膨張する宇宙さながらに拡大の一途をたどっている。
5.歴史の定義
過去の記号は現在に存在し、記号の集合であるコンテクストも現在に存在する。記号はなんらかのコンテクストのなかで互いに関連づけられることによって、過去の事象を指示するものとなる。記号はコンテクストに組み入れられることによって、そのコンテクストを構成している他の記号と関連づけられる。逆にいうと、記号はコンテクストを構成している記号と関連づけられることによって、そのコンテクストに取り込まれる。たとえば「鉄砲」という言葉は銃身を有する火器を意味するが、「種子島」という記号と関連づけられて「南蛮貿易」のコンテクストに組み入れられる。その結果、「鉄砲」という言葉は過去の事象を指示する記号となるのである。
この世界に過去の記号は無数にあり、それらの記号を関連づけて組み合わせたコンテクストも無数に存在する。コンテクストは人間の関心の網によって構成されており、多種多様なコンテクストのどれも孤立しては存在しない。コンテクストのなかで記号が互いに関連づけられているように、コンテクスト同士も相互に関連しあう。コンテクストの時系列的な関連を通時的関連と呼ぶ。過去の事象を通時的に関連するコンテクストで総括すれば時代区分となる。安土桃山時代のコンテクストは、それに先立つ戦国時代やそのあとに続く江戸時代のコンテクストとも因果的に関連している。さらに戦国時代のコンテクストは、それに先行する室町時代、鎌倉時代、平安時代などのコンテクストとも密接に関連している。同様に江戸時代のコンテクストは、後続の幕末や明治時代のコンテクストと関連している。コンテクストを時系列的にたどれば太古から現代まで連綿とつながっている。
しかしまたコンテクストは同時代においても主題的に関連している。主題は政治、社会、経済、文化をはじめ、およそ人間の生活に関わるあらゆるジャンルにわたる。たとえば南蛮文化は、政治的には幕府や各藩の外交政策、経済的には南蛮貿易、学術的には医学、天文学、地理学、宗教的にはカトリック、技術製品としては鉄砲、火薬、眼鏡、時計、ビードロ、食品としてはパン、ジャガイモ、カステラ、ワイン、衣料としては生糸、絹織物、ビロードなどおびただしい数の主題を包含している。南蛮貿易によって日本に持ち込まれた文物の伝来経路をたどればスペイン、ポルトガル、オランダ、イタリア、さらには中国、東南アジア、アメリカ大陸など世界中とつながる。このようなコンテクストの主題的な関連を共時的関連と呼ぶ。過去の事象を共時的に関連するコンテクストで総括すればジャンルとなり、それぞれのジャンルは無数の主題に細分化できる。
ここで、歴史を通時的および共時的に関連するコンテクストと定義する。コンテクストはすべて互いに通時的および共時的に関連している。コンテクストは現在の人間の関心の視点から関連づけた過去の事象である。過去の事象を通時的に関連するコンテクストで総括することによって、共同体の歴史は、それぞれ本質的特徴を備えた時代に区分される。各時代はさらに前期・中期・後期・末期などと細分化される。この場合、歴史はそれぞれの時代の歴史すなわち時代史である。時代史は、それぞれ共時的に関連するさまざまな主題を内容としている。主題が時代史の内容を形づくっており、主題的な内容がないところに時代史は成立しない。
過去の事象を共時的に関連するコンテクストで総括することによってジャンルが生じる。それぞれのジャンルは無数の主題に細分化できる。この場合、歴史はそれぞれの主題の歴史すなわち主題史である。すべての事象は過去の事象の因果的な帰結として成立するので、いかなる事物もそれぞれの前史をもっている。共時的につながりのある主題は、それぞれが時系列的な関連を有する。時系列的な関連のないところにいかなる事象も成立せず、したがって主題のコンテクストも存在しえない。生糸や鉄砲は南蛮貿易によって日本に輸入された産品として、共時的な主題として南蛮貿易のコンテクストに組み入れられる。しかし生糸には生糸の歴史があり、鉄砲には鉄砲の歴史があって主題そのものが成立する。コンテクストはどれ一つとっても通時的であると同時に共時的である。このように概観すると、すべての時代史と主題史を包括した「歴史全体」というものを想定する誘惑にかられる。この想定のもとでは、歴史は通時的および共時的に関連するコンテクストの総体として存在することが前提とされる。しかし、歴史全体というものは理念としてしか存在しない。それは、あらゆる構成要素の総体として定義された世界は理念として想定することはできても、具体的に認識も体験もできないのと同じである。
世界の範囲と内容が人間が現実に生きて活動する共同体に規定されたように、歴史の範囲と内容も共同体によって規定される。共同体は、共同性を生来の特性とする人間が生きて活動する場である。人間は生まれてから死ぬまでさまざまな共同体に属し、共同体の成員すなわち共同主体として生きる。人間は共同主体としてそのつど属する共同体において客体と関わる。共同主体と客体との関わりは個々の主体によって体験として記憶され、それと並行して事象として記録される。記録は基本的に共同主体間の情報の共有化を目的としており、共同主体の行為である。つまり他の共同体の成員に情報を伝える役割を担う共同主体(公務員、報道人、研究者、歴史家など)としての行為である。共同主体によって記録された事象は、後世の共同主体により過去の記号として既存のコンテクストに組み入れられて歴史となる。歴史はいずれかの共同体において共同主体によって形成される。それゆえ歴史は本質的に共同体史である。
共同体史を形成するのは共同主体であり、共同主体は共同体の成員として見られた限りの主体である。個々の主体は共同体史をもつと同時に、それぞれ個人史をもっている。個人史は、そのときどきの共同体のなかで累積された個々の主体の体験の軌跡である。個々の主体が誕生してから現在にいたるまで積み重ねてきた体験を俯瞰するとき個人史が生まれる。個人史は個人がこの世界に生まれて以来積み重ねてきた体験の軌跡であり、したがって唯一無二である。この唯一無二の歴史から、おのずとこれから進むべき人生の軌道が開ける。その軌道は、これまでの人生がそれに向かって進んできた目的に向かって続いている。人間が自分の過去に関心をもつのは、根本的に自己認識が動機となっている。自分の過去の人生を総括することによって現在における自分を把握し、これからの行く末を見定めようとする。人間の過去への関心は、本質的に自己認識の欲求である。個人史という唯一無二の歴史を他の人間と共有しようとするところに文学をはじめとする芸術が生まれる。芸術は個人史の表現であり、芸術活動は個人史を他の人間と共有するための作業である。
個人史が個々の人間の歴史であるのにたいして、共同体史は共同体の成員としての歴史である。この世界に生まれた人間は生涯を通じてさまざまな共同体に属し、そのつど共同主体として活動して共同体史の形成に関与する。ただし、共同主体として共通の事象に関与しても、関与のしかたはそれぞれの主体によって異なる。主体によって事象に関与する強度や姿勢が異なれば、その結果生じる体験も異なる。事象の見方や解釈も、個々の主体の視点や立場に応じてさまざまである。それゆえ共同体史と個人史が一致することはありえない。
共同体史はそれぞれの共同体に属する人間の関心の視点から構成される。共同体史のコンテクストは基本的に時系列的なコンテクストと共時的なコンテクストからなり、それぞれ現在の人間の関心の視点で無数の過去の記号から構成される。過去の事象を互いに関連するコンテクストに再編しようとするのは、共同体を構成する個々の人間の過去への関心が動機である。個々の人間は主体としては自分の過去の人生に関心をもつが、共同主体としては自分がこの世界に誕生する以前の過去にも関心をもつ。この過去への関心は、知的興味やノスタルジーの枠におさまるものではない。人間が共同主体として個々の主体の出生よりはるか以前の過去を振り返る動機は、共同体としての自己認識への欲求である。共同体は存続するために自己認識を必要とし、自己認識を確立するために過去を振り返る。共同体として自己認識を得るために共同体が誕生して以来の過去を回顧し、現在の状況を認識し、未来を予見する。このとき共同体がみずからに投げかける問いは、「我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのか」1)という言葉に集約することができる。共同体史として具現化する歴史は、この問いにたいするそのつどの現在における共同体の答えにほかならない。
6.歴史の変容
鳳凰堂は平安時代中期に藤原道長の長男頼通によって1052年に創建された平等院の一部である。当初平等院は本堂をはじめ多数の堂塔からなら大伽藍であったが、その後の戦乱や災害ですべて焼失し、鳳凰堂のみが奇跡的に残った。鳳凰堂は周囲の池とともに西方極楽浄土をこの世に現出しようとする意図で建立された。内部には阿弥陀如来坐像を本尊として多数の菩薩像が配置され、壁面には九品来迎図が描かれるなど、極楽浄土を観想できるように設計された。平等院はその後、源平合戦、元弘の乱、山城国一揆などの舞台となりながらも存続したが、江戸末期にひどく荒廃した。そのため明治以降何度か改修が重ねられ、近年「平成の大改修」がおこなわれた。このときできるだけ創建当時の姿に近づけるという京都府の改修方針をめぐって、「忠実に復元するのは当然」という賛成意見と、「古色をそのまま残すべき」という反対意見にわかれた。この議論の本質は、千年前の過去の事象を指示する記号として、いずれが「史実」を反映した記号たりえるかということにある。とはいえもとより「史実」の客観的基準があるわけではない。あるのはこの記号が組み入れられるべきコンテクストの相違である。この相違はコンテクストを構成する人間の関心の視点の違いからきている。賛成派の方は極楽浄土をこの世に再現するために極彩色で施工されたという共時的関連を重視するのにたいし、反対派は建立されてから千年の歳月が経過したという通時的関連に重きをおく。いずれの見方に立つにせよ、これは千年前の過去の事象を指示する記号が現在の人間の関心の視点によって変容される一例である。
古墳や住居跡といった古代の遺蹟のように史料に乏しい歴史的事物の場合、その場所に関するさまざまな言い伝えによってコンテクストを作る。しかし言い伝えはあてにならず、なんらかの文献資料があったとしてもほんの数語言及されているだけで、異なる解釈を許すものもあれば、その証言自体が事実ではないこともある。そのため言い伝えを導きの糸に、既存のコンテクストとして関連する文献資料と照合しながら出土品を緻密に分析することになる。想像力を最大限に働かせた考証によって新しいコンテクストが作られる。その後、調査が進んで新資料や出土品が出たら、それらは過去の事象を指示する記号として既存のコンテクストに組み入れられる。新たに発見された記号が既存のコンテクストを構成する記号と関連づけられることによって、コンテクストの内容はより豊富なものとなっていく。その一方で、あらたな資料の発見や考証の進展の結果、古墳の成立年や被葬者などの事項に関する従来の推定が覆ることもある。その場合は既存のコンテクストは適宜修正される。発見された資料が既存のコンテクストを固定から覆すような証言力を持っている場合は、既存のコンテクストが棄却されて、それに代わってまった新しいコンテクストが作られる。このようにコンテクストは伝承されるともに、絶えず書き加えられ、修正され、ときには完全に書き換えられる。それによってコンテクストの総体としての歴史は不断に変容する。
過去の記号として保存されている史料が、過去に起きた事象を正確に記録していると単純に断定することはできない。その最も単純な理由は、それらの史料が偽造もしくは改竄されたものであるかもしれないからである。しかし、たとえ真正な記録であっても記録者の主観的な判断や嗜好が介在することも避けられない。正確な記録を意図しながら予期しない錯誤が含まれている可能性もある。いずれの場合も厳密な史料批判によって真偽が判定されなければならない。史料が過去の事象を正確に反映しているとはいえない理由として、史料批判がおよばない理由もある。それは認識論的理由ともいうべきもので、人間にはもともと事象全体を見通すことができないのである。コンテクストは人間の関心の視点から関連づけられた一連の記号である。人間の関心の視点から広がる視界をパースペクティヴという。パースペクティヴは関心の視点を起点とする個々の人間の認識の視界である。対象を知覚するときにつねに身体に規定された視点から見るように、事象を認識する場合もそれぞれの人間固有のパースペクティヴから見る。事象は人間のパースペクティヴに応じてそれぞれ異なる側面を見せる。したがって事象はその全体ではなく、特定の視点から見られた側面だけが認識される。だが、これは人間の認識能力の限界というべきものではない。むしろそれは認識が成立するための根本的な条件である。なぜなら認識の視界のないところに事象の認識はありえないからである。人間の認識(神の認識ではなく)が問題である限り、事象は認識の視界としてのパースペクティヴにおいてのみ認識される。事象は特定のパースペクティヴから特定の側面において認識され、別のパースペクティヴから別の側面において認識される。このように事象は人間の視界に応じてさまざまな側面を呈する。それぞれの視界からの認識によって明るみに出された事象の側面が、そのつどの具体的な認識の成果である。この認識の成果があってはじめて、事象のさまざまな側面の総体として「事象全体」が想定されるのである。したがって事象全体は観念的に想定された理念であって具体的な認識の対象ではない。事象はそれぞれのパースペクティヴからなされる具体的な認識の成果として多様な側面において認識される。しかし事象がどれほど多様な側面で認識されようとも、それらの側面が事象全体を形成することはない。なぜなら事象全体は具体的な認識の成果から観念的に想定された構成物であり、認識に先行して存在するものではないからである。
過去の事象を認識するとは、事象を構成する記号をコンテクストに組み入れることである。コンテクストは現在の人間の関心の視点から関連づけられた過去の記号である。過去の事象を認識するために過去の記号を関連づけてコンテクストを構成しようとするとき、人間は必ずそれぞれの関心の視点に立つ。関心の視点から広がる認識の視界がパースペクティヴであり、過去の事象はそれぞれのパースペクティヴに応じて異なる姿を見せる。関心の向きを変えると、パースペクティヴも変化し、その結果パースペクティヴにおいて見られた歴史も姿を変える。歴史はパースペクティヴに応じて絶えず変容する通時的および共時的に関連したコンテクストとしてこの現在に存在する。収集した記号を既存のコンテクストに組み入れるときも、それぞれの視点から記号を評価したり、取捨選択したり、序列を入れ替えたりする。関心の視点を離れてそれ自体で固定した客観的な史実というものはない。あるのはそのつどの現在の人間の関心にとって切実な歴史的事実である。
コンテクストを構成する現在の人間の関心を離れて歴史は存在しない。2)歴史は現在の人間の関心の函数であり、客観的に存在する歴史というものはない。過去の人間が主体として客体と関わることによって歴史に関与したように、現在の人間も既存のコンテクストを参照し、コンテクストを書き換え、あるいは新しいコンテクストを加えたりすることによって歴史に関与する。コンテクストが更新されることによって通時的および共時的に関連するコンテクストとしての歴史も変わる。それゆえ歴史は過去の客観的事実を連ねたものではなく、現在の人間の関心にもとづいて作られる歴史のコンテクストとして不断に生成されるものである。先にコンテクストを「記号を捕捉する関心の網」と表現したが、人間の関心の網にかからない歴史というものは存在しない。この場合、人間がすべての歴史に関心をもつというより、むしろ人間が関心をもったものが歴史のすべてである。
1)ポール・ゴーギャンが1897年から1898年にタヒチ島で描いた絵のタイトル。
2)歴史は現在の人間の関心から生じることを歴史家の立場で語ったのが、イタリアの歴史学者ベネデット・クローチェである。「現代の歴史が直接に生から発生したものであるとするならば、過去の歴史と通称せられている種類の歴史もまた同様に生から直接に成立するものである。何故ならば、現在の生の関心のみこそが人を動かして過去の事実を知ろうとさせることができるということは明らかである。したがってこの過去の事実は、それが現在の生の関心と一致結合されている限りにおいて、過去の関心にではなく現在の関心に答えるのである」(『歴史の理論と歴史』羽仁五郎訳)。