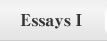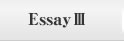第7章 存在論的視点
第1節 存在
1.存在了解
人間は目の前の具体的な事物から、心のなかの記憶や感情、さらには抽象的な観念にいたるまで、およそ存在するものを「在る」と受け止める。存在の最も基本的な了解は在ることである。在ることの了解は、たとえば目の前の花瓶を見たときにそれを存在するものとして受け止めることである。花瓶に差してある花を入れ替えようとして花瓶に手を伸ばすのは、花瓶がそこに存在することを前提としているからである。花瓶が存在することを前提としているとは、花瓶がそこに在ることをつねに了解していることである。在ることの了解はあらゆる意識活動の前提であり、意識活動の基礎のうえにおこなわれる人間のあらゆる精神的および身体的な活動の根底にある。
人間は目の前の事物を存在するものとして受け止めるだけでなく、自分自身をも在ると受け止めている。というより人間は目の前の事物を在ると受け止めるとき、つねに自分が在ることを前提としている。なぜなら自分が在るという了解がなければ、およそ在ることについての了解をもつことができず、したがってまた他の事物を在ると受け止めることもできないからである。人間はつねに自分が在ることを了解しており、自分が在ることの了解に照らして自分以外のものを在ると了解する。自分と自分以外のものが共通して在ることの了解を存在了解という。存在了解は、自分が在ることの了解に基礎をおき、自分を含むすべてのものが存在することの了解である。
人間が存在了解をもつためには、なによりも自分が在ることを了解していなければならず、そのためには自分が自分に現れていなければならない。自分が自分に現れるとは、自分が自分にたいして隠れていないことである。自分が自分にたいして隠れていたなら、人間は自分を意識することもなければ、自分というものを了解することもない。自分を了解することがなければ自分は存在しないに等しい。なぜなら自分は自分として了解された限りで存在するからである。自分が存在するとは、自分が在ることを了解することである。ここで、自分が自分に現れることと、自分が自分として了解されることと、自分が存在することは一つのことである。自分が了解されることにおいて自分が自分に現れ、自分が自分に現れることにおいて自分が在ることが了解されるのである。
自分が自分に現れるのは、自分が隠れた状態から明るみに出ることであり、それは意識の反照においておこなわれる。意識の反照は、意識が意識そのものを意識することである。意識はつねにあるものの意識であるが、同時にそれ自身の意識でもある。自分が自分に現れるとは、意識の反照において自分が意識に照らされた明るみに出ることである。意識の反照において自分が自分に現れてはじめて自分が在ることが了解される。意識はつねにあるものの意識として自分以外のものも照らしている。自分が自分に現れるとき、同じ意識の光に照らされて自分以外のものも自分に現れている。自分が自分に現れることにおいて自分が在ることが了解されるように、自分以外のものも同じ意識の光のもとで在ると了解される。自分が自分に現れて在ることの了解を基礎として、存在一般の了解が生じる。この存在一般の了解が自分以外のもの、すなわち他の人間や事物を在ると受け止めるための土俵をなす。自分が現れて在るのと同じ土俵で、自分以外のものを現れて在るものとして受け止めるのである。
自分が在ることの了解において自分が自分に現れるとは、自分が自分を意識することである。発達論的に見るならば、人間が最初に自分を意識するのは胎児のとき羊水の原環境においてである。胎児はまだ目も見えず耳も聞こえない段階で自分に気づく。自分に気づくとは、自分が自分と出会い、自分が在ることを了解することである。ここでいう自分は言語化以前の<じぶん>である。それは「自分」という言葉に先立つ「おのれ性」もしくは「みずから性」ともいうべきものである。胎児が<じぶん>に気づくことによって意識が目覚める。<じぶん>に気づくとは<じぶん>が存在することに気づくことである。<じぶん>の存在に気づくことそれ自体が原初の意識をかたちづくる。胎児は<じぶん>が在ることを了解することによって意識に目覚め、それとともに無から有へと出現する。胎児が<じぶん>が在ることを了解することは五感の形成に先行する。胎児が<じぶん>に気づくとき、<じぶん>の了解は在ることの実感に満たされている。それは視覚にも聴覚にも、その他の芽生えつつあるいかなる感覚にもよらない存在の了解である。ここでいうまでもなく「自分」がそれ自体は言葉であるように、「在る」もそれ自体一つの言葉であり、胎児は在ることを言葉として理解しているわけではない。胎児にとって在るとは認識の対象でもなければ理解の内容でもない。言語化以前の在るを<ある>と表記するなら、<ある>とは羊水に包まれた胎児の言語化以前の存在についての透明な実感である。そこには言葉はいっさい介在しない。<ある>は直接的な存在了解である。この了解には、いかなる疑いも差しはさむ余地がない。<ある>ことは、意識に目覚めた胎児にとって最も原初的な了解である。
胎児のなかで<じぶん>の了解と<ある>ことの了解は不可分のものとして目覚める。胎児が<じぶん>に気づくとき、自分を<ある>ことにおいて了解する。胎児が<じぶん>に気づくことによって意識の領域が開け、自分と自分以外のものが在ることの了解として存在の領域が開ける。この存在の領域に現れる自分以外のものは、やがて意識が発達するにつれて他の人間やもろもろの事物として把握される。存在の領域に存在するものを認識するために、感覚とそれを意識する感覚意識が形成される。感覚が発達して五感に分化すると、視覚や聴覚や触覚などがそれぞれの働きにおいて対象を捉える。感覚の発達に伴い感覚意識の領域が広がる。存在の領域に存在するものは感覚意識の対象である。それゆえすべての感覚意識の対象は、根底において存在することが了解されている。
2.存在の事態
成熟した意識に対して存在の領域が開け、そこにおいて存在するものは在るものとして了解される。意識に目覚めた人間は存在の領域にはいり、そこにおいて在ることに直面する。人間にとって存在は自己と同じく始原的な事実である。存在は事実として人間にいやおうなく与えられている。与えられることと在ることは一つのことである。およそ与えられるものは存在し、およそ存在するものは与えられる。与えられることとしての所与は存在することであり、存在することは所与である。自分の存在にせよ自分以外の存在にせよ、人間にとって存在するとは所与として与えられて在ることである。この世界において人間は与えられて在ることを回避できない。このように不可避的に与えられて在ることを存在の事実という。およそ事実が事実として成り立つのは、事実が与えられて在るからである。存在の事実は、あらゆる事実の基礎である。あらゆる事実は、存在の事実の基礎のうえに成り立つ。人間がこの世に生を授かることによって存在の領域にはいることも、存在の領域で自分が存在することも、あるいは存在の領域で自分以外の人間が存在することも、人間以外のものが存在することも存在の事実として絶対に変更がきかない。人間はこの世界に生まれていやおうなく存在の事実に引き渡される。この世界で存在は回避不能な事実として人間に迫る。事実が事実として人間に迫るのは、当の事実が存在するからである。事実が存在することは、変更することも回避することもできない。存在の事実が絶対に変更することも回避することもできないことを存在の事実性という。
存在の事実が人間に迫るのは、存在の領域において人間に存在が開示されて、人間が存在に直面することによってである。しかしまた存在が人間に開示されるのは、人間の認識が存在に関与することによってである。人間が存在の事実に直面するとき、そこにはいやおうなく人間の認識が関与している。人間は認識を介して存在と向き合う。人間が存在と向き合い、存在が現に在ることの事実として人間に迫ることには、不可避的に人間の認識が関与する。ここで認識の定義を確認するならば、認識とは了解や理解や推定や判断など事象の把握にかかわる知的能力の作用である。了解は言葉として分節化されていない事象の把握であり、了解の内容を読み解いて言葉として分節化したときに理解が生じる。あるものの認識においてそれを直接的に、つまり言語化以前に<ある>と受け止めるのは了解であり、それを言葉を介して在るもしくは「存在する」と把握するのは理解である。事実とは人間に避けがたく与えられることであり、それはまた人間に所与として開示されることであり、そこにはいやおうなく認識が関与しているのである。
存在に認識が関与するとは、人間が存在に直面してそれを事実として受け止めることである。人間が存在に直面するためには、人間自身も存在に現れていなければならない。存在に現れるとは、現れて在ることの了解に立ち入ることである。人間は人間として存在している以上、つまり自分を自分として了解している限り、現れて在ることの了解に立ち入っており、そこには不可避的に認識が関与している。このように人間がいやおうなく認識を介して存在の事実に直面することを存在の事態という。存在の事態は人間が認識を介して存在と向き合うことである。人間が存在の事実に直面するのは必ず存在の事態においてであり、存在の事態はつねに認識を巻き込んでいる。人間は存在の事態を離れて存在について考えることはおろか、およそ存在というものを予感することすらできない。人間にとって存在にまつわるいっさいのことは、いやがおうでも認識が関与する存在の事態において起こる。。
人間は現れて在ることの了解をもつことによって、存在の事態におかれる。存在の事態において存在と直面し、現に在るものと出会う。現に在るものと出会うとは、現に在るものを在ると受け止めることである。存在の事態において人間が現に在るものと出会うためには、人間自体が存在に現れていなければならない。人間はみずからに現れることによって、はじめてみずからを在ると受け止める。人間がみずからに現れるとは、みずからの意識に現れることである。人間がみずからに現れることができるのは、人間が意識をもっているからである。仮に意識がないとしたら人間は意識にたいして現れることはできず、したがってみずからに現れることはない。意識がないという仮定は、たとえば死体の状態として想定することができよう。死体には意識がなく、みずからの意識に現れることもない。たしかに死体そのものは存在に現れている。しかし死体は完全に存在そのものに沈んだままであり、存在の事態に立ち入って存在と直面することはない。
人間は存在了解にもとづいてこの世界において出会う事物を存在すると受け止める。事物を存在すると受け止めるさいに人間は根本的にその存在を確信している。世界はこの存在確信の土台のうえに成り立っている。なんらかの事物が存在すると思ったのは錯覚で、よくよく調べてみたら実際には存在しなかったというケースはある。しかしその場合でも、そうした錯覚そのものが成り立つためには根底に存在することの了解がなければならない。現実として存在するにせよ、錯覚として存在するにせよ、そこではつねに存在することの了解が前提になっている。存在することの了解は、存在にたいする確信であり、本当に存在するか否かの検証もこの存在確信の基礎のうえでなされる。ネス湖の恐竜やヒマラヤの雪男の存在が論議されるのも、根底に存在確信があるからである。 恐竜や雪男は存在するかと問うとき、雪男が実際に存在するか否かの以前に、その問い自体が存在についての基本的な了解のうえに成り立っている。もし人間のあいだに存在についての了解がなければ、恐竜や雪男の存在について論じることもなければ、ましてやその調査に乗りだすこともない。調査の結果、恐竜や雪男は実際には存在しないと結論づけられた場合でも、存在そのものの了解、すなわちいかなる説明も要しない存在にたいする確信はいささかも揺らぐことはない。
存在確信は人間のいっさいの知的活動に先行する。デカルトの「我思う、ゆえに我在り」(コギト・エルゴ・スム)も例外ではない。なぜなら「我思う」ことから「我在り」といいうるためには、自己が存在することについての了解がすでになければならないからである。仮に自己が存在することの了解がないとしたら、コギトはコギトの内部で完結するしかないだろう。というのも「我思う」から帰結するのは「我思う」であり、けっして「我在り」ではないからである。その場合コギトをどれほど徹底しても、あるいは徹底すればするほど「我思う、ゆえに我思う」という同語反復しか生み出さない。コギトの根底に存在の了解があるからこそ「我思う」ことから「我在り」ということができるるのである。「我思う、ゆえに我在り」は構文的には推論の体裁をとっているが、「我思う」ことから「我在り」が推論されるのではない。「我思う」ことにおいて、すでに我が存在していることが確認されるのである。徹底した懐疑と内省のすえに「我思う」とは、我が存在していること、すなわち自我が現れて在ることを自覚することである。このときコギトは最も原初的な了解としての存在了解である。コギトの言表において存在は思考に先行する。「我思う」は自我が存在することの追認にすぎない。それゆえコギトの主人公は「コギト・エルゴ・スム」という代わりに「スム・エルゴ・コギト」(我在り、ゆえに我思う)というべきであった。
以上見たように、あるものが存在するとは、現れて在ることである。現れることなく隠れたままでいるならば、それは存在しないことである。どこから現れるのかと問われたら、無から現れるとしか答えようがない。だが、最初に無があってそこから有が生まれるのではない。無は有の反対として無そのものである。すなわち無はないのである。存在が無から現れるとは、ないことから現れることである。存在がないことから現れるとは、存在の前にはなにもなく、それ自体において現れて在ることを意味する。存在とはそれ自体において現れて在ることであり、存在以前にはなにもない。その意味で存在はすべての発端である。人間も、動物も、植物も、鉱物も、さらには地球も、天体も、宇宙も、あらゆる事物は存在することを前提としている。それらすべての活動や運動は、生きることも死ぬことも、食べることも飲むことも、動くことも止まることも存在することから始まる。人間や動物や植物を生かしている生命も、存在することを前提として成り立つ。生命の謎は生命科学の進歩によってますます解明され、生命の成り立ちについて膨大な知識と情報がもたらされることだろう。しかし生命が存在するということについては、生命科学は一指たりとも触れることができない。科学は根拠に規定された必然性の糸をたどりながら事象を解明する。根拠から根拠へ遡行することにより、必然性の糸は果てしなく延びる。他方、存在はそれ自体においてあり、他のなにものによっても根拠づけられない。他のなにものによっても根拠づけられないとは、根拠必然性がないこと、したがって偶然であることを意味する。存在においてはあらゆる必然性の糸がぷっつり切れている。存在はまさに必然性の糸が切れたところにある。先に「世界と人間が然るようにあることに根拠はなく、それゆえ偶然である」(第1章第1節)といったが、この世界の偶然性は根本的には存在そのものが偶然であることにもとづいている。存在そのものが偶然であるとは、存在することは必然的ではなく、それゆえ存在しないことも可能であるということである。およそ存在するものは、存在しないことも可能であることの無限の可能性の海に浮かんでいるのである。
存在は偶然であり、そのようなものとして無根拠である。存在が無根拠であるとは、存在はそれ以上遡ることができないことを意味する。存在はいかなる根拠によっても先行されることがないという意味で、考えられる限り最も始原的な事実である。ここで「始原」という言葉は、時系列的な意味に解されてはならない。あえてこのようにいうのは、存在の根拠はとかく時系列な始原と混同されがちだからである。その証拠に古代の神話は存在の始まりを「天地創造」に求め、現代の神話は「ビッグバン」に求める。しかしそれらは存在そのものではなく、存在している事物の物理的な発生源であり、存在の根拠とはまったく関係ない。存在はいかなる前提もなく、あらゆる瞬間に現に在ることに現れている。すなわち存在は根拠なく現在するのである。
存在するとは根拠なく現在することであり、それゆえ存在を否定することも、反駁することも、疑うこともできない。なぜならあることを否定したり、反駁したり、疑ったりするのは、なんらかの根拠からなされるからである。たとえば目の前にある花瓶と思ったものは、よくよく見たら取っ手と注ぎ口がついているので花瓶であることが否定される。ここでは取っ手と注ぎ口が花瓶であることを否定する根拠となっている。しかしそのような根拠から花瓶であることが否定されようと、花瓶であることが否定された当のものが存在することに変わりはない。花瓶であると思ったのは間違いで、実は水差しだったとしても、花瓶であると思われたものが存在することは否定できない。目の前の花瓶もしくは水差しは、それ自体において現れて在る。この陶製の容器を水差したらしめているのは取っ手と注ぎ口であるが、水差しを現に在るものたらしめているのは存在である。存在そのものは存在以外のものによって根拠づけられず、したがってなにものによっても否定されない。いかなる根拠によっても先行されないという意味で存在は始原的な生起である。存在はそれ自体で存在し、他のなにによっても根拠づけられないものとして、いかなる記述も拒む。存在について語ろうとすれば、「在る」という言葉が許される最大限であり、それ以上のどんな形容も受けつけない。なぜなら存在はそれ自体において現れて在るのであり、なんらかの構成要素からなるものでもなければ、いかなる修飾要素もまとっていないからである。たとえば花瓶はその素材や形状や外観について、陶製、縦断面がほぼ楕円形で横断面は円形、高さ約30センチ、直径15センチ、地肌は土色などといかようにも記述できる。しかし花瓶の存在は記述のしようがなく、せいぜい「在る」ということがすべてである。1)
3.時間性と空間性
人間が存在の事態において存在と直面するのは、現に在ることとしての現在においてである。現在において人間が存在の事態に立ち入るのは<いま・ここ>である。<いま・ここ>は、人間が存在へと立ち現れる領域である。<いま・ここ>は、根本的に人間が存在するところである。人間が存在するとは<いま・ここ>にあることである。<いま・ここ>に在るとは、人間が現に在ることとして現在することである。存在の事態において、現に在ることとしての存在は<いま・ここ>にあることにおいて了解されている。
空間論的考察で見たように、<いま・ここ>にあることは、時間的な契機として<いま>と空間的な契機として<ここ>を包含している。時間的契機である<いま>に注目するならば、「いまある」という現在性の存在様態は現に在ることとしての現在から汲み取られている。「いまある」とは、現在性の了解を言語化したものである。時間論的考察において見たように、「まだない」という未在性の了解は「いまある」という現在性の了解を基準として成立している。「まだない」の了解は「いまある」ことの了解から出発して、未在性の存在様態として現在に存在する。存在様態は人間の認識に受け止められた存在の仕方であり、根本的に人間の認識の構造によって規定されている。未在性の存在様態を生み出す心の働きは予期である。予期の本質は「いまある」こととして了解された現在性の存在様態を越え出ることにある。予期において「いまある」ことが「まだない」ことと関係づけられることによって、認識は現在性の存在様態から未在性の存在様態へ越え出る。その一方で認識は想起の作用により「いまある」という現在性から「すでにあった」という既在性へと滑り出る。人間の体験は次々に記憶として記銘され、その大部分は瞬時にして消失し、一部は徐々に忘却され、限られた記憶だけが人間のうちに保存される。それらの記憶は想起されることによって現在に再現される。そのさい現在に再現された記憶はことごとく「すでにあった」こととして了解されている。想起によって再現された記憶はすべて既在性の存在様態において現在にある。「いまある」という存在の基本的な了解は、他の存在様態との相互参照によってそれ自体において「まだない」という未在性の了解と、「すでにあった」という既在性の了解へと拡散している。「いまある」ことの了解がそれ自体において未在性と既在性を含んでいるのは、現在における知覚が予期および想起と不可分であるという人間の認識の構造にもとづいている。「いまある」ことの了解がそれ自体において未在性と既在性へと広がっていることを時間性という。
<いま・ここ>にあることの空間的契機である<ここ>に注目するならば、人間の存在は「ここにある」こととして了解される。「ここ」は自分が存在に現れるところとしての絶対的な言語以前の<ここ>と、それに関係づけられた無数の相対的な「ここ」を包括する概念である。相対的な「ここ」は部屋でもあるし、建物でもあるし、街全体でもある。しかし「ここ」を自分が存在に現れるところと限定するならば、自分以外のものが存在に現れる場所は「ここ」ではない。しかしながらそれらの場所も自分が存在に現れる「ここ」を基準としている限り「ここ」と関係がある。それらの場所は基準としての「ここ」との関係において「そこ」や「あそこ」などの言葉で指示される。「そこ」も「あそこ」も「ここ」から派生しており、存在を開示する場であることに変わりはない。「ここ」に在る存在様態を「此処に在る」ことと解して此在性と呼び、「ここ」ではない場所に在る存在様態を「彼処に在る」ことと解して彼在性と呼ぶことにする。此在性の存在様態は参照により彼在性の存在様態と相即的に成立する。「ここ」の了解がそれ自体において「そこ」や「あそこ」と関係づけられていることを空間性という。
時間性と空間性は、存在の事態における人間の認識の構造的な特性である。存在了解は、それ自体において時間性と空間性を含んでいる。存在とは現に在ることとしての現在であり、認識構造に規定された存在の事態において<いま・ここ>にあることとして了解される。<いま・ここ>にあることを構成する時間的契機である非言語的な<いま>は、時間的に様態化されることによって「いま」と言語化される。「いまある」ことの了解は、時間的に様態化されるプロセスで他の存在様態との相互参照によって「まだない」と「すでにあった」の了解へと広がる。<いま・ここ>にあることの空間的契機としての<ここ>の了解は、空間的に様態化されるプロセスで他の存在様態との相互参照により「そこ」もしくは「あそこ」の了解へと広がる。
ここで時間性と空間性の契機の起源に言及するならば、言語化以前の<じぶん>がみずからに現れることによって意識の領域が開ける。この言語化以前の意識の領域を<いま・ここ>と表記するならば、それは言語化以前の<じぶん>が意識に現れる領域である。<じぶん>は<いま・ここ>においてみずからに現れる。始原的な意識の領域として<いま・ここ>が開けることによって存在が開示される。存在が開示されるとは、<じぶん>が<いま・ここ>に立ち現れることにおいて、存在すると了解されることである。<じぶん>が<いま・ここ>に存在することは、人間にとって最も始原的な存在了解である。この始原的な存在了解において、反省によって「自分」として概念化される以前の<じぶん>と、反省によって「いま」と「ここ」として分節化される以前の<いま・ここ>は不可分に融合している。人間の存在了解は、<じぶん>が<いま・ここ>に存在するという始原的な了解を基礎としている。この始原的な存在了解を究極の拠りどころとして、人間がおこなうあらゆる反省レベルの意識活動において自分が存在することが出発点とされている。
<じぶん>が<いま・ここ>にあることは、人間の最も始原的な存在了解である。この言語化以前の意識の領域である<いま・ここ>が反省によって対象化されると、<じぶん>は「自分」として概念化される。それと同時に<いま・ここ>は分節化されて、それぞれ「いま」と「ここ」として概念化される。それに伴って「いまある」ことは「まだない」および「すでにあった」ことと対比されて理解され、さらにここから時間区分としての「現在」が派生する。同様に言語化以前の<ここ>が概念化されることによって、「そこ」や「あそこ」と相対的な空間的な場所として「ここ」が派生する。この派生の過程を逆照明するならば、原初の意識の領域である<いま・ここ>は、<じぶん>がみずからに現れることの始原的な存在了解がそれ自体において孕んでいる時間性と空間性の契機である。時間性とそれに関連するすべての時間の観念、および空間性とそれに関連するすべての空間の観念は、時間性と空間性の契機を孕んだ始原的な存在了解に淵源する。
1)哲学史上、存在の根拠の問題に正面から取り組んだのはライプニッツである。彼はこの問題を「何ゆえに、無いのではなく或るものが現実に存在するのか」(『二十四命題』池田善昭訳)と定式化した。この問いに答えるにあたって拠りどころとしたのは「何ものも根拠なしには生じない」という形而上学的原理である。そのような根拠は、現実に存在する「実在的根拠」である。実在的根拠は「実在的存在」として必然的に存在しているのでなければならない。さもなければあるものを存在させることはできないからである。ライプニッツはこの実在的存在をあらゆる事物の究極の根拠として提示し、これに「神」という言葉を当てた。存在の根拠をとことん追い詰めながら最後に神を根拠と等置する点で、ライプニッツの思想は本論の対極に位置する。