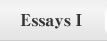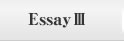第1章 世界論的視点
第2節 環境
1.環境
総体としての普遍的世界は、個々の人間が生きるこの世界から派生した理念である。この世界は具体的な人間や事物や関係からなるという点で限局的であり、相互に重なる共同体から構成されているという点で複層的である。個々の人間はこの限局的で複層的な世界に生まれてなんらかの共同体に属し、そのなかで世界の構成要素に囲まれ、それらと関わりながら生きる。この世界で個々の人間が世界の構成要素に取り囲まれている状況を環境という。
人間はこの世界に生まれると同時になんらかの共同体に属し、特定の環境におかれる。人間がこの世界で生まれて特定の環境におかれることは避けられない。なぜなら人間がこの世界に生まれておかれる環境は個々の人間の誕生に先立って存在するからである。人間がこの世界でおかれる環境は、不可避的に所与として与えられた事実である。事実とは人間に所与として与えられ、その限りで避けられない事象である。人間に先行して存在する事象を「先に在った」事実として先在的事実と呼ぶ。先在的事実としての環境は、変更することも回避することもできない。この世界に生まれてくる人間には、自分がおかれた環境を先在的事実として受け入れる以外の選択肢はない。事実が変更することも回避することもできないことを事実性と呼ぶことに対応して、先在的事実が変更することも回避することもできないことを先在的事実性と呼ぶ。先在的事実性とは、人間に与えられた事実が人間に先行して存在することである。人間が生まれ落ちる共同体とその環境は、先在的事実性において人間に与えられている。
この世界に生まれたばかりの人間の子供が最初におかれる直接的な環境は、産婦人科の分娩室である。分娩室は新生児が生まれて初めてもつ世界との物理的接点である。母親の胎内から出た新生児が最初に接触する人間は、出産に携わる産婦人科医や助産師や看護師である。同時に間は、母親の体内から胎盤とともに取り出された瞬間に家族共同体に属している。新生児は、母親の体内から取り出されることによって、これこれの名前をもった父親と母親のあいだに生まれ、特定の家族共同体に属する。その家庭は貧しく、夫婦仲も良くないかもしれない。こうした環境は新生児にはどうしようもないことであり変更できない。子供はこの両親の手で育てられ、彼らの家庭とそれを取り巻く地域のなかで成長する。地域は人間の成長に決定的に影響する環境要因であるが、それも新生児は選択することもできなければ変更することもできない。新生児はこうした先在的事実を所与として受けいれるしかない。
やがて少年期を経て成長した青年は、両親の住む故郷を離れて別の町で暮らすことを決意する。その決断には、自分の人生について考えをめぐらすようになった青年が、それまでの人生を規定した環境の先在的事実性から自由になるという意味合いがある。これまでは家族と、その家族を取り巻く地域社会は変更のきかない先在的事実であった。しかしいまや青年はこれらの事実を丸ごと拒否することができるまでに成長している。両親から離れて別の町に住むことは、青年の自由意志による選択である。青年はみずからの意志でそれまでの環境を拒否し、あらたな環境を選択する。とはいえ青年が移り住む町は、青年がそこに行く前から存在しているものである。青年がこの世界に誕生したときとは異なり、このときはみずからの意志で環境を選択するが、選択される環境はすでに存在しており、青年の意志的な選択に先行する先在的事実である。青年はこの新しい環境でなかなか定職につけず、経済的に困窮する。周囲の人間との関係も悪化し 、自暴自棄になって犯罪をおかす。警察に逮捕されて裁判にかけられた結果、有罪の判決がくだり懲役刑をいいわたされる。青年が送り込まれる刑務所は、みずから意志して選んだものではないが、青年がこれから生きていく環境となる。この環境も青年が移送される前から存在している先在的事実である。この不幸な青年にとって、この先何年かは刑務所が青年の属する共同体となる。
以上から明らかなように、人間が生まれ落ちる環境も、意志的に選択する環境も、強制的に指定される環境も、人間にとって先在的事実である。人間は、どこに生まれようと、いかなる共同体に属そうと、みずから意志したものであろうとなかろうと、そのつど特定の環境におかれ、その環境を構成する要素が所与として与えられる。人間はそれらの所与を受け入れ、それらと関わりながら生きる。人間が所与を受けとめ、所与にたいして働きかけるのはつねに現在である。人間が生まれ落ちる家族や、自由意志によって選択する共同体や、他人の意志によって強制される環境は先在的事実であるが、それらの先在的事実が存在するのは現在である。たしかに先在的事実は人間の誕生や選択や強制に先行するが、先在的事実が人間に所与として与えられるのはあくまでも現在である。環境はつねに現にある事実として人間に迫る。環境はいかなるかたちであれ人間に先行し、その限りで先在的事実であるが、個々の人間に対峙する事実として人間に迫るのは現にある事実としてである。先在的事実は人間がそれに直面する局面で見れば、つねに現にある事実である。事実性は、先在的事実が現にある事実として人間に対峙することである。およそ事実が人間に所与として迫るのは現在であり、先在的事実が人間に与えられるのも現在においてである。
この世界に生まれた人間が特定の環境のなかでなんらかの共同体に属し、具体的な人間や事物に囲まれるのは、変更不能な事実である。しかしそれは世界を構成する個々の要素が変化しないということを意味するものではない。むしろ世界の構成要素は絶えず変化し、変化することによって存続し、それが世界の多様性を生み出している。この世界に生まれた人間は、世界を構成するさまざまな要素に取り囲まれており、その数量と多様性は際限がない。人間がこの世界で生きるとは、この多種多様な世界の事象と関わることである。世界の事象と関わるとは、人間が世界を構成する個々の要素を受けとめ、それらに働きかけ、さらにはそれらを改変することである。世界の構成要素は単に変化するだけでなく、人間の手で変更することもできる。人間は世界を構成する個々の要素を変更するだけでなく、人間を取り囲む環境そのものも変更することができる。その最たるものが革命である。革命を起こしてそれまで民衆を支配してきた古い政治体制を覆して、新しい体制に置き換える。革命によって環境は激しく破壊され、劇的に変化し、新しく生まれ変わる。しかし革命家にとっても、反革命家にとっても、彼らに同調または反対する市民にとっても、18世紀後半にフランスで、あるいは20世紀前半にロシアで、あるいは20世紀後半に中南米で、それぞれの時代と場所に特有の環境におかれる事実性は変えられない。革命が成功して新しい社会体制に変わったとしても、その結果人間が新しい特定の環境におかれることに変わりはない。王政が倒れて共和制になり、帝政が打倒されて社会主義体制に移行し、あるいは軍事政権が倒されて革命政権が樹立されると、その過程で起こる内乱、粛清、反革命など途方もない混乱が、激動の時代に生きる人間にとって新しい環境となる。それらの環境がそのときどきの人間が意図したとおりのものであるか、意図したものとは正反対のものであるかにかかわらず、人間がそのつど特定の環境におかれることの事実性は変わらないのである。
2.個人史
人間は、この世界に生まれて世界を構成する無数の要素に取り囲まれる。人間はそれぞれの環境において世界の構成要素を所与として受け入れ、つねにそれらと関わりながら生きる。人生とは、人間がこの世界に生まれて世界の構成要素と関わる過程である。この世界に生まれ落ちてから現在にいたるまでの人生を俯瞰すると、人生は1本の軌跡のように見える。この軌跡を個人史という。個人史は、個々の人間が生まれてこのかたそのときどきの環境において世界の構成要素と関わり続けて現在に収斂する過程である。現在は過去の累積の帰結であり、人間はそのつどの現在における過去の累積の帰結としてそれ自体において個人史である。
個人に先行して存在する事実を「先に在ったこと」として先在的事実と呼ぶのにたいして、個人史を構成する過去の事実を「既に在ったこと」として既在的事実と呼ぶ。個人史は既在的事実の累積である。先在的事実は個人を取り巻く環境の所与性に由来するが、既在的事実は個人史を構成する体験された事実の所与性に由来する。先在的事実が変更することも回避することもできないように、個人史として累積された既在的事実は修正もやり直しもきかない。人生には成功することもあれば失敗することもあり、ときには脇道にそれることも、過ちを犯すこともある。個人史は、この世界に生まれてこのかた体験した無数の出来事や、偶然の出会いや、大小の成功や失敗から織りなされている。個々の人間が誕生して以来現実と関わりながら、現にあるとおりの推移をたどってきたのは否定できない事実である。個人史の軌跡は別のようでもありえたはずであるが、結果としてかくあるとおりに推移して現在に帰結したという事実は絶対に打ち消すことができない。人生は望むと望まざるとにかかわらず現にあるとおりであるほかはない。過去を振り返り、自分の人生を個人史として俯瞰するとき、人生はかくあるようにならざるをえなかったという必然性を帯びる。
人間がこの世界に生まれることは根拠のない偶然であり、人間がこの世界に生まれる理由は存在しない。人間はただ偶然この世界に生まれる。そこには根拠もなければ、根拠によって規定された必然性もない。しかしこの偶然性の大海原にあって、これまでたどってきた人生はかくあるようにしかなりえなかったという限りにおいて必然的である。個人史は別のようでもありえたが、実際には現にあるとおりのものであることは変更できない事実である。人生をその必然性において受けとめるとき、これから進むべき人生の軌道が見えてくる。これまでの個人史の軌跡が既在的事実として修正もやり直しもきかないのにたいし、これから進む人生の軌道は刻一刻と選択できる。これから進む人生は、そのつどの現在における選択をとおして新たに既在的事実を生み出す過程である。
人間とはそれ自体においてこの世界に生まれて以来書き綴ってきた個人史の帰結である。現にあるとおりの人間は個人史の必然的な帰結であり、これに代わるものはない。この唯一無二の歴史から、おのずとこれから進むべき人生の軌道が開ける。その軌道は、これまでの人生がそれに向かって進んできた、しかし自分自身にも明確ではなかった目的に向かって続いている。それはこれまでの人生で策定された無数の目的連関の終点に位置すべき人生の目的である。それは人間の頭上に君臨する超越的目的ではなく、この世界に生まれて以来書き連ねてきた個人史に由来する内在的目的である。
3.現実
人間はそのつど与えられた環境を事実性において受けいれるしかない。人間がこの世界に誕生していやおうなく特定の環境におかれたとしても、人間がみずから環境を選択したとしても、さらには積極的に環境に働きかけて環境そのものを変えたとしても、人間を取り巻く環境はこの現在に与えられた事実として人間に対峙する。環境を構成する個々の要素が変わり、人間を取り囲む環境がめまぐるしく変化しようとも、環境はつねにこの現在において事実として人間に迫る。人間がこの世界で特定の環境におかれて不可避的に直面する事実を現実という。現実とは字義どおり「現にある事実」である。この世界に生きる人間は特定の環境においてそのつどの現実に直面する。現実は「現にある事実」として人間に迫り、人間は生きている限り現実を回避できない。
現実において人間と事物はそれぞれが無数の他の人間と事物と連なり、絡み合い、輻湊してもろもろの関係を生み出している。現実において人間が他の人間や事物と結ぶもろもろの関係を現実の諸関係と呼ぶ。人間自身も、身のまわりの事物も、道路や建物や橋などの人工的な構築物も、すべて現実の諸関係に組み入れられている。現実の諸関係は、家族や親戚や友人などの人間関係から、生産や流通や販売などのシステム、政府や企業や軍隊などの組織、法律や経済や政治などの制度にいたるまでありとあらゆるレベルの人間と事物の関係を包含する。
人間自身も現実の諸関係に組み込まれることによって現実の一部をなしている。しかし人間は単に現実の一部をなすだけでなく、現実に能動的に関与することができ、それどころか現実の諸関係を改変することもできる。この面で見れば人間は現実にたいして能動的である。その一方で人間は現実の諸関係に制約されており、この面で人間は現実にたいして受動的である。実際、無数の人間と事物によって織りなされる現実の諸関係は、一人の人間の意志で自由に動かすことはとうていできない。その意味で現実は個々の人間から独立しており、ときには個々の人間と対立もする。
現実を特徴づけている基調は現実感である。現実感とは「これは現実である」という確信である。この確信は現実の事実性にもとづいている。現実の事実性は、現実がこの現在に所与として与えられており、その所与性に関して変更することも回避することもできないことである。現実において人間は現実の諸関係に組み込まれている。この世界に生きるとは、現実の諸関係を構成する人間や事物と関わることである。この世界に生きる限り、人間は現実の諸関係に組み込まれており、そこから逃れることができない。「これは現実である」という確信は、自分が現実の諸関係に組み込まれていることの実感である。
現実の反対は夢である。夢を見ているとき、自覚的ではないにせよ夢が現実だと思っている。しかし夢の内容がどれほどリアルであろうと、目が覚めれば「あれは夢だった」と判断できる。夢のなかで夢を見て、夢から覚めたと思ったら、それも夢だったということがある。この場合も最終的には目が覚める。最終的に目が覚めたという判断は、自分はいま目覚めているという覚醒意識に裏づけられている。この覚醒意識の根底にあるのは現実感、すなわち自分が現実の諸関係に組み込まれていることの実感である。朝、ベッドで目が覚めると同時に現実の諸関係が意識に浮上する。まず自分が現在いる場所が潜在的に確認され、これから起きてする必要な身支度が習慣的に意識される。意識は自分と家族を取り巻く状況や、その日にやるべき仕事へと拡大する。その意識の背景には地域や学校や会社、政治や経済や社会などさまざまなレベルの現実の諸関係が広がっている。こうして今日目覚めた世界は、昨日寝る前の世界と同じであることを瞬時に確信する。どれほど深い眠りをむさぼろうと、人間はいやおうなくこの世界へと目覚める。それはそこから逃げられないという意味で最終的な覚醒であり、そうして目覚めた世界は最終審としての現実である。
最終的に覚醒した現実を夢とみなすことも、目覚めたまま現実から逃げ出すこともできない。とはいえ、現実を夢とみなしたり、目覚めた状態で現実から逃げ出す方法がないわけではない。そのような方法としてひきこもりや精神病の諸症状をあげることができる。たとえば自分の部屋にひきこもって現実との関係を物理的に遮断する。一日中ゲームをしているか、本を読んでいるか、ただぼーっとしているかの違いはあっても、本人は現実との関係を断ち切ることに必死である。あるいは、周囲にたいして極度に無関心になることによって現実の事実性を希薄化しようとする。あるいは、自分は某国から亡命した科学者で密かに強大な核兵器を開発し、その気になればいつでも世界を一瞬にして消滅させることができるなどと妄想することによって現実のほうを修正しようとする。さらには現実感を完全に喪失して現実に起こるすべてのことが夢のなかの出来事としか思えなくなる。こうした行動や症状が思春期に多く見られる理由は明らかである。それはこの時期に生理的に子供から大人へと変わり、社会的にも進学や就職など一生の進路の選択を迫られて、いやがおうでも現実と向き合うようになるからである。このとき夢見る少年・少女は覚醒を強いられる。家庭では両親から、学校では教師から現実に直面するよう促され、それを世間の常識が強引に後押しする。大部分の子供は程度の差はあれ躊躇と抵抗を経ながら次第に現実への覚醒に順応していく。しかしあくまでも現実への覚醒を拒絶する子供は、失われた夢の代償として幻覚を見、幻聴を聞き、妄想の世界にはいる。このような代償行動や症状が発現すること自体、現実が揺るぎない覚醒であることを逆照明しているのである。
4.日常
現実において人間が日々生活を営む局面を日常という。日常は読んで字のごとく「日々の常」であり、昼と夜のリズムに刻まれて連綿と繰り返される。日常は人間が現実に生きる基盤である。人間は日常に生まれ、日常で成長する。人間が成長する過程で、住んでいる地域や、所属する共同体や、家族構成が変わっても、人生の大半の時間を日常で過ごすことに変わりはない。
日常を特徴づけている基調は親近感である。日常で身のまわりに見いだされるのは、どれも慣れ親しんだものばかりである。朝はいつもと同じ部屋で目覚め、見慣れた洗面所で顔を洗い、いつもと変わらない食卓で朝食をとる。食卓の上に見慣れないコーヒーポットが置かれていたとしても、それは長年使っていたコーヒーポットが壊れたので購入したものであることを知っている。朝食にコーヒーを飲むのは長年の習慣なので、新しいコーヒーポットもたちどころに日常に溶け込む。壁に掛けてまもない絵は目新しい感じがするが、それも数週間後には見慣れ、やがて見飽きる。このように日常は見慣れたものと見飽きたもので満ちている。日常の繰り返しに飽きると、人は非日常を求めていっとき日常から脱出しようとする。そのためキャンプに行ったり、海外旅行に出かけたりする。ベネチアでゴンドラに乗って水の都をクルージングするのは一生に何度も経験できない非日常である。しかしゴンドラを漕ぐゴンドリエーレにとっては、見慣れた観光客を見飽きた風景に案内する日常である。
日常身のまわりにあるすべての事物は機能性と有用性を備えている。機能性とは、事物がなんらかの機能を有することである。事物の機能とは、事物が有する所定の働きである。所定の働きは、事物が機能を発揮することによって達成されるはずの目的から規定される。目的とは、現在は所有していないため手に入れようと志向するものである。手に入れようと志向するものは物であったり、事柄であったり、行為であったりする。たとえば手に入れようとする物は車であり、事柄ならば幸せになることであり、行為ならば庭木を植え替えることなどである。いずれの場合も、目的は人間によってそのつどの関心にもとづいて設定される。事物は機能性と設定された目的にもとづいて「~するためのもの」として定義される。事物がその機能を発揮するのは、事物が設定された目的に使用される場合である。たとえばハサミは紙を切るという機能を有する。ハサミを機能に関して設定された目的から定義すれば、「紙を切るためのもの」である。この場合、ハサミの意味は紙を切るという機能性にある。ハサミは紙を切る目的に使用されてはじめてその機能を発揮する。ハサミが石や鉄を切る目的に使用されたら、ハサミの機能は発揮されない。ハサミが所定の機能を発揮して紙を切る目的を達成した場合に、ハサミの意味が満たされて有意味となる。設定された目的が現に達成されているか、したがって意味が顕在的に満たされているか、あるいは目的は機会さえあれば達成されるか、したがって意味が潜在的に満たされているかは問わない。日常身のまわりに配置されているものは、それぞれの機能に関して顕在的または潜在的に意味を満たしている。
有用性とは、所定の機能を有する事物が有用であること、つまり役に立つことである。事物の有用性は、その事物の価値である。しかし価値はそれ自体で存在するものではなく、有用性が評価されることを前提としている。事物の機能の目的を設定するのが人間であるように、事物の有用性を評価するのは人間である。事物が有用であるとは、人間によって設定された目的を満たすために機能を実行した結果が人間にとって役に立つということである。たとえばハサミが有用であるとは、実際にハサミを使って紙を切った結果が人間に役立つことである。ハサミが錆びて紙がうまく切れなければ、それは人間にとって役に立たず、したがって無価値である。人間が機能に関して設定した目的を達成するものは有意味であり、その結果が人間にとって役立つものは有用である。日常身のまわりにおかれているすべての事物は、機能性と有用性を備えている。それゆえ日常は有意味なものと価値あるもので溢れている。機能性と有用性にもとづく意味と価値が日常の基調として親近感を生み出している。
5.目的連関
日常生活で身のまわりにある事物は、機能性と有用性の関係で互いにつながっている。それらは一見ばらばらにおかれているように見えたとしても、個々の事物の意味と価値が機能性と有用性の関係で了解されている。事物の意味と価値が機能性と有用性の関係で了解されているとは、事物が機能性において把握され、それらの有用性が評価されていることである。この機能性と有用性の了解は無数の事物のあいだに網の目のように張りめぐらされ、あたかも神経回路のようにすべての事物にゆきわたっている。この了解の網が、個々の事物を機能性と有用性の連鎖につなぎとめている。そのため散在する多数の事物は混沌に埋没してしまうことなく、そのときどきの必要に応じて特定の目的のもとに互いに関連づけられる。なんらかの目的が立てられると、それまで雑然と放置されていたように見える諸事物は、それぞれの機能性と有用性の了解にもとづいて目的とそれを達成するための手段の関係に編成される。目的を達成するための手段を実行する局面では、手段そのものが目的化されてそれを実行するためのもろもろの方策が新たに手段として導入される。このような目的とそれを達成するための手段の連鎖を目的連関という。日常身のまわりにある事物は、つねになんらかの目的連関に編入されている。しかも事物が編入されている目的連関は一つではなく、ある目的連関では目的の位置を占め、別の目的連関では手段の位置を占め、そのときどきの状況に応じて手段が目的になり、目的が手段に変わる。
ここで了解の概念を定義しておくと、了解とは世界に存在する事象を精神的に把握することである。「精神的に把握する」という表現は、身体的に把握するという言葉と対比して用いられている。たとえば目の前にあるハンマーを手で掴むことは身体的に把握することである。これにたいしてハンマーの機能性や有用性を了解することは精神的に把握することである。身体的に把握することが対象をみずからの身体に関係づけることであるように、精神的に把握するとは対象をみずからの関心に関係づけることである。了解には、言葉で表現されない不分明な了解から言葉で表現された明瞭な了解まで段階的な幅がある。特に言葉で表現された明瞭な了解を理解という。
言葉で表現されない了解は非言語的な了解として意識の水面下に沈んでいる。このような意識の水面下を無意識と呼ぶとするなら、人間の心は大部分が無意識である。しかしそれは鉱物のように沈黙した無意識ではなく、了解の網目が隅々までゆきわたっている。了解の内容は言葉で表現されていないが、反省すればいつでも言葉に置き換えられて意識の水面に浮上する。了解の内容を言葉で表現することを言語化という。不分明な了解の内容を読み解き、それを言語化することによって了解は理解となる。
理解とは、言語化によって対象を関心の脈絡に組み入れることであるが、身のまわりにあるすべての事物について言語化された理解を保持しなければならないとしたら、それは視界にはいる事物の定義をかたっぱしから反芻するようなもので、人間の頭はたちまちパンクしてしまう。そのような事態を避けるために、いったん言葉で表現される理解に達したら、事象の理解は再び非言語的な了解の状態で保存される。非言語的な了解から言語化された理解にいたるのは連続的なプロセスであり、両者のあいだに明確な境目はない。それはまた非言語的な了解から言語化された理解に進む一方向のプロセスでもない。非言語的な了解が言語化された理解となる一方で、言語化された理解がその内容を保持したまま再び言葉によらない了解の状態に後退する。それは言葉によって表現されないだけで、その気になればいつでも言語化できる。このとき了解は言語化の待機状態にある。日常身のまわりの事物が機能性と有用性の関係において了解されているのも、この待機状態の理解による。待機状態に後退している事物の機能性と有用性の関係は、必要ならばいつでも呼び出して言葉で表現することができる。
たとえば靴を履くたびに、それが「外を歩ときに足に履くためのもの」などと言葉で確認することはない。それにもかかわらず外出するときに靴を履くのは、その用途が自明のこととして了解されているからである。靴を履く手順もいちいち手順を言葉で再確認しなくとも、左右の靴を揃えて足を滑り込ませる。それは靴をはく手順を体が覚えているからである。このように反復によって記憶に定着した手順を習慣という。日常のルーチンを構成する目的連関は大半が習慣化されている。そのため朝起きて出勤し、仕事を終えて帰宅してから就寝するまで、膨大な数の作業や行動のほとんどを習慣にゆだねることができる。
日常は目的連関の了解が網の目のように張りめぐらされているが、それらはつねに明瞭な意識に上がっているわけではない。それでも意識の水面下では目的連関の了解の網は途切れることなくつながっている。たとえば通勤途中に通る公園で咲き誇るヤマブキを見て、子供のときにヤマブキ色のクレヨンを使って絵をかいたことを思い出し、頭のなかに白い画用紙と黄色いクレヨンの筆触がよみがえる。しかしそうなときでも足は確実に駅に向かって歩いている。たしかにこの瞬間は、駅に向かっているのは電車に乗るためであるという目的連関の了解は、色鮮やかな黄色の印象の背景に退いている。だが、そのあいだも了解の神経はしっかり目的連関をつなぎ留めており、反省すれば目的連関はいつでも意識の水面上に浮上する。
日常生活のどんな局面を切り取っても人間はつねになんらかの目的連関のなかにいる。朝起きて身支度するのは会社に出勤するためであり、会社に出勤するのは仕事をするためであり、仕事をするのは収入を得るためであり、収入を得るのは生計を営むためである。人間は日常において家庭、職場、社会と場所を変えながらさまざまな共同体のレベルで現実と関わる。この現実との関わりの全過程で目的が設定され、その目的を達成するための手段が選択され、そしてそれらの手段を実行することが目的となって新たに手段が選択される。こうして目的と手段は次々と連鎖し、それによってさまざまな目的連関が形成される。目的連関は一人の人間においても一つではない。新製品を企画するという仕事上の目的連関、週末に家族でキャンプに行くという家庭上の目的連関、仕事帰りにジムに通うという健康上の目的連関、液晶テレビを有機ELテレビに買い替えるという生活上の目的連関など、日常のあらゆる局面で目的連関が策定される。さらにそれらの目的連関から、それぞれの目的の実現に関連する副次的な目的連関が派生する。これらすべての目的連関は互いに並行し、交差し、あるいは複雑に絡みあって全体としての目的連関を構成する。この目的連関のピラミッドの頂点に位置するのは人間自身である。そもそも人間がこの世界で目的連関を策定するのは究極的には自身が生存するためである。人間は自身の生存という目的のために、食物を摂取し、生殖し、他の人間と協力する。それを可能な限り効率的に遂行するために世界の構成要素を目的と手段に編成して目的連関を策定するのである。この目的連関のピラミッドのなかで個々の目的が実現され、そこから次々と新しい目的が立てられる。逆にある目的の達成に失敗したら、それに関連するもろもろの目的連関が消滅し、変更され、または入れ替えられる。こうして目的連関のピラミッドは絶えずその姿を変えながら不断に更新されるのである。