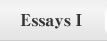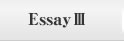第4章 言語論的視点
第3節 技術
1.自然の概念化
人間が自然の一部として自然と交流すること、すなわち大地の上で生き、空気を吸い、水を飲み、必要な栄養を体内に取り込み、代謝を経て不要になったものを体外に排出することは人間の生存の基本形である。それはおよそ200万年前に人類がアフリカ大陸に誕生してから今日の文明社会にいたるまでまったく変わることがない。自然は生命の源泉であり、人間は生きるために絶えず自然と交流し、自然の事物を人間が使用できるように加工しなければならない。だが、人間は蝶が花の蜜を吸い、鳥が空中を飛んでいる虫を飲み込み、モグラが土に穴を掘るように、直接身体的に自然と交流するのではない。人間は言葉を介して自然と交流する。言葉を介して自然と交流するとは、自然の事物を概念で把握すること、すなわち自然を概念化することである。自然の概念化は個々の自然の事物の本質を把握することから出発する。事物の本質は、それがなんであるかという問いの答えとなるものである。しかしこの場合「なんであるか」という問いで問われているのは、それ自体でなんであるかではなく、「人間にとってなんであるか」である。人類の長い歴史において人間にとって最も関心のあるのは直接みずからの生存に関する事柄であった。少なくとも古代ギリシャに自然が純粋なテオリア(観照)の対象となるまで、自然の事物がそれ自体でなんであるかを問う動機そのものが人間にはなかった。自然はもっぱら食べること、寝ること、生殖すること、身を守ること、攻撃することなど、生存を維持する観点から見られた。人間にとって最大の関心は、目の前にある自然の事物が危険なものか安全なものか、食べられるものか食べられないものかなど、直接みずからの生存に関わることであった。自然の事物が人間の生存の維持にとってなんであるかを問うことにより、人間の生存に関わる特徴が弁別され、それにもとづいて事物の本質が把握されて概念化された。
言葉を獲得した人間は生存の必要性に迫られて自然の事物を概念化した。あるいは人間は自然の事物を概念化するために言葉を獲得したともいえる。いずれにしても言葉は人間のみがもつ自然の認識方法である。自然の事物は概念化されることによって特定の種類に分類され、それと同時に他の種類から区別される。その結果、それ自体は個物の集合である自然に種類の網がかけられ、自然全体がさまざまな種類に分類される。それによって人間は自然全体を見渡すことができるようになったのである。
事物の本質は事物の本質的特徴によって構成される。この場合、事物の本質的特徴はいわゆる「客観的特徴」ではなく、人間にとって関心のある特徴である。人間にとって最大の関心はその生存を維持することであり、ある特徴が人間にとって本質的であるか否かの基準は、それが人間の生存にとって重要であるか否か、すなわちそれが人間の生存に関与するか否かである。みずからの生存を維持するという観点から、事物の本質は「人間の生存にとってなんであるか」という問いの答えとなるものである。たとえば木は、「実は食べることができ、切り倒せば木材になり、火をつければ燃えるもの」として捉えられる。生存を維持する観点とは、自然の事物を人間の生存に照らして見ることである。それは自然の事物を人間の生存への関与性において把えることである。
自然の概念化は、自然を概念で把握することである。概念はもともと自然のなかにはなく、人間の頭のなかに作り出されたものであるが、概念の素材となるものは自然のなかに所与として与えられている。たとえば「木」の概念には木と呼ばれる自然の事物が対応する。最初に自然の事物が所与として与えられ、それを感覚が受容する。概念化の第1段階として、事物の感覚特徴から本質的特徴が抽出される。抽出されたいくつかの本質的特徴が綜合されて事物の本質が構成される。概念化の第2段階として、構成された本質に対応する概念の名称が適用されて自然の事物は概念で把握される。
自然の事物が概念で把握されると、それにもとづいて事物同士の関係が言葉によって概念化される。関係の概念も人間の頭のなかに作り出されたものであるが、それに対応するものは自然のなかに所与として与えられている。たとえば人間の目の前に木があれば、木の根や枝の位置は人間の身体を基準として「上」または「下」、「右」または「左」などの空間的概念で把握される。あるいは木から実や葉が地面に落ちるのを見て、「先」または「後」、「速い」または「遅い」などの時間的概念が形成される。空間的概念と時間的概念は、直観によって把握可能な関係を表す直観的概念である。
原因と結果の概念は直観的概念反省された概念として反省的概念である。原因と結果の概念も人間の頭のなかにだけ存在するが、それに対応する事象は自然のなかに見いだされる。自然はかたときも休むことなく変化しているが、それは自然の個々の事象がそれぞれ因果性を発揮するからである。自然の事象はことごとく因果性によって生みだされ、それぞれが原因となり結果となりながら絶えず新たな事象を生み出す。自然はどんな局面を切り取っても多種多様に入り組みながら因果的に生成している。そのなかから特定の局面が抽出されて、本質把握により時間的に先行する事象が「引き起こすもの」として把握され、時間的に後続する事象が「引き起こされたもの」として概括される。その結果、人間の頭のなかに「原因」と「結果」の概念が生み出され、それによって自然は原因と結果の概念によって再構成される。
自然が原因と結果の概念によって再構成されると、自然の事象を観察して、たとえば「木に火をつければ燃える」という経験則が導出された。このような経験則が成立するためには、「木」の概念と「火」の概念が形成され、両者が時間的な先後関係において把握され、さらにその先後関係に「原因」と「結果」の概念が適用されることが必要である。自然の事物の概念と、時間的な先後関係と、それらの因果的な把握にもとづいて、人間は自然との関わりを企図することができた。企図とは、目的を設定し、目的とそれを達成するための手段の連鎖を策定することである。人間は自然を改変するという目的を設定し、その目的を達成するための手段として、次々と道具を生み出した。
2.言葉と道具
道具とは、自然との関わりにおいて自然の事物を加工するための手段である。人間が道具を使って自然に能動的に働きかけるためには、最初に働きかける対象である自然の事物と、そのために道具として用いる事物の本質が言葉によって概念として把握されていなければならない。そのうえで自然に働きかける具体的な動作を原因として、働きかけた結果が予想されているのでなければならない。働きかけた結果を予想することは、対象の概念と道具の概念との関連づけが、因果的な連関において把握されていることを前提とする。因果的な連関を考慮して予想される働きかけの結果は目的である。目的が設定されると、因果連関を考慮して目的を達成するための手段として道具が選択される。それゆえ道具は偶然発見されたものではなく、企図によって発明されたものである。
道具は基本的に延長された身体である。たとえばモグラのように手で穴を掘る代わりに手の延長としてシャベルを使う。人間は他の動物が直接身体的に自然と関わるのにたいして、道具を介して自然と関わる。道具は、鋭い牙や、速い脚や、空を飛ぶための翼などの武器をもたない人間にとって他の生物に伍して生きていくための武器ともなった。人間は他の動物のように身体を武器とする代わりに道具を武器としたのである。現代においては人間と自然のあいだは多種多様な無数の道具や機械やシステムによって媒介されているが、その基底にあるのは太古以来の人間と自然の関わりである。
通説では、人類はあるとき二足歩行を始め、その結果自由になった両手で石や木を掴んで道具として使用するようになり、それによって大脳の発達が促されて言語を獲得したとされている。しかし、道具が発明されるためには、自然の事物を加工するという目的の概念と、それを達成するための手段の概念が生まれていなければならない。その結果、自然の事物を加工する目的を達成する手段として道具が求められる。自然の事物を加工するための手段という道具の概念は、言葉によってつくられるものである。したがって人類の歴史において言葉の獲得は、道具の発明と使用に先行したと考えざるをえない。人類の歴史において言葉の獲得は道具の使用よりも先であるという見解は、言語学者のサピアも次のように吐露している。
「人間の文化的遺産のうちで、火を得るために錐をもむ技術にせよ、石を削る技術にせよ、ことば以外にもっと古くからあった、と主張できるものがあるかどうか、疑わしい。わたしとしては、ことばは、もっとも低段階の物質文化の発達よりもなお先に生じており、しかも、重要な表現の道具である言語が、それ自体はっきりした形をとるまでは、これらの文化の発達は、実は厳密には不可能であった、と信じたい気もちである。」1)
別の通説では、人類は二足歩行ができるようになると自由になった手で道具を使い、その刺激によって脳が急速に発達したとされている。しかし単なる身体機能の変化が脳の急速な発達を引き起こすとは考えにくい。たしかに二足歩行するようになったことで、後足でより大きな荷重を支えることが必要となり、後足が前足(手)より太くなった。手も道具を使うことで、他のどんな動物よりも巧みに指を動かせるようにはなった。だが、こうした身体機能の変化が誘引となって脳が幾何級数的に大きくなったとは考えにくい。人間の脳が急速に拡大したのは、人間が言葉を獲得した結果であろう。言葉によって自然の事物を概念化することにより、自然を観念的に再構成することが可能になった。その結果、人間は自然全体を見渡すことができるようになり、自然の奥行きと広がりは果てしなく拡大した。この拡大した自然の構造に対処するために神経回路が緻密化し、それに伴って脳が拡大したと考えられる。脳容量の増大の大半は前頭葉の急激な拡大によるものだが、ここに言語中枢があることは偶然ではない。
3.技術
技術とは、主体としての人間が客体としての自然に働きかけて自然を改変する能力である。この場合の主体は他の人間と共同する共同主体である。技術は、共同主体によって共有された能力である。しかし、実際に自然にたいして能力を発揮するのは共同主体を構成する個別主体である。共同主体の能力は個別主体の能力を基礎としている。これは能力を発揮する局面だけでなく、能力を形成する局面にもいえる。個別主体は言葉の場合と同様、技術的能力も学習によって獲得する。個別主体としての人間が学習によって獲得した技術的能力を技能と呼ぶ。技能は、共同主体が共有する技術を実際に自然との関わりにおいて運用する能力である。技術が他の人間との共同の成果であるのにたいし、技能は個人の能力の成果である。共同で自然を改変する企図において人間が求められた能力を発揮することができるためには、それに必要な技能を備えている必要がある。そのためにはそれぞれが共同主体によって共有された能力を学習によって獲得しなければならない。
能力はさしあたり潜在力であり、言葉と同様に技術も顕在化してはじめて現実のものとなる。能力としての技術は思想もしくはコンセプトとして顕在化する。思想もしくはコンセプトを具体的に表現したものは、設計書、図面、規格、仕様書などの技術文書である。これらの技術文書にもとづき、道具と機械を駆使して自然に働きかける活動が生産である。生産によって生み出される製品は、能力としての技術の最終的な結果である。生産の全過程は、能力の最終的成果である製品を目的とする企図にほかならない。
学習は、共同体を構成する個別主体が共同主体によって共有された技術を獲得して身につけることである。これにたいして個別主体が考案した技術が、共同主体によって共有されるのは共有化である。自然を改変する個人の技能は、同じ共同体に属する他の多くの人間と共有されることによって共同主体の能力となる。この能力の共有化は、個別主体がもっている能力を他の人間が習得することによってなされる。ある個人の能力を他の人間が習得し、それが広く共同主体によって共有され、一般的に自然に適用されるようになると、その能力が標準(スタンダード)となる。個人が新しい技術を開発する場合は、この標準に達していることが前提とされる。つまり新しい技術を開発する人間は、そのときどきの共同主体によって共有された技術をわがものとしていなければならない。新しい技術はつねに既存の技術を土台にして開発される。どんな天才発明家でも自分一人で技術を一から開発することはないように、新しい技術の開発はそのときどきの共同主体によって共有されている技術を出発点として、その可能性を最大限に活用するのでなければならない。それゆえ技術の共有化にはつねに共同主体が共有する技術を学習するプロセスが先行する。
人間は自然との関わりにおいて共同主体として企図する。この場合、企図とは共同の目的を立て、自然の因果的な諸条件を勘案して目的を達成するために最も効果的な手段を策定することである。企図において人間は共有された技術を適用して自然に働きかけ、その結果自然から相応の反作用を受ける。自然に働きかけ、自然から反作用を受ける共同主体の体験をとおして技術は変容する。具体的にいえば、共同主体は自然に働きかける企図の成果を検証し、その検証結果にもとづいて、技術を自然の因果的な諸条件にいっそう適合するように修正する。それによって技術は企図の目的をより効果的に達成すべく改良される。改良された技術は、それ以後の企図で適用される。その結果、共同主体はあらたな自然との関わりを体験し、その体験にもとづいて技術はさらに改良される。このように共同主体の企図による自然への能動的な働きかけと、自然からの共同主体へのフィードバックをとおして技術は連続的に発展する。これは人間と自然の関わりにおいて作用と反作用の原理にもとづいて進行する循環的なプロセスである。このプロセスを技術発展の縦軸とすれば、能力の共有化と学習は技術発展の横軸である。自然との関わりを企図し続けることをとおして技術は絶えず改良される。改良された技術は共同主体に共有されると同時に、学習によって共同体を構成する個別主体に獲得される。企図の成果の検証、それにもとづく技術の改良、あるいは個別主体の学習などの具体的な場面で、個別的な要因が関与していることはいうまでもない。個人の能力や学習意欲から、機械の故障や気象条件などにいたるまで技術発展のプロセスに影響する要因は無数にある。しかし全体として人間が共同で自然を改変する能力としての技術は、企図の循環的プロセスを縦軸とし、能力の共有化と学習を横軸と発展する。これは人間と自然との関わりのダイナミズムにおいて必然的に進行するプロセスである。
4.言葉と技術
言葉も技術も人間の共同主体の能力である。言葉は意識を表現する能力として人間が他の人間と共同することを可能にする。技術は人間が自然に働きかけて自然を改変する能力として、人間が自然にたいして能動的に働きかけることを可能にする。技術が進歩すれば、それに伴って人間と自然の関係が変化する。そもそも技術は人間と自然の関係を(たとえば人間にとってより快適に)変化させることをめざして技術が開発されたり改良されたりするのである。人間と自然との関係が変化すれば、自然に働きかける共同主体としての人間と人間の関係も変化する。人間を取り巻く状況が変化すれば人間の意識も変化し、それに伴って意識の表現である言葉も変化する。
人間は言葉と技術という能力を駆使して自然と関わる。それは具体的には次のような企図の一連の過程としておこなわれる。
(1)感覚が収集した周囲の環境に関する情報を知性が処理して全体的な連関(目的連関/因果連関)を構想し、それにもとづいて具体的な行動を決定する。
(2)そのさいに感覚による情報の収集と、知性による情報処理の成果を最大限に活用して、最も実現可能性の高い行動を決定して、それを目的として設定する。
(3)さらに自然の因果的条件を勘案して、目的を達成するために最も効果的な技術を選択して自然に適用する。
人間と自然との関わりは言葉と技術を介した意識的活動であり、それは基本的にこのような過程をたどる。なぜなら自然の一部でありながら自然から切り離されている人間は、自然と交流するために自然との関わりそのものを企図しなければならないからである。企図において人間は他の人間と共同する。技術は人間が自然と関わり、自然に働きかける局面で発揮される共同主体の能力である。人間は自然に技術を適用して、植物を摂取するために土地を耕し、種を植え、苗を育て、その実りの成果を刈り入れる。動物を摂取するために、家畜小屋を作って飼育し、あるいは網を編んで魚を捕獲する。生命維持活動をより効率的に遂行するために、森を切り開いて耕地にしたり、広大な原野を柵で囲って放牧場にしたり、魚の養殖場を作ったりする。さらに生産性を高めるために建物や工場を立て、道路を作り、港湾設備を建設する。これらはすべて基本的に自然から与えられた生命を維持するために自然に働きかけて、自然を改変する活動である。
技術は言葉によってコンセプトとして表現される。コンセプトは、自然を改変することを目的として編成された概念の体系である。言葉で表現された技術は共同主体によって共有された能力として、次の世代に伝承される。伝承された技術は文化として後続の世代によって承継される。文化が蓄積されることによって文明が誕生する。人類史の発展はどの局面を切り取っても、人間は自然の一部として、絶えず自然と関わり、自然と同化しなければならないという根本的な事実を基礎としている。
人間は、自然との関わりにおいて自然の改変を企図し、改変された結果を目的として設定し、その目的を達成するために目的連関を策定する。策定された目的連関を実現するために、技術を駆使し、機械や道具を使って自然に働きかける。自然に働きかけた結果として自然から反作用を受ける。自然への働きかけと自然からの反作用の過程で技術は変容をこうむり、企図を重ねるごとに発展する。人間は自然との関わりにおいて絶えず企図し、企図をとおして技術を発展させ、それを言葉によって後続の世代に伝えてきた。その結果人間はあらゆる生物種のなかで唯一文明を誕生させた。人間が進化を続けてきたのは、自然との関わりにおいて言葉と技術を使って不断に企図し、その成果を文化として継承し続けたからである。
1)エドワード・サピア『言語』(安藤貞雄訳)