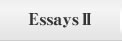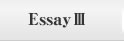翻訳者として生きてきた四半世紀余りを振り返ると、人との出会い、偶然の機会、そしておそらくは時代にも恵まれた半生だったとつくづく思う。私は翻訳の仕事を始めてから、いわゆる「下積み生活」というものはまったくなかった。いわば歌手志望者が新人コールに出場し、そのままデビューしてしまったような格好である。最初から驚くほど多くの依頼が舞い込んできた。それまで本格的な翻訳の経験はないにひとしかったが、仕事を通してこれでもかというほど多くの経験を積んだ。どんな職種でも、駆け出しの時期に「自分はこの世界でやっていけるかもしれない」と思えることほど自信になるものはあるまい。
だが、自信とは裏腹に、これまでの翻訳人生は不安と緊張の連続だったと言っても過言ではない。 たとえば、大きな仕事に専念してほかの依頼を断り続けているとき、「これが終わったら仕事が途切れるのではないか」とか、「いつか自分より力のある若い翻訳者が現れて仕事が減るのではないか」という不安がよぎる。あるいは、書籍の翻訳を引き受けるたびに、「はたして完璧に訳せるだろうか」と気弱になり、着手してからは「納期にまにあわないのではないか」と焦燥に駆られ、どうにか仕上げたあとは決まって自分の能力の足りなさに嫌気がさす。
とはいえ、実際には世の好不況にかかわりなく仕事が途切れた記憶はほとんどないし、どんなに困難な仕事もなんとかやり遂げてきた。だとすれば、あれらの心配はすべて取り越し苦労にすぎなかったのか。結果だけ見ればそうなるが、真実はそうではあるまい。むしろたえず不安と緊張があったからこそ、今日まで続けてこられたのだと思う。さもなければ私はとうの昔に天狗になって自滅していたことだろう。
30年前、およそ翻訳の仕事がどんなものか知らなかった私に、たまたま出会った北欧語サービスセンターの中村さんが言った言葉を思い出す。
「翻訳で食うていこう思うたら技術翻訳ができんとあかん。文学翻訳なんかやろうと思いなはんな。技術翻訳で食えるようになってから趣味でやったらええんや。」
それ以来、無我夢中で翻訳に打ち込んできたが、いつのまにか産業翻訳を基盤にしつつ、出版翻訳も手がけるという形で、中村さんがアドバイスした通りになっていることにわれながら驚く。
思春期は画家になることを目指し、その後哲学を志し、紆余曲折を経ていまは翻訳の仕事を通してそれらに触れている。このような形で自分の人生が実現された幸福に、私自身必ずしも気づいていなかった。作家であれ、画家であれ、芸術家はそのキャリアのどこかで自分の道を見出し、そのときは命を削ってでも創造に打ち込む。翻訳家がそうしてならない理由はない。
朝、誰もいない仕事部屋の窓のカーテンを開け、原稿に向かって一日中黙々と仕事する。日々同じことを繰り返すことができることの幸せ。この静かな創造的生活を来る日も来る日も続けたいと思う。
死ぬ前に自分の人生を振り返ったとき、毎日同じリズムで仕事できた時間こそが、一番幸せだったと思うのではないだろうか。もちろん社会生活を営む以上、生活のリズムがさまざまな要因で乱されるのは避けられない。どれほど変化を避け、機械のように正確に同じ動作を毎日続けようとしても、取り巻く環境は轟音をたてながら凄まじい速度で転変していく。やがて外部の環境がじわじわと私自身の環境を圧迫し、ついには押し潰してしまうだろう。だからこそ人生において「なにもない日」がこのうえなく貴重なものに思えるのだ。
翻訳をしているときの充実感は、他のなににも代えがたい。たとえば好きな音楽を聴きながら、美術書の図版を愛でつつ翻訳する。それは至福の時間と言ってもいい。興に乗ったときなど、自分は翻訳をするためにこの世に生まれてきたのではないかとさえ思う。願わくば残された人生において、誰よりも長く、誰よりも多く翻訳したい、それがいまの私の気持ちである。
(2009年12月1日)