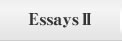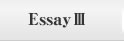翻訳を始めて5年ほどたったころだろうか。毎日ありとあらゆる種類の翻訳を次から次へとこなしていた。そんなとき、ドイツで出版された書籍の一部を訳す仕事が舞い込んできた。グリム童話を扱った学術書である。小さいころから慣れ親しんだ童話の底流に潜む、子供のおどろおどろしい深層心理を、精神分析の手法でえぐり出すという内容だった。読んでいて著者の分析の手腕と哲学的な洞察につい引き込まれた。
産業翻訳の世界でこの種の仕事が舞い込むことはきわめて珍しいが、自分の専攻に近いこともあり、内容を理解するのはさほど困難ではなかった。ところが、いざ訳そうとすると思うように進まない。意味は十分把握していながら、それを言葉に表現できないのは実に歯がゆい。およそ専門とは言えない技術系の文章を、そこそこに訳せるようになっていたのでなおのことだった。しばし自分の翻訳能力に対する懐疑心と焦りに苛まれたのち、私は覚悟を決めた。苛立つ気持ちを抑えつけ、頭の中でまだ分節化されていない理解を一つ一つ言葉に置き換えていった。そしてどうにか最後まで訳し終えたとき、翻訳とは自分の内部で混沌としている言葉を練り固める作業であると深く実感した。
そのころ私は産業翻訳の世界ではちょっとした「売れっ子」だった。さまざまな翻訳会社から毎日のように電話がかかり、引き受けた仕事を上回る件数の依頼を断る状態が続いていた。それでも私は翻訳を一生の仕事にしようとは思っていなかった。といって別の仕事を探していたわけでもない。他人の書いたものを訳し、それが職業になるということが、実感としてピンと来なかったのである。翻訳が好きで、現に翻訳で生計を立てていたにもかかわらず、どこかで翻訳業という職業は「実業」ではないような気がしていたのだ。
しかしこの本を訳したことで、翻訳という職業に対する自分の考えが鮮明になった。翻訳とは、自分の内部の言葉を練り固めること、それを通して自分自身の存在を実感すること-「われ翻訳す、ゆえにわれ在り」-たとえ私が翻訳以外の職業に就いたとしても、このような確かさの感覚を持つことはあるまい。それがどんなに面白い仕事であっても、その確かさがなければ、いつかふとそれは私にとって「虚業」と思えてしまうに違いない、そんな予感がした。
原稿用紙に鉛筆で手書きしていた頃のことなので、訳文も手元になければ原文も残っていない。書名も著者の名前も記憶にない。それからまもなく日本で同じような内容の本が出版されたので、もしかしたらそれに関係した仕事だったのかもしれないが、確かなことはわからない。ただ一つ言えるのは、この本を訳したことがきっかけで、私は好むと好まざるとにかかわらず一生翻訳を職業として続けるだろうと確信したことである。
(2009年10月1日)