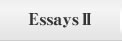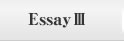電話帳をたよりに電話をかけまくった翻訳会社のなかに「北欧語サービスセンター」があった。翻訳会社というより個人で営む翻訳事務所で、スウェーデン語・デンマーク語・ノルウェー語など、北欧の言語を専門に扱っていた。その中にドイツ語も含まれていたので、私は「ぜひ一度伺いたい」と頼み込んだ。翻訳の仕事の現場というものを一度この目で見てみたかったし、あわよくばドイツ語の仕事を少しでも回してもらえないか、という淡い期待もあった。そうして何度もしつこく電話したあげく、ある日ついに強引に押しかけた。
当時、北欧語サービスセンターは渋谷のマンションの一室にあり、所長の中村一(はじめ)氏が一人で切り盛りしていた。私と顔をあわせるなり、中村さんは関西弁でまくし立てた。
「翻訳で食うていこう思うたら、技術翻訳ができんとあかん。文学翻訳なんか、やろうと思いなはんな。技術翻訳で食えるようになってから、趣味でやったらええんや。」
電話での「市場調査」で、翻訳市場に出回っている翻訳は技術系のものが大半を占めるらしいということは分っていた。しかし、なにしろ生まれついての文科系人間、どこかに自分に合った仕事があるのでは、という甘い幻想を捨てきれずにいた。が、中村さんのこの言葉で完全にふっきれた。
部屋の本棚には、辞書やファイルがぎっしりと並んでいた。中村さんいわく、技術翻訳をやるには専門の辞書を揃えねばならない。英語以外の言語、たとえばドイツ語を翻訳するには独英辞典も必須だ。まず独英辞典で英語の訳語を調べ、それから英和辞典なり日本語の専門辞典なりで日本語の意味を調べる。いわゆる「第二外国語」の技術翻訳の基本中の基本ともいうべき手順を私はこのとき初めて知った。
中村さんは大阪大学の法学部を卒業後て、スウェーデンに留学し、世界的な工具メーカーであるサンドビック社にしばらく勤めたあと、帰国して翻訳事務所を立ち上げた。一人で北欧の主要言語をすべてこなすので重宝がられ、当時すでに多忙を極めていた。
私にとって中村さんと出会えたことは、翻訳者の仕事場をじかに見ることができたというだけでも、大きな収穫だった。仕事場といっても原稿用紙に手書きしていた時代のこと、今日のようにパソコンがあるわけではなく、FAXもまだ市販されていなかった。多数の辞書と資料を揃え、隣室にはベッドを置いて24時間仕事できる体制を作る。それを目の当たりにしたことは、百の講釈を聞くよりインパクトがあった。
「翻訳はええよ。会社みたいに上司に気つかわんでええし、嫌なこと我慢してやる必要もあらへん。好きなときに働いて、好きなときに休む。仕事の合間に一杯やっても、誰にも文句言われへん。」
私と中村さんは初対面で意気投合し、その後もちょくちょく会っては渋谷界隈を飲み歩いた。
あれから30年近く、中村さんが病気を得てからは一緒に飲むこともなくなったが、いまでも時折思い出してはお互いに電話をかけ合い長話をしている。
(2007年8月20日)