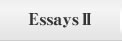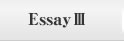かつて翻訳の受け渡しは、通常すべて速達郵便で行なっていた。大量のときは宅配便で送り、特に急ぎの場合はバイク便を使った。バイク便は料金こそ高いが、都内ならどこでも1時間以内に届けられるため、私も仕事を納期ぎりぎりに仕上げて納めるのに重宝した。ファックスも使いはしたが、受け渡しは基本的に原稿の枚数が少ない場合に限られ、あくまでも補助的な手段にとどまった。
1990年頃からパソコン通信で納品するのが一般的になり、郵便や宅配を使うのはむしろ例外となった。さらに1995年頃からはインターネットの電子メールがパソコン通信に取って代わった。やがて翻訳者が翻訳会社に納品するだけでなく、翻訳会社からも翻訳原稿が電子メールの添付ファイルで送られてくるようになった。大部分はワードファイルで、エクセルやパワーポイントの場合もあった。今でこそ珍しくもなんともないが、初めて電子メールで原稿が送られてきたときは少なからず驚いた。それは日本を含む世界中の企業・翻訳会社・翻訳者が、同じ文書作成ソフト、すなわちマイクロソフト社のOfficeを使うようになったことを意味していたからである。
当初は、メールで送られてきたファイルを自分でプリントアウトするのが面倒なので、翻訳会社に印刷したものを別途郵便か宅配便で送らせていた。しかしまもなくほとんどの翻訳会社が電子メールで原稿を送るようになったため、私も諦めて自分でプリントアウトすることにした。
はじめのうちは電子メールで送られてきた原稿をしぶしぶプリントアウトして作業していたが、あるときワード原稿に上書きすれば効率的に翻訳できるのではないかと思いついた。実際、長いものなら、たとえば同じ訳語を100回入力しなければならないところを1回の一括変換ですむ。こうして初めて上書きで仕上げた翻訳を納めたときは、どこか手抜きをしたようで後ろめたさすら感じた。
そのうち翻訳会社の側から上書きを指定するようになった。上書きであれば原文のレイアウトを生かせるため、翻訳者から送られた翻訳を編集する手間が省けるからである。翻訳者側でも上書きすることで時間当りの処理量が増える。そのため昨今の翻訳業界では、翻訳作業のはほとんどが上書きで行われている。
こうして見ると、上書きは良いことずくめのようにも思えるが、実は大きな陥穽がある。
もとより外国語と日本語は一対一で対応するものではない。文章全体を通して1つの語にさまざまな訳語を当てることで、原語の意味に肉薄するのが翻訳である。したがって同じ語にどれだけ多様な訳語や言い回しを当てているかが、良い翻訳のバロメータの一つとなる。しかし、原稿に上書きする場合は一括変換した訳語をついそのまま使ってしまいがちである。そうしてできあがった翻訳は、ニュアンスの幅を欠いた、平板なものにならざるをえない。
さらに、翻訳者にとって命取りともなりかねないのは、上書きによって原文の一語一語と格闘する意欲が失われることだ。それはとりもなおさず翻訳能力の停滞、ひいては低下につながる。変換効率と言語表現は、どうやら相いれないもののようである。
(2009年5月25日)