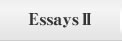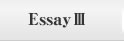インターネットが一般社会に普及し始めたのは1995年である。この年に発売されたWindows95は、ウェブブラウザとして「インターネットエクスプローラー」を標準搭載していたため、誰でも世界中のウェブサイトを閲覧できるようになった。
当時はダイヤルアップ接続だったため、ウェブサイトを検索しようとするたびに、いちいちプロバイダーにダイヤルしなければならなかった。パソコンからは「ジー、ジジジー、ジジー」とダイヤル音が聞こえ、さらにプロバイダーを呼び出してから接続されるまでの間も「ジーーー」と鳴り続けた。これらの時間はすべて通話料として請求されるため、電話代が驚くほどかさんだ。
2000年頃からADSLなどのブロードバンドが始まり、接続が高速化するのと並行して料金定額制が導入された。利用時間に応じて設定された一定額を払えば、その範囲内で何度でも検索できるようになったのである。さらにブロードバンドの主役がADSLから光ファイバー通信へと移行すると、インターネット接続は一段と高速化し、価格も下がった。
インターネットが登場する以前、翻訳者はいろいろな分野に対応するために、語学関係の辞書をはじめ、さまざまな分野の専門事典のほか、雑誌や新聞の切り抜き、商品カタログ、パンフレットなど、ありとあらゆる資料をそろえておく必要があった。しかも、それらはいつでも素早く参照できるように本棚に整理しておかなければならない。資料が増えれば本棚も増え、そのスペースを確保するのに苦労する。私の場合は、本棚が部屋に入りきらなくなったので、押入れを改装して書棚にした。
インターネットが普及したことにより、あらゆる分野の最新情報を手軽に手に入れられるようになった。しかもパソコン1台で済むので、本棚のスペースも不要である。というわけで、ほんの一昔前にくらべて翻訳者を取り巻く環境は激変した。では、翻訳の仕事がパソコン1台あれば済むかと言うと、決してそうではない。
たとえばある翻訳の仕事で出てくる専門用語をインターネットで調べ、半分程度カバーできたとしよう。その場合でも残り半分の用語の意味を調べるには、どうしても専門辞典が必要である。このとき専門辞典を持っているかどうかで翻訳の質が決まる。ありていに言えば、辞典を買うか買わないかが、翻訳者の優劣を大きく左右するのである。しかし、半分はインターネットで済むのに大枚払って買うのは抵抗がある。その意味では、翻訳者にとって辞典類を購入する心理的ハードルは一昔前より高くなったと言えるだろう。
実際、「インターネットで相当調べがつくのに」「せっかく買ってもそのあと二度と使わないかもしれないのに」「そもそも翻訳者としてものになるかどうか分からないのに」辞書や辞典に投資することはできない、と言うかもしれない。確かに辞書や事典を買ったからといって、翻訳者としてものになる保証はまったくない。だが、買わなければものになることは絶対にないということは保証できる。
(2009年5月20日)