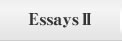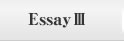あるとき翻訳会社からドイツ語で書かれた地質工学の論文の翻訳を依頼された。発注元は清水建設。翻訳枚数にして40ページほどだったが、見たことも聞いたこともない地質学関係の専門用語がびっしり詰まっていた。日本語とドイツ語の地学辞典や土木辞典など関係ありそうな辞典類を総動員して一つ一つの用語の意味を調べた。それでも適当な訳語が見つかったのはほんの一部で、ほとんどは既存の専門用語から推察して自分で訳語を案出するしかなかった。こうして四苦八苦した末、なんとか訳しおえて納品にこぎつけた。
翻訳を納めてから1週間ほどたって翻訳会社から電話があり、先日納めた翻訳のコピーは取っていないかと聞かれた。原稿用紙に鉛筆で手書きしていた時代なので、いったん納めたら手元にはなにも残っていないし、よほどのことでもない限りコピーを取ることなどない。わけを尋ねると、先日の翻訳は客先の担当者が現場に送ったが、どこかで紛失してしまったらしい。エージェントでもコピーを取っていないので、再度料金を払うので同じ原稿をもう一度訳してもらいたいという。いまなら翻訳したファイルを電子メールで送るので、別にコピーを取らなくても手元にファイルが残る。途中ファイルがどこかに紛れこんだからといって、同じものを最初から訳し直すことなどありえない。
今回の仕事は技術翻訳としては超難物の部類に属するので気が進まなかったが、断れば先方が困るだろうし、1週間前に訳したばかりだから少しは楽だろうと思って引き受けることにした。ところが実際にやってみると、頭のなかにる訳語は一つとして残っておらず、再び辞典類を総動員してすべての用語を同じ手順で調べるはめになった。翻訳に要した時間も前回とほとんど変わらない。なんという非効率! あれほど苦労して調べあげた訳語をどこかに書き留めておけば、こんなに苦労せずにすんだはずだ。これからは翻訳に出てきた専門用語は書き留めることにしよう。そう決心して、自家製の専門辞書を作ることにした。
普通のノートでは使い勝手が悪かろうと、コクヨのフォルダーと26穴のルーズリーフをまとめて買い入れた。翻訳するたびに重要な単語や難解な用語をノートに書いてはフォルダーに綴じていく。あとで調べるのが目的だから、フォルダーはできるだけ細かく分けることにした。たとえば「土木」として1冊にまめるのではなく、「ダム」「橋梁」「トンネル」など、アイテムごとに1冊を当てる。こうして仕事をするたびに新しいフォルダーを作成し、あるいは書き加えていくうちに、その数は200冊ほどになった。
これだけ作るのにかなりの時間と手間をかけたが、それに見合う効果があったかと言うと、残念ながらまったくと言っていいほどなかった。翻訳しながら必要と思われる用語を出てきた順に次々と書き足していくから、数が増えれば増えるほど目当ての単語を探し出すのに苦労するのである。そこで途中から、用語をできるだけアルファベット順に配列するように工夫したが、手書きのことゆえおのずと限界がある。結果としてかなりの数の単語と訳語を収集しながら、それらをあとで調べることはほとんどなかった。
そうこうしているうちにワープロが登場した。ワープロなら単語をアルファベット順に並べたり、あとから追加や変更したりできる。そこでメインに使うデスクトップの傍らにラップトップを置き、翻訳作業と並行して辞書を作成することにした。こうなると手書きの辞書の方はますます使わなくなる。こうして約200冊の自家製辞書は活用されることなく本棚の一段をびっしりと占めて長い眠りについた。それから何年か過ぎたある日、それらのフォルダーはまとめて廃棄された。
いまから思えば、なんとも無駄な労力であったが、これも「古き良き時代」のエピソードと言うべきか。
(2007年10月25日)