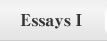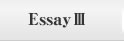VII
旧約の神は、みずから創り出した多種多様な生き物たちを見て「よし」とされた。それは生き物の存在が肯定されたことを意味する。生き物の存在はそれ自体で肯定されている。神は他の生き物と同じように人間も個体として創り出した。しかし人間は知恵の実を食べて個となった。ここで、個とは代替不可能の謂いである。個体の本質は代替可能性にある。人間も個体としては代替可能であるが、同時に個であることによって代替不可能な存在でもある。この代替不可能の一点で人間はまさに神と同等の位置に立つ。だがその代償として人間は神の怒りをかい、生の楽園から追放された。その意味するところを敷衍すれば、人間は知能が発達して言葉を獲得した。言葉によって人間は自然を対象化するとともに、自分自身をも対象化した。その結果、人間は私=自我を自覚し、みずからを代替不可能な個として認識した。そして人間は自然にたいして距離をおくと同時に、内なる自然である生からも離反した。人間は代替不可能な個となる代償として、みずからの生と疎遠になった。本来、生の自己目的において生はそれ自体で肯定されているが、人間は生から離反することにより生の自己肯定から見放された。こうして人間は生を喪失した。
人間は個体としてはその共通の特徴のゆえに生物種に属するが、個としては生物種を超え出ている。というのは、自分であることの意識としての個は共通の特徴によって括ることができないからである。生物種に属する個体と自分自身である個のあいだにある裂け目は、人間の存在を根底で規定している。このことは個体と個の特性の決定的な差異に明確に現れている。個体は共通性のゆえに他の個体と代替可能であるが、個は個別性のゆえに他のいかなる個とも代替不可能である。個の個別性は、根本的に自己意識にもとづいている。個はその自己意識のゆえに自己でない個を代替することもできなければ、自己でない個によって代替されることもできないのである。
生は自己目的を完遂するために代替可能な個体を必要とする。なぜなら代替可能な個体にしてはじめて生は個体から個体へと生き続けることができるからである。もし個体が代替可能でなければ、生は連続的な移行がかなわないため、現在体現している個体が死んだ時点で消滅する。代替可能な個体のみが生の連続性を保証するのである。代替可能性は生の自己目的が完遂されるための前提である。人間も生の自己目的に規定されて他の生物と同様に個体としてこの世界に生まれる。しかし個体であると同時に個として生まれた人間は、生の自己目的と完全に一致することはない。というのも生の自己目的が個体にたいして代替可能性を求めるのにたいし、個は代替可能性の否定を本質としているからである。人間は個であることによって個体から離反し、それによって生との一体性から疎外されている。そのために人間は根本的に生の自己肯定を拒まれている。この個体と個のあいだの裂け目は人間存在の宿命であり取り消すことができない。<身体に包まれた心>に対応させていえば、個は個体のなかにあって個体を住処としながら、どこまでも個体の代替可能性から逃れようとする。そのために人間はけっして生の自己肯定のうちに安息できないのである。
生の自己肯定から見放されて生を喪失した人間は、生を回復するためにどうにかして自己の生を肯定しようとする。そのために人間がみずからに突きつける問いは、「人間はいかにして現に生きていることを肯定できるか」である。生の自己肯定からの疎外を補償するためには、現に生きていることを肯定することができなければならない。だが、それは生を直接的に肯定することではありえない。もともと人間が生の自己肯定を拒まれていることから出発しているのであるから、生を直接肯定することはできない。人間が生の喪失を補償する唯一の方法は生の直接的肯定ではなく、意味を介する肯定である。それは現に生きていることに意味を与え、それによって人生を価値あるものと認めることである。意味は目的によって規定される。設定した目的が達成されることによって意味が満たされる。したがって生きる目的を設定し、その目的が達成されたとき、現に生きていることは有意味なものとなる。それとともに生きていることに価値が認められて生が肯定される。
人間が生きるのは他人の人生や人生一般ではなく、つねに自分の人生である。人間はそのつど自分固有の人生を生きる。「人間はいかにして現に生きていることを肯定できるか」の問いを検証できるのは、ただ自分の人生においてのみである。そこでこの問いを自分の人生に引き寄せて追求すると、それはより個人的な、それゆえより切実な問いに収斂する。その問いとは人間なら誰もが人生で一度は発する究極の問い、すなわち「自分はなんのために生まれてきたのか」である。この問いで問われているのは生きることの目的、すなわち自分の人生の目的である。この問いはすべての人間に終生重荷としてのしかかり、誰もそれを振り払うことはできない。明瞭に意識するとしないにかかわらず、人間は誰もがつねにこの問いをみずからに問いかけている。人は往々にしてこの問いから目をそらし、まるで問いそのものが存在しないかのように振る舞う。だが、そのような振る舞いのなかにこそ、この問いが絶えずそれから目をそらし続けるものとして見え隠れしているのである。
本来、目的は自己を超え出ることによって設定され、あるいは目的を設定することにおいて自己を超え出る。しかし、生はそれ自体を目的として完結しており、生そのものを超え出ることはなく、生の外に設定される目的もない。生きる意味は生きる目的が達成されることによって満たされる。生きる目的が立てられないところに生きる意味は存在しない。生の自己肯定に安住している人間以外の生物にあっては、生きる目的が立てられることはなく、したがって生きる目的が達成されることもなければ、生きる意味が満たされることもない。生物には生きる目的が生の自己目的としてすでに与えられており、生きることはそれ自体で肯定されている。生の自己目的に貫かれた生物には、死もなければ死の恐怖もなく、したがって死にまつわる疑念や絶望もない。
人間が他のいかなる生物とも異なるのは、人間は自分が死ぬことを知っている点である。人間が人生を生きるうえで抱えるすべての問題は究極的には死に関連している。人生に疑問を抱き、人生の意味を問い、人生に絶望するのも、人間は死すべきものであり、しかも人間自身がそのことを知っていることに淵源する。しかし人間が生の自己目的から逸脱するのもこの死の自覚によってである。人間はまさに死を恐れ、死を嘆き、死に絶望することによって、生の自己目的による支配を脱している。生の自己目的による支配とは、みずからの生が生の自己目的に貫かれ、それゆえ生の自己目的に盲目的に服従することである。それは生と死についていかなる疑念も抱かずに、ただ黙々と生まれ、生き、死んでいくことである。これにたいして人間は死を恐れ、死を嘆き、死に絶望することによって死に抗う。人間は死に抗うことで、生の自己目的による支配の手から逃れる。生の自己目的による支配を免れている限りで人間は自由である。この自由のゆえに人間は生の自己目的に盲目的に従うかわりに、みずからの意志で生きる目的を立てることができるのである。
自然界で生を体現するのは生物であり、生が生きるのは生物の個体においてである。個体において生の主体性は、生存本能と生殖本能として具現化される。本能は個体を突き動かし、個体は本能に従って生きることによって生の自己目的を遂行する。人間も生物である限り本能を原動力として生きている。本能がなければ、生物として生きる原動力を失い生命を維持することができない。しかしまた人間は生の主体性に主導された生命活動を土台として、同時に人間の主体性も発揮する。生の主体性は人間を含む生物では本能行動として発現するが、人間の主体性は企図として発揮される。
生の自己肯定を拒まれた人間がみずからの生を肯定するためには、現に生きている人生に意味を与えなければならない。人生に意味を与えるには、生きる目的を達成する必要がある。生きる目的を達成するためには、その前提として生きる目的を立てなければならない。生の自己目的から逸脱した人間には、他の生物のように生きる目的が生の自己目的としてすでに与えられてはいない。だが、それと引き換えに、生の自己目的に支配されていない人間にはみずから生きる目的を立てる自由がある。生きる目的を立てるとは、人生を企図することである。人生を企図するとは、生きる目的を達成するために生きる目的そのものを立て、その目的の実現に向けて目的連関を策定することである。
人生は人間がこの世界に生まれて不断に積み重ねる体験の過程である。この世界に生まれ落ちてから現在にいたるまでの人生を俯瞰すると、人生は1本の軌跡のように見える。それは生まれてこのかたそのときどきの環境において世界の構成要素と関わり続けて現在に収斂する過程である。現在は過去の累積の帰結であり、自己はこの世界に生まれて以来積み重ねてきた体験の帰結である。
自己がこの世界に生まれて以来現実とさまざまに関わりながら、現在にいたる推移をたどってきたという事実は絶対くつがえすことができない。自己は人生における体験の累積の結果として、肯定的なことも否定的なことも含め、現にあるとおりのものであるほかはない。現にあるとおりの自己はこれまで積み重ねてきた体験の必然的な帰結であり、これに代わるものはない。自己の歴史は修正もやり直しもきかない。人生は、紆余曲折を経ながらも現にあるようにならざるをえなかったという限りで必然的である。 人生は別のようでもありえたはずであるが、実際には現にあるようにならざるをえなかった。人間がこの世界に生まれてこのかた体験してきたことのすべてが、現在ある自己を現にあるとおりのものにしているのである。
人間がこの世界に生まれることは根拠のない偶然であり、人間がこの世界に生まれる理由は存在しない。人間はただ偶然この世界に生まれる。そこには根拠もなければ、根拠によって規定された必然性もない。しかしこの偶然性の大海原にあって、これまでたどってきた人生はかくあるようにしかなりえなかったという限りで必然的である。人生は別のようでもありえたが、実際には現にあるとおりのものであるほかはなく、それはは変更できない事実である。人生をその必然性において受けとめるとき、その必然性を根拠としてこれから進むべき人生の軌道が開ける。その軌道はひとえにこれまでの人生の軌跡を引き継いでいる。ただ異なるのは、これまでの人生の軌跡が修正もやり直しもきかないのにたいし、これから進むべき人生の軌道は刻一刻と選択できることである。これから進むべき人生は、そのつどの現在における選択をとおしてあらたに自己を創り出す過程である。
これから進むべき人生の軌道は、これまでの人生がそれに向かって進んできた、しかし自分自身にも必ずしも明確ではなかった目的に向かって続いている。それはこれまでの人生で数限りない試行錯誤を繰り返しながら策定された無数の目的連関の終点に位置すべき人生の目的である。それは人間の頭上に君臨する超越的目的ではなく、この世界に生まれて以来書き連ねてきた自己の体験の歴史に由来する内在的目的である。それはあの「自分はなんのために生まれてきたのか」という問いに唯一答えることのできる目的でもある。
人生は人間が生まれて以来、積み重ねる体験の軌跡である。人生には成功することもあれば失敗することもあり、ときには脇道にそれることも過ちを犯すこともある。この世界に生まれてこのかた体験した無数の出来事や、数多くの偶然の出会いや、大小の成功と失敗から織りなされた人生は、もはや変更もやり直しもきかない。自分の人生は望むと望まざるとにかかわらず、現にあるとおりのものであるほかはない。肯定的なことも否定的なことも含めてみずからの過ぎし人生をかくあるようにしかなりえなかったと受けとめるとき、人生は宿命という必然性を帯びる。
これまでの人生の軌跡を宿命として受けとめるとき、その軌跡の行く末に見える人生の目的は、これまでの自分の人生で策定された無数の目的連関の終着点に位置する。それは人間の頭上に君臨する超越的目的ではなく、この世界に生まれて以来積み重ねてきた個人史に由来する、それゆえ内在的な目的である。それはあの「自分はなんのために生まれてきたのか」という問いにたいする唯一可能な答えである。人はこの目的に向かって企図することによって、これから進むべき人生の軌道を歩む。生きることの意味を見いだし、みずからの人生に価値を認めることで人生が正当化され、人間の内部で生からの離反が生の自己肯定に転化する。自己肯定の状態において人間は生を回復し、生それ自体が肯定の証しとなり、現に生きていることが端的に「よし」とされる。そのとき旧約の神が微笑む。
(2015年3月)