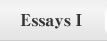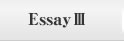VI
人間はこの世界に生まれて以来の体験の積み重ねの結果として現在に存在している。人間は生まれてこのかたそのつどの状況でさまざまな局面と関わりながら体験を積み重ねる。人間と世界との関わりのなかで、主体の諸特性が体制化されて能力として形成される。主体の能力は世界と関わる過程で発揮され、状況との相互作用をとおして絶えず発展する。主体の能力が発展するのにともない世界は奥行と広がりを増し、それに対応して人間の体験が深化する。主体の能力の発展と世界の深化が絡み合うなかで体験は絶えず累積される。しかしこの体験の不断の累積は永久に続かない。なぜなら死によって終止符が打たれるからである。誕生以来休むことなく続けられてきた体験の累積は死によって途絶する。死の瞬間に累積された体験のいっさいの内容が、誕生以来培ってきた全能力とともに忽然と消える。
あらゆる事象がこの世界のなかで起こるように、死もこの世界で起こる出来事である。死というものの存在は、この世界で経験をとおして知られる。とりわけ一緒に暮らしている家族が病死したり、高齢の親戚が老衰で他界したり、親しい友人が事故で落命したりしたときに、死は強烈に経験される。子供は死の経験を重ねるにつれて、生きているものは必ず死ぬことを次第に理解する。身の回りで動物や昆虫の死を目撃し、家族や親族との死別に遭遇し、あるいは本を読んで歴史に登場するどんな英雄も最後は死を迎えたことを知って、命あるものにとって死は避けられないものであるという認識をもつ。死が避けられないだけでなく、生きられる年数も生物の種類によってほぼ決まっている。同じ種に属するすべての個体が正確に同じ年数で死ぬわけではないにしても、標準的な寿命を大幅に越えて生きながらえることはない。寿命まで生きて死ぬのであれ、そこまで長生きできずに病気や事故で死ぬのであれ、生きているものにとって死は絶対に避けられない。いうまでもなく子供自身も死を免れることはできない。死というものを知るにつれて、死にたいする不安や恐怖心が芽生える。家族をはじめとして親密な人間の死を考えると思わず悲しくなる。自分もいつか死ぬということにそこはかとない不安を覚える。自分が死んでこの世界から消えてなくなるという事態は理解を越えている。
死が恐怖や不安を喚起するのは人間だけである。人間の場合は死そのものの観念が恐怖を喚起する。動物には死の観念がないから、死にたいして不安や恐怖心を抱くことはない。もちろん動物は天敵や捕食者を恐れ、それらの接近をきわめて敏感に察知して、逃げたり防御の態勢をとったりする。しかし動物はみずからに危害を加えるものを恐れるのであって、死そのものを恐れることはない。動物にあるのは現在における直接的な感覚、この場合はみずからに加えられる攻撃にともなう苦痛である。人間は反対に死そのものを恐れ、死が苦痛をともなうか否かは二次的である。重病にかかって手術をしなければ助からないとき、人間は死を回避するために手術の苦痛を甘受する。
死は生物学的には生命機能の停止である。生命機能の停止は、病気か、犯罪を含む事故か、老化のプロセスの終末として起こる。人間も人間以外の生物も病気か事故か老化が原因で死ぬ。地球上に生命が誕生して以来、人間にとっても人間以外の生物にとっても病死か、事故死か、老死のいずれかで死ぬことはいささかも変わりない。ただし、人間に限っていえば自殺によって死ぬこともある。自殺とはみずからの意志で死ぬことであるから、安楽死も他人の手を借りた自殺である。自殺も安楽死も生命機能を停止させるという点では生物学的な死である。しかし生物学的な死をみずから招こうとするのは人間を除いてない。自殺の誘惑に駆られるのは人間だけである。人間がみずから命を絶とうとするのは、ひとえに人間の側の事情による。それは死という出来事が、人間にとっては単に生物学的な死にとどまらない意味合いをもっているからである。人間にとって死が生物学の範囲を超えた意味合いをもつことは、人間と人間以外の死すべきものとの本質的な差異を示唆する。
死はなによりも親しい者との死別として経験される。家族、親戚、友人はいうに及ばず、犬や猫などのペットでも、それまで長く共通の時間を過ごしてきた人間や動物が死んでしまえば二度と再び会えなくなる。親しい人間が地球の裏側の土地に永住したり、異国の地で終身牢に入れられたりするような場合も、一生会えなくなるという点では死別と変わらないように思える。しかしそれらは死別ではなく離別である。離別の場合は当人がこの世界からいなくなるわけではなく、依然としてこの世界に存在している。離別とは、ここにはいないという意味で「不在」である。そもそも不在は、不在の主が存在していることを前提としている。誰かがここにいないということは、別の場所にいるという事実もしくはその推定のうえに成り立つ。つまり不在とは存在の一様態にほかならない。だが、死の経験をとおしてどんな不在とも異質の別れがあることを知る。死ねば地球の裏側はおろか、宇宙の果てにも存在しなくなる。それは不在ではなく「非在」である。ここにいないのではなく、どこにもいない。端的にこの世界から消え去るのである。この事実を受け入れるのは、けっして容易ではない。死が恐ろしいのは、親しい者と永遠に別れなければならないからである。その恐ろしさは死にゆく者にとっても、あとに残される者にとっても同じである。死が目前に差し迫っていなくとも、いつかそういう日が来るという確信が身震いするほどの恐怖を呼び起こす。それは死の観念をもつ万人に共通の恐怖である。そのため人間は人知の限りを尽くして非在を打ち消しにかかる。死者はこの世界に存在しなくなっても、どこか別の世界で生きているのだ、と。こうして太古よりこのかた地球上のいたるとことで「来世」、「天国」、「冥界」、「あの世」、「彼岸」など、死後の世界にまつわるありとあらゆる物語が編み出されてきた。それらはすべて非在を不在に転化しようとする絶望的な努力の跡である。
穏やかに他界した死者の顔を見ると、生きていたときの顔といささかも変わらない。棺に納められた死者は目をつむり、顔からは血の気が失せて体は冷たくなっているものの、きのうまで生きていた故人が厳としてそこにいる。しかし棺を取り囲む遺族たちは、故人がそこにいながら絶対にそこにはいないことを知っている。そこにいるのは故人の身体にすぎず、<身体に包まれた心>はそこにはない。しかし心がなければもはや身体でさえなく肉体=物である。死後時間がたつと腸内に生息している細菌や微生物が活発化し、肉体=物は腐乱して形態が変わる。そのためできるだけ速やかに死体を土に埋めたり、焼却したりして人の視界から消し去る必要がある。肉体の方はこのように物理的に処理すればいいが、問題は心である。心は肉体が死ぬと同時に消え失せる。が、それで心の問題はかたづくかというと、けっしてそうではない。なぜなら心が肉体の死とともに瞬時にして消え失せるという事実こそ、人間にとって最も受け入れがたいことだからである。それまで生きて周囲の人や事物と交わり活動してきた人間が、死によって突然いなくなる。死ぬのは肉体であるが、肉体は消滅しない。消滅するのは肉体ではなく心である。心が消滅するとは、故人の記憶に保存されているすべての体験が、誕生以来体験の積み重ねによって形成された能力もろとも完全に消え失せることである。死は故人の歴史の途絶である。死が耐えがたいのは、心が消滅することにより、生まれてからずっと書き続けられてきた自己の歴史が途絶えることである。そのため人間は心の消滅を受け入れることに激しく抵抗する。たとえ肉体は死んでも、心だけはなんとか生きながらえさせたい。そこで心は肉体の死とともに消え失せたのではなく、故人の体から魂となって抜け出して、別の世界に行ったことにする。そのために人が死んだら、魂を別の世界に送り出すための手の込んだ儀式をおこなう。意味ありげな葬具で飾りつけられるだけ飾りつけ、ありとあらゆる工夫を凝らして荘厳な雰囲気を醸し出し、神秘めかした経文が朗唱される。だが、本当にこの世界とは別の世界があって、人間は死んだらそこに行くことが決まっているならば、これほど手の込んだ仕掛けをあつらえる必要はないはずである。この世界とは別の世界を懸命に演出するのは、死者を別の世界に送り届けるためというよりは、むしろ残された者に死者は別の世界に行ったと信じ込ませるためである。それは残された者が、いずれ自分も死んだらそこに行けるとみずからを納得させるための手続きでもある。
人間がこの世界に生まれるのは、生物として生れることであり、そのメカニズムは生物学の対象である。死そのものは、この世界に誕生した肉体が成長と老化のプロセスを経て生命機能を維持できなくなるという純粋に生理学的な現象である。そこには不明なことはいっさいない。医師は呼吸と脈拍と瞳孔を調べて、あっさり臨終を宣告する。だが、人間にとって死が問題であるのは、身体が死ぬとそれに伴って<身体に包まれた心>が消え失せることである。<身体に包まれた心>が消え失せるとは、心の主語である私が消滅することである。私はこの世界に生まれることにより、<いま・ここ>に立ち現れて私自身に顕現する。すなわち私は<いま・ここ>で私自身と出会う。私が私自身と出会うことがすべての始まりである。私を起点として私の外が広がり、そこに世界の光景が繰り広げられる。それは私が生まれて以来いっときも休むことなく関わり続ける世界である。私はそのつどの状況で世界と関わる。その世界は、<いま・ここ>を起点とするパースペクティヴに繰り入れられる私の世界である。しかし私が死ねば、私の外は永久に閉じて二度と開くことはない。それに伴って私の世界も消え去る。きわめつけは、この世界に生まれて以来、私のあらゆる活動の主語としてつねに私に顕現してきた私もいなくなる。他のだれでもない私が私自身に二度と会えなくなるのである。心を魂に見立てて別の世界に救い上げようとする懸命の努力が、死んだら私が私自身と会えなくなるという事実が人間に与える衝撃と恐怖を逆照明している。
死はあくまでも経験的な出来事であるから、死の不可避性は先天的に知られていない。人間の運命を支配する死の不可避性は、この世界に生まれたあと、それもかなりの年月を経てようやく知ることになる。それは契約を結んだあとで、契約書のどこにも書かれていない重大な事項が告知されるようなものである。死が避けられないことを知らされたとき、差し迫った問題は現に生きていることをいかに正当化できるかである。人間が自己の生を正当化できるためには、生は意味あるものでなければならない。そこで人間は自分はなにゆえ生まれてきたのかと問う。自分が生まれてきた理由がわかれば、人生の目的もわかり、人生に意味を見いだすことができるだろう。しかし人生の契約には生まれてきた理由はどこにも書かれていない。だから、死によってこの世界に生きている意味が危うくされるのを防ぐためには、生まれる前までさかのぼって契約を見直すしかない。契約を見直すとは、この世界に生まれてくる理由を契約の条文に書き加えることである。生きる意味を生まれる前までさかのぼって求めようとすれば、「神」を引き合いに出すほかはない。神は人間の生を越えた超越的目的である。宇宙の摂理を定める神なればこそ、人間が生まれて死ぬことの意味を与えることができる。しかしそのような超越的目的は認識によってはとらえられず、ただ信仰によってのみ到達できる。こうして信仰と引き換えに生まれてきた理由と、生きる目的と、死後の行き先を書き記した契約が手渡される。人間はこの契約を遵守して、ひたすら信仰心を高めようとする。この必死の努力の根底にあるのは、人間の生きる意味への渇望である。知恵の実を食べた人間は、もはやパンだけで生きることができない。パンが満たすことができるのは身体の飢えだけである。心の飢えを満たすことができるのは意味しかない。
人間にとって死が恐ろしい第五の理由は、意味を追い求める懸命の努力にもかかわらず、死によっていっさいの意味が無化されることである。人間は必ず死ぬのであれば、生きるための努力はすべて無駄になるのではないか。どれほど努力をしても、最終的な結末が死であるならば意味がないのではないか。人間がいずれは死ぬと決まっているならば、生きる努力はおろか、およそ人生でなにごとかをすることも無駄ではないか。人生でなにをしようと、その成果がすべて死によって消し去されるならば所詮無意味な所業ではないか。たしかに死が避けられないことが人生からあらゆる意味を奪うとしたら、人生でなにをしようとすべて無駄になるだろう。これをつきつめれば、生まれてくること自体が無意味だということになる。死は人生で起こるすべてのことを虚しくする。死はあらゆる虚無の源泉である。死は生からすべての意味を剥奪し、生きることも、努力することも、およそなにごとかをすることも無意味にする。それどころか死は、人間に自分が生まれてきたことすら後悔させる。このような事態の根底にあるのは、生きることの意味を問い求める代わりに、死に人生からあらゆる意味を奪い取る力をゆだねる姿勢である。死の絶対的な力を前にして、人間は完全に無力になる。人間は生きる意味を見いだせないだけでなく、生きる意味を問う意欲すら失う。残されているのは人生を消極的に生きることでしかない。それは人生に意味を見いだせないまま惰性で生きることである。やがてそのような状態で生きることが耐えられなくなり、精神的な死の苦しみが生物学的な死の苦しみを上回ると思えたとき、人間は死の誘惑に駆られる。生物はひたすら生き続ける生の自己目的に従属しているので、みずから命を絶つことはない。あらゆる生物種のなかで自殺するのは、生の自己目的から逸脱した人間だけである。人間はみずからの生に疑念を抱き、ときに絶望し、ときに生き続けることを拒否する。人間は、つねに生と死の岐路に立たされているのである。
生きることの原動力をなすのは生の主体性である。ひたすら生きることをめざす生の主体性は生の自己目的として具現化する。生の自己目的は、生のみによって動機づけられ、生のみを目的とする。生の自己目的において、生の主体性はひたすら生き、そして生き続けようとする。このような生の自己目的において生はそれ自体で肯定されている。しかし、人間は種に属する個体であると同時に個人史を書き連ねる主語としての個である。個体は代替可能性を本質とし、代替可能性が生殖の原理をなす。生殖によって生まれた新しい個体が元の個体と代替可能でなければ、生は個体から個体へと生き続けられないからである。それゆえ個体の限界を超えて生き続けようとする生の主体性は、個体としての人間に代替可能性を要求する。これにたいして個は「いま・ここ」にいる私として代替不可能性を本質とする。人間は個として唯一無二の存在であり、なにものによっても代替されえない。この個体と個の対極性のゆえに、代替可能性と代替不可能性がせめぎあう人間は生の自己肯定に安住できない。
人間はその存在の根底に個体と個の分裂を抱えている。個体と個の分裂というこの宿命的な存在構造のために、人間は根本的に生から離反している。しかしまた人間は生から離反しているからこそ、生を回復しようと希求する。それは本来それ自体において肯定されてあるべき生を回復しようとする本源的な欲求である。この欲求に駆られて人間は生の自己肯定の状態を追求する。だが、個体と個の分裂という宿命的な存在構造を抱えた人間は、個を離れて個体に復帰したり、個を個体に同化させたりすることによって自己肯定の状態を達成することはできない。ひとたび個体の枠を飛び出した人間は直接自己の生を肯定することはできない。生から離反した人間がその生を肯定するためには意味という媒介を必要とする。人間が自己の生を肯定するためには生を価値あるものとして評価できなければならず、そのために人間の生は意味あるものでなければならない。生との一体性から切り離された人間は、その生を肯定するために意味を必要とする。それゆえ人間はみずからに「いかにして現に生きていることを肯定できるか」と問わざるをえないのである。
個体としての人間は生の自己目的によってこの世界に生まれるが、それは生が個体から個体へと生き続けるためである。生は特定の個体に体現し、その個体が新しい個体を生むことによって生き続ける。しかし個としての人間は、なにものによっても代替されえない。種を構成する個体は死んでもその生は他の個体に受け継がれるが、唯一無二の個は個体が死ねば完全に消滅する。個の消滅とともに、個の前に広がる世界も消滅する。そしてなによりも私から私自身が消え去る。人間にとって死は不条理以外のなにものでもない。
だが、死が不条理なのは人間にとってだけである。人間以外の生物は、ただ生まれ繁殖して死ぬことを黙々と実践しており、そこに不条理めいたものはなにもない。植物の種子は発芽して成長し、花を咲かせたあと枯死する。やがて季節がめぐりふたたび種子は芽を出し、同じ成長と衰退と再生のプロセスを繰り返す。それは植物に限ったことではなく、動物でも同じである。セミは幼虫時代に暗い土のなかで長い年月を過ごしたあと地上に出て羽化する。明るい世界を自由に飛べるようになってからは数週間しか生きられず、そのあいだ交尾する相手を求めて鳴き続け、首尾よく交尾が完了したらひっそりと死ぬ。カゲロウにいたっては、羽化した成虫には食物を摂取するための口すらなく、ひたすら交尾の相手を探して飛び回り、1日たらずで死んでいく。カマキリのオスは、交尾している最中にメスに頭から食べられながら精子を送り続ける。このように虫たちはそれぞれ子孫を残す手筈を整えて死んでいく。このプロセスは太古以来何億回、何十億回と繰り返されてきた。そこに貫かれているのはひたすら生そのものを維持しようとする生の自己目的である。そこには生きる意味などない。これらの動物の生は文字どおり「無意味」である。しかしもともとかれらは意味を求めてもいなければ、意味を必要としてもいない。意味は生の自己肯定の欠如の代償である。生物にあっては、生は生の自己目的としてそれ自体で肯定されている。生が生の自己目的を遂行するプロセスを自然の条理と呼ぶならば、生物にとって生と死と再生のプロセスはまさに自然の条理である。
もしこの世界に死がなければ、生はそれ自体で永久に存続する。生がそれ自体で永久に存続するとは、生は個体の限界を超えることなく永久に存続するということである。なぜなら、もし死がなければ寿命はなくなり、生が個体の限界を超える必要もなくなるからである。生物に寿命がなければ、動物であれ植物であれ子孫をつくる必要はない。動物や植物が必死に子孫を残そうとするのは寿命があるからである。寿命がなく永久に生き続けるのであれば、もとより子孫をつくる必要はない。子孫をつくる必要がなければ成長する必要もない。それというのも、動物や植物が細胞分裂を数限りなく繰り返して成長するのは、生殖機能を成熟させて子孫をつくるためだからである。成長して生殖機能が確立したら、生殖して子孫をつくる。首尾よく生殖するために、植物は色とりどりの花を咲かせては、昆虫をおびきよせて受粉を促す。受粉して子孫を残そうというのでなければ、植物は花を咲かせることもない。それどころか植物の種子が土のなかから芽を出して、水と太陽の光を取り込んで成長することすらない。動物も死がなければ生殖して子孫を残す必要はなく、生殖能力を獲得するために他の動植や植物を食べて成長する必要もない。もちろんオスがメスを引きつけるために、色鮮やかな羽をつけたり、たてがみをなびかせたり、不相応に大きい角を生やしたりする必要もない。生殖する必要がなければ成長する必要もないので、生物はみな永久凍土に埋もれた植物の種子のような状態で永遠に生き続けるだろう。永遠に生きるとは永遠の無為と同義である。それは眠っている状態が永久に続くようなものである。夢を見ることもない暗黒の眠りが永久に続くとしたら、それは死んでいる状態といささかも変わらない。だが、永遠の無為と死は本質的に異なる。死は生の途絶であり、死ぬとは生まれて死ぬことである。生まれることがなければ死ぬこともない。永遠の無為とは死ぬのではなく、およそ生まれないのである。「およそ生まれない」とは、言葉の真の意味における無である。無はなにものも生み出さないが、死はそれと反対に誕生と成長と再生をもたらす。
そもそも生きることは不可避的に死ぬことを前提としている。死そのものは一瞬の出来事である。ある瞬間に存在が非在に転化し、そこですべてが立ち消える。その先にはなにもない。しかしその先になにもないからこそ死は生を限定できるのである。死に限定されることによって、個体の生は誕生-成長-生殖-死の過程として成立する。生は死に限定されて、はじめて生まれてから死ぬまでの生成の過程でありえるのである。もし死の先になにかあったら、たとえば「来世」があったら生は限定されない。生が死によって限定されなければ、生そのものが存在しない。なぜなら死によって限定されなければ生は永遠に続くことになり、永遠に続く生が永遠の無為に帰着することは、たったいま見たとおりである。永遠の無為とは、およそ生まれないことである。それはまさに生の自己目的の対極である。ひたすら生きることを目的とする生の自己目的は、つねに個体の生によって遂行される。生の自己目的は個体の生を反復することによって実現される。生の自己目的は、生が死によって限定されてはじめて個体の生として具現化される。個体が死んで、生はあらたな個体に受け継がれる。あらたな個体に受け継がれた生は、ふたたび死にいたるプロセスを経てさらにあらたな個体へと引き渡される。このように生の自己目的は、生が死に限定されることによって個体の生として実現され、個体の生は死を介して個体から個体へと受け渡される。死によって限定されることにより、生は永遠の無為に帰着することなく、むしろ永遠に存続するのである。