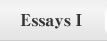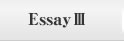II
神が存在しない以上、人生に意味や目的はない。すなわち人間が現に生きていることを価値あるものとする根拠はない。生きていることと生きていないことは完全に等価である。
しかし人間は存在しないことに対する了解をもちうる。存在しないことはありえないことではない、と。
このとき初めて存在していることが、存在しないかもしれないことに突き合わされる。存在の事実性は非存在の蓋然性によって根底から揺さぶられる。現に生きていることが、あたかもルーレットの赤と黒のごとき偶然性を帯びる。自らの生をこの端的な偶然性において受け止めるとき、人生に対するまったく新しいかかわりが求められる。すなわち、この絶対に偶然的な人生をどの点において正当化するのか。
人間にとって自己は現実の名に値する唯一のものである。それは他のいかなるものよりも身近にあって、人間は生涯それから逃れることができない。
自己とは常にこの自己であり、その一体性のゆえに危うくされている。たとえば家が火事になれば逃げ出せばよい。人が水に溺れたとして、これを見捨てることもできよう。他人が襲ってくれば返り討ちにすることも可能である。しかし自己だけは逃げることも、見捨てることも、打ち殺すこともできない。
「自己がある」ことは、ひとつの奇跡である。だが、それより驚くべきは「自己である」ということだ。人間はこの自己との全面的な一体性のなかに目覚め、他者でありうるいかなる可能性からも生涯完全に断ち切られている。
自己であること、それを実存と呼ぶ。実存はすべての本質から解除され、共同性のあらゆる紐帯から切り離されている。それゆえに実存はいかなる内容ももたない。それゆえに実存は不幸である。
しかしながら不幸は幸福の否定態として、それ自体において幸福を内包している。不幸は幸福の予感であり、幸福の可能性を暗示する。それゆえ実存は不幸の淵に滞留することを選択しないならば、幸福の可能性に賭けるよりほかない。
ここで実存に課せられるのは幸福の存在証明である。つまり「幸福は存在する」ということの証明。あたかもデカルトがコギタチオに存在論的明証性を与えたように、幸福は倫理的明証性を有する。
コギトが反省する意識にとってのみ、そしてまさに反省を遂行している時間だけ明晰判明であるように、幸福の存在証明も固有の時間を有する。
実存は幸福の瞬間に豊かさに満たされる。実存は世界を内容とし、世界は実存によって所有される。すなわち実存は世界を体験する。このとき実存と世界は互いの一体化において絶対的に肯定される。
世界体験は主体と客体のディアレクティークである。主体性が深化するのに伴い世界はその奥ゆきと広がりを増し、逆に世界の拡大は主体性の深化を促す。世界体験の強度が増すことにより幸福の存在証明はより確かなものになる。
他方、美しい音楽を聴いたあと、その感動は初めのうちこそ生々しい余韻をとどめているものの、やがて単なる感動の記憶しか残らないように、実存は常に不幸へと立ち返らざるをえない。だから実存は繰り返し幸福の存在証明を実行しなければならない。
ここにおいて幸福の存在証明が人生の目的となる。すべての行為はこの目的に向けて秩序づけられる。ここでは個々の行為は自己完結性を失い、他の行為と関連づけられる。行為は目的の達成を基準とする有意性によって測られ、それに応じて価値が付与される。
あらゆる行為は幸福の存在証明を目的とする意味と価値の連関において組織化されなければならない。